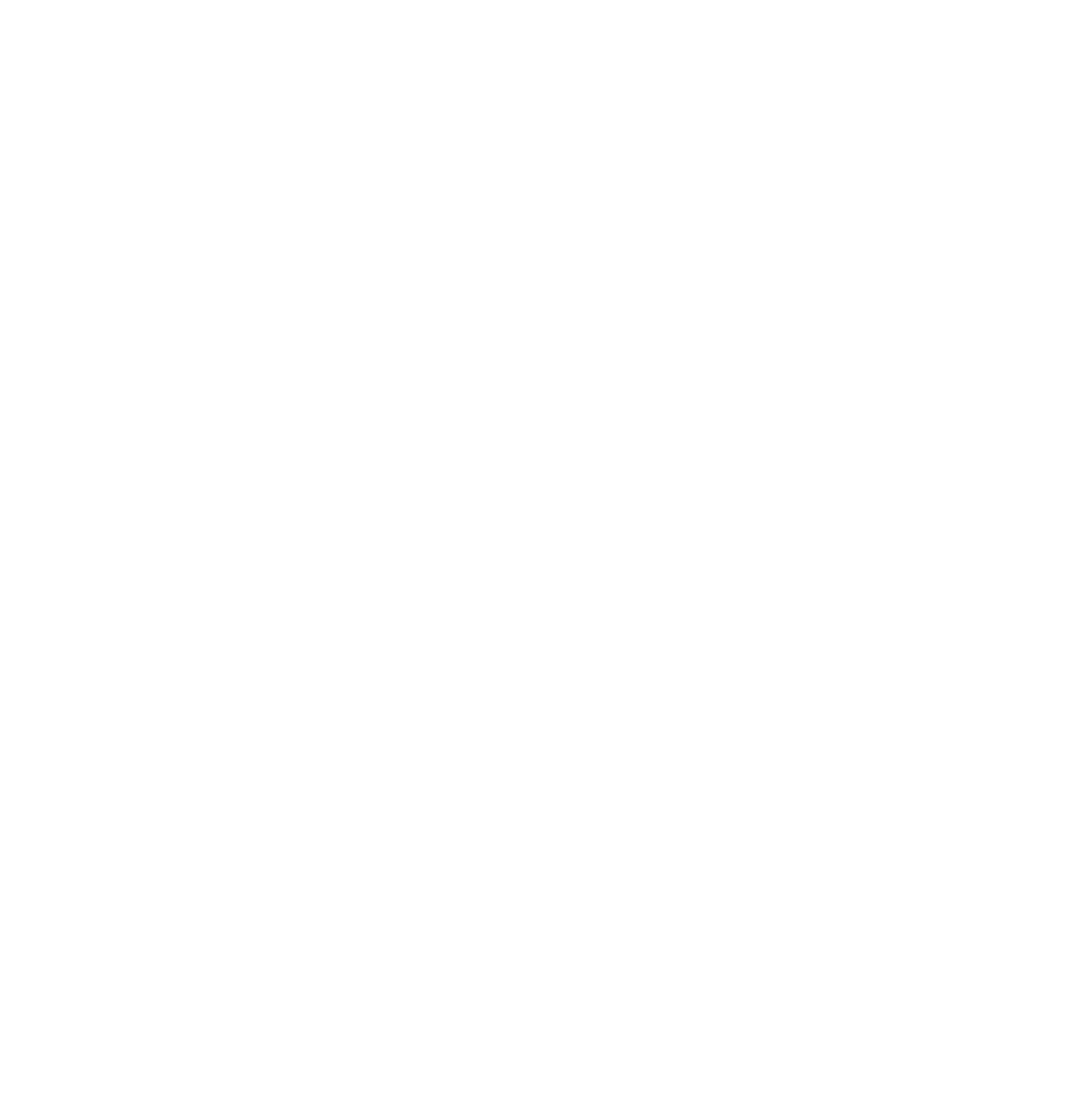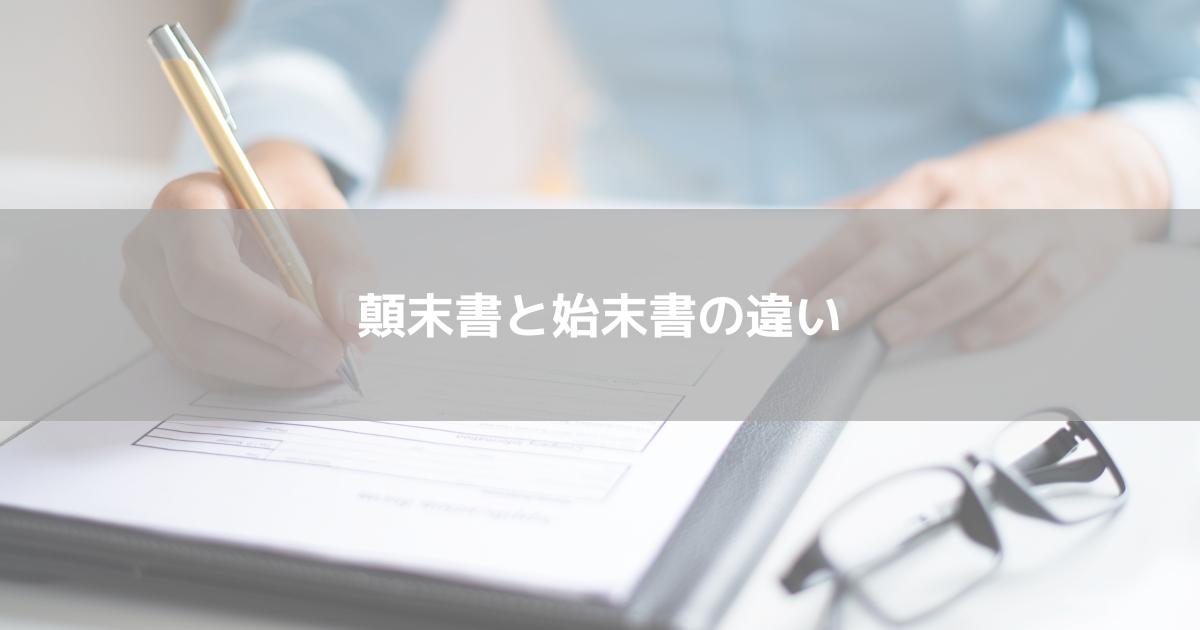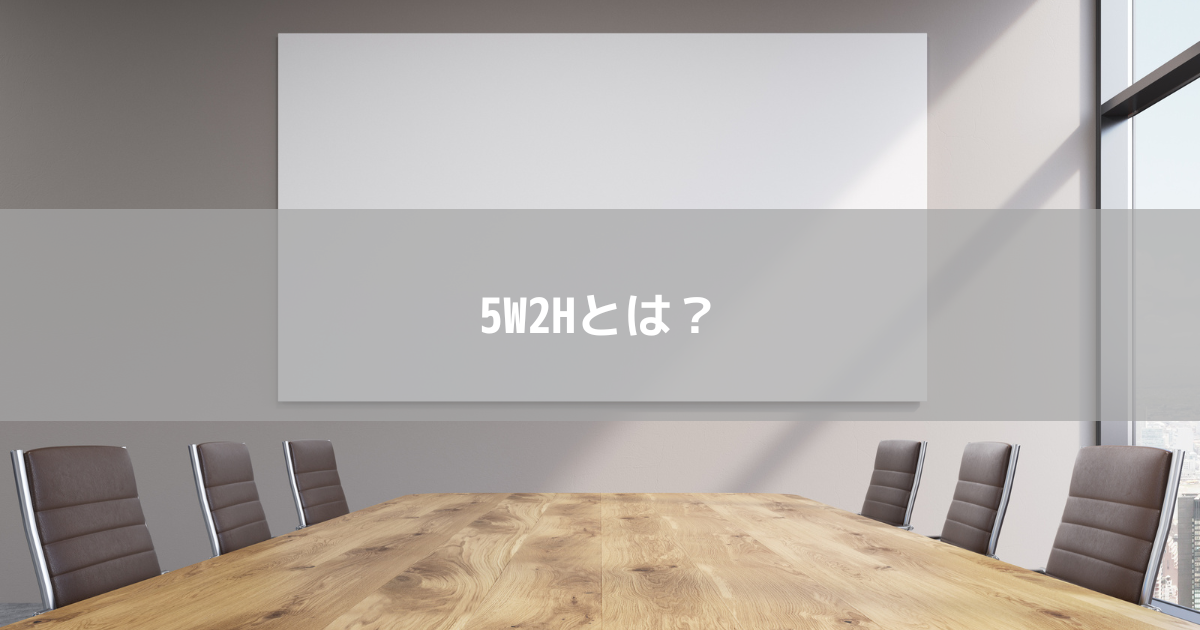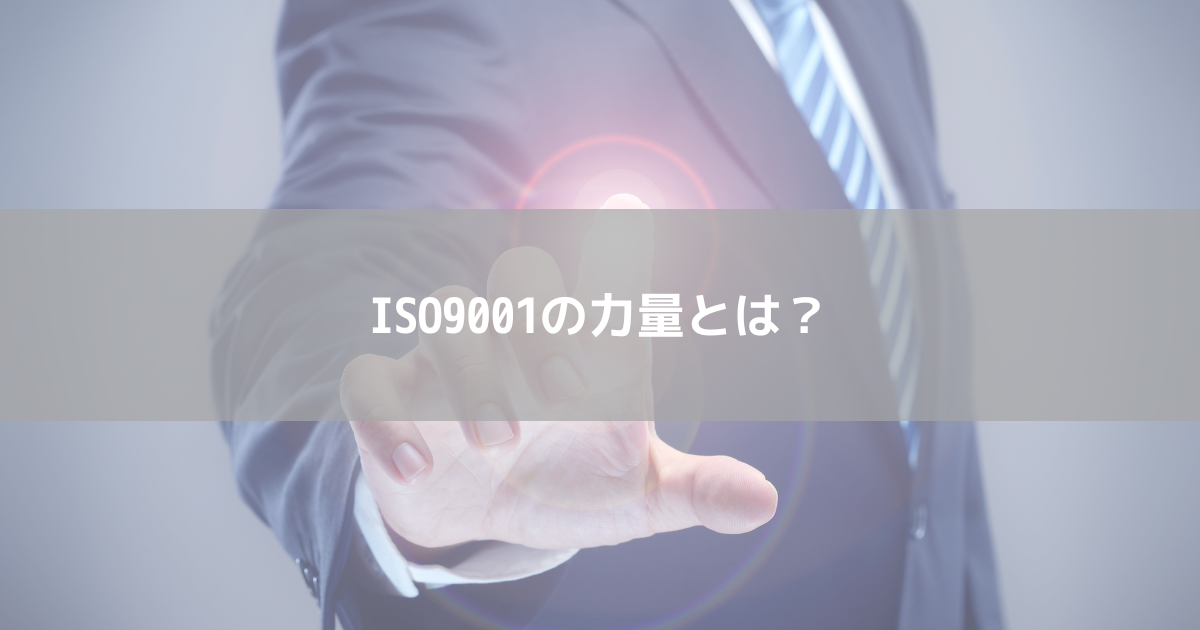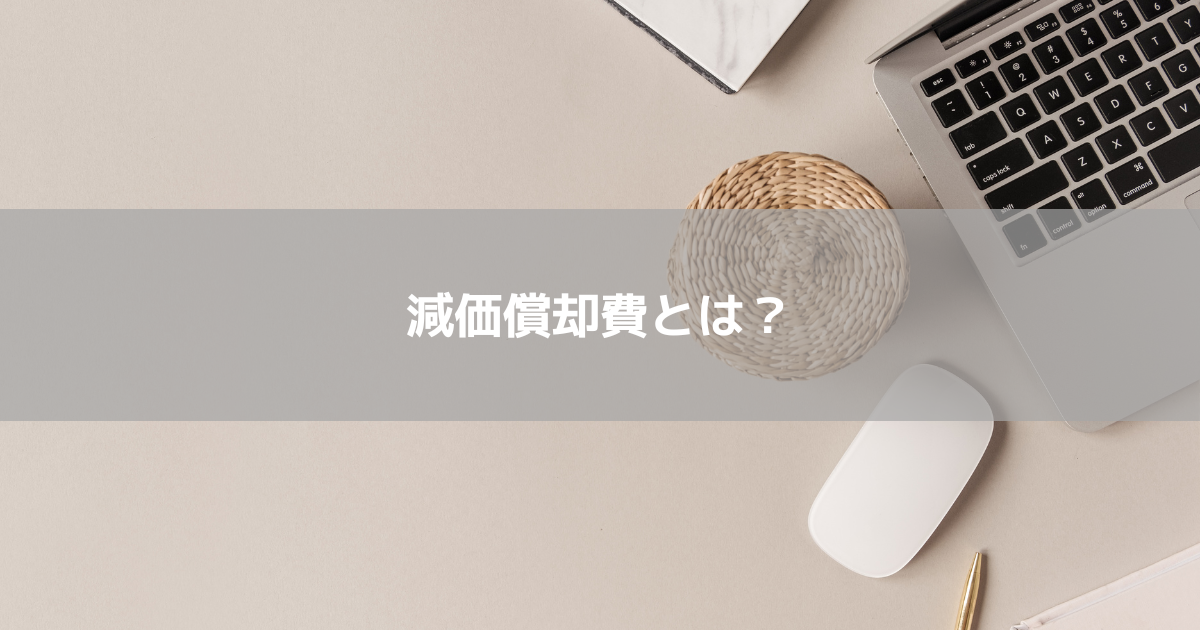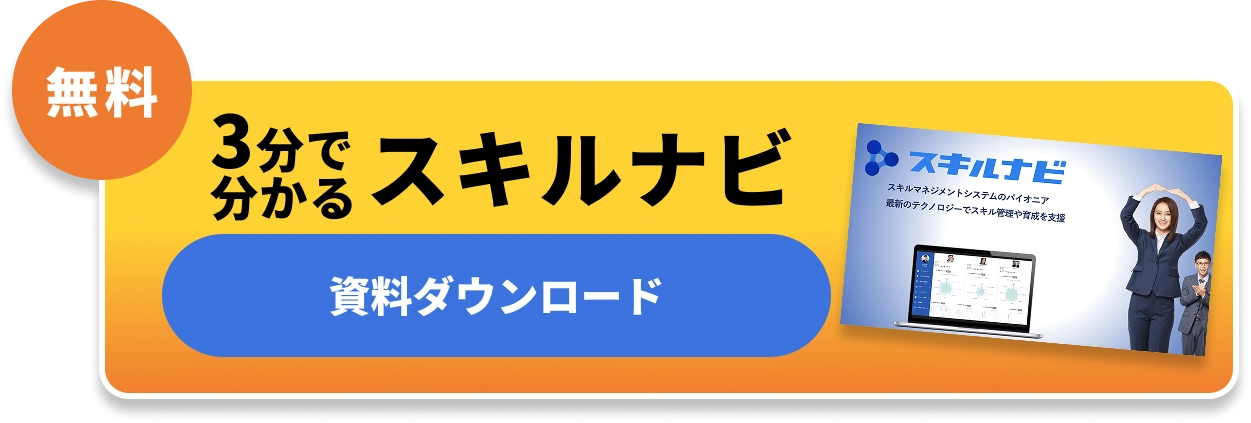ISO審査とは?種類、認証機関の選び方、費用、審査フローを解説
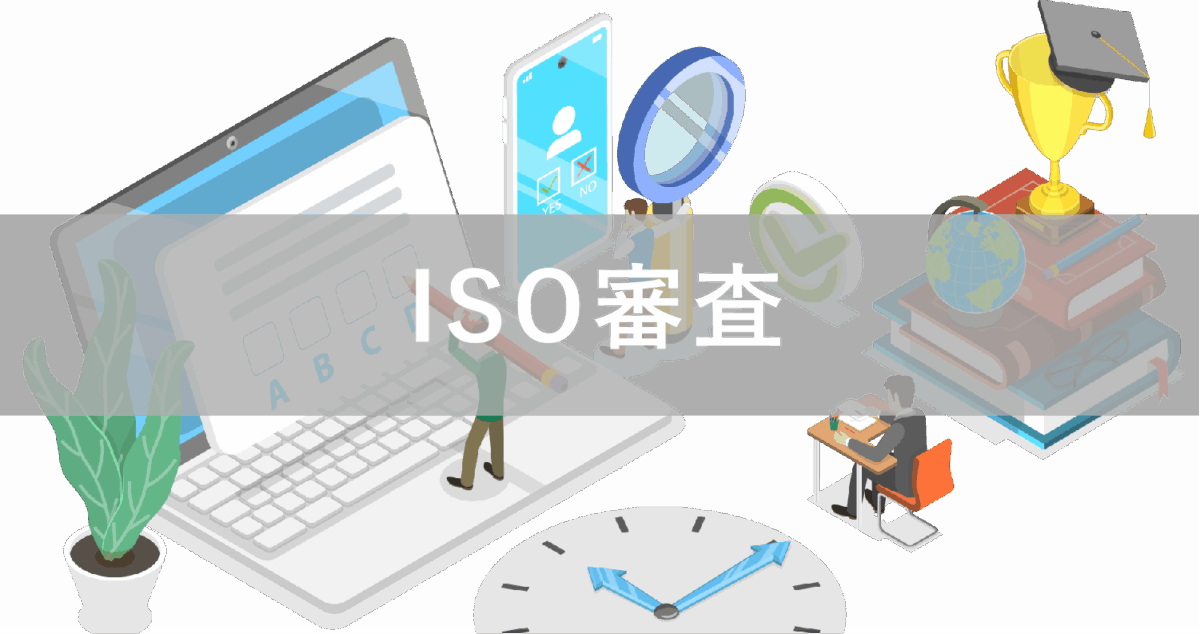
ISO審査は、国際的な標準規格にもとづき、企業や組織の仕組みや製品品質が適切であるかを第三者機関が認証する仕組みです。
認証を取得することで、品質や環境への取り組みを客観的に証明でき、取引先や顧客からの信頼向上にもつながります。
本記事では、ISO審査の基本から種類、認証機関の選び方、費用の目安、そして実際の審査のフローまでをわかりやすく解説します。
ISOの基本知識
ISOとは、スイス・ジュネーブに本部を置く非政府機関「国際標準化機構」の略称で、製品やサービスについて国際的に通用するISO規格を制定しています。
ISO規格には、製品そのものを対象とする「モノ規格」と、組織の品質活動や環境活動を管理するマネジメントシステムを対象とする「マネジメントシステム規格」があり、世界中で同水準を保証する規格として広く活用されています。
ISO審査とは?
ISO審査とは、製品やマネジメントシステムがISO規格に適合しているかを、第三者審査機関が認証する仕組みです。
審査では規格に定められた要求事項に適合しているかどうかがチェックされ、適合していると判断された場合、ISOの認証が取得できます。
ISOの認証を取得することで、企業は国際的に通用する信頼性を示すことができ、企業の信用アップや売上向上の効果が期待できます。
ISO審査の3つの種類
ISO認証を取得・維持するためには3つの審査を受ける必要があります。
本項目では、それぞれの審査の内容を詳しく解説します。
登録審査(初回審査)
登録審査は、組織がISO認証を取得するために最初に受ける審査です。
まずマネジメントシステムに関するマニュアルや規程などの書類をもとに一次審査が行われ、一次審査に通過すると二次審査へ進みます。
二次審査では実際の現場における運用状況が審査され、ISO規格の要求事項に適合していると認められた場合、正式に登録証が発行されます。
維持審査
維持審査は、登録審査によってISO認証の登録証が発行された1年後と2年後に、その仕組みや運用が継続してISO規格を満たしているかを確認するためにおこなわれる審査です。
文書や記録、現場での実践状況の確認を通じてISO規格の要求事項が守られているかをチェックします。
登録審査とは違い、登録証は新たには発行されず、また、審査は一段階のみとなっております。
更新審査
更新審査は、登録審査から3年後におこなわれる審査で、認証を継続するために必要な重要なプロセスです。
この審査では、登録審査と同じくISO規格に関わる全ての項目が対象となり、文書や運用状況を詳細に確認して審査がおこなわれます。
組織が規格に基づいた仕組みを維持・改善していることが認められると、新たに登録証が発行され、その後はまた維持審査、更新審査が繰り返されます。
審査機関の2つの種類
審査機関は、ISO認証を担当する第三者機関であり、国際認定協力機関(IAF)に加盟している「認定機関」と、認定機関から認定を受けた「認証機関」があります。
本項目ではそれぞれについて解説します。
認定機関
認定機関は、認証機関がISO審査をおこなう機関としてふさわしいかを審査・認証する役割を担う機関です。
認証を受けた認証機関のみが正式にISO審査を実施することができるようになります。
日本では「日本適合性認定協会(JAB)」と「情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC)」が認定機関として活動しています。
また、世界各国にも認定機関があり、各国の認定機関が相互認証をおこなっています。
認証機関
認証機関は、ISO認証の取得を目指す組織や企業に対して審査をおこない、ISO規格への適合性を判断する役割を持つ機関です。
日本国内には約50社の認証機関が存在し、企業は自社の業種や目的に応じて認証機関を選択することができます。
認証機関には各分野やISO規格に精通した審査員が配置されており、専門的な視点から社内文書や現場での運用実態を審査し、ISOの登録証を発行します。
ISOの審査機関を選ぶポイント
前項で述べた通り、日本国内には約50社もの認証機関が存在します。
本項目では、ISO認証を取得する際の審査機関の選び方について、4つのポイントを解説します。
対応している業界・規格
ISOの認証機関を選ぶ際には、まず自社が属する業界や取得を目指すISO規格に対応しているかを確認することが重要です。
認証機関ごとに得意とする分野や対象している業界・ISO規格が異なるため、業種に適した専門知識を持つ審査員が在籍している機関を選ぶことで、より実情に合った審査を受けられます。
自社の目的に合致した認証機関を選ぶことが、スムーズな認証取得につながります。
審査費用
ISO資格取得の審査費用は、依頼する認証機関によって異なります。
そのため、必ず複数の認証機関から相見積もりを取り、費用の内訳や条件を比較することが大切です。
単に金額の安さだけでなく、審査員の専門性やサポート体制も考慮することで、費用に見合った価値ある審査を受けることができます。
適切な相見積もりは、コスト管理と品質確保の両立に有効です。
審査内容
ISOの認証機関を選ぶ際には、審査内容に注目し、自社の業界に対する知見や審査実績が豊富な認証機関を選ぶことが重要です。
業界特有の課題や運用方法に精通している認証機関であれば、形式的なチェックにとどまらず、実務に即した指摘や改善のヒントを得られます。
そのため、認証機関の過去の実績や担当審査員の専門性を事前に確認することで、より有意義な審査につながります。
対応スピード
ISOの審査機関を選ぶ際は、対応スピードも重要なポイントです。
問い合わせや見積もり依頼に対するメールの返信状況などから、対応のスピードを事前に確認することで、審査スケジュールが遅延するリスクを減らせます。
迅速かつ丁寧な対応をおこなう認証機関は、審査当日もスムーズに進められる可能性が高く、認証取得までの全体的な効率向上につながります。
ISO審査に必要な費用の目安
- ISO審査を受ける際には、認証機関に支払う審査費用が必ず発生しますが、金額は認証機関によって異なります。
また、審査準備や書類作成のサポートとしてコンサルタントを利用する企業も多く見られます。
コンサル費用は必須ではありませんが、経験豊富なコンサルタントによる支援を受けることで、準備がスムーズになり、認証取得までの期間や手間を短縮できる場合があります。
費用は、審査費用とコンサル費用を含めて計画することで目安を把握することができるでしょう。
ISO審査のフロー
ISO認証を取得する際の審査には大きく分けて3つのフローがあります。
本項目では、それぞれのフローについて解説します。
オープニング
オープニングは、ISO審査の最初のステップで、認証機関の審査員と対象企業が顔を合わせ、審査の進め方を確認する場です。
具体的には、審査計画書を共有したり、審査範囲や重点項目、日程などの内容についてすり合わせを行います。
企業側は運用状況や組織体制を簡単に説明し、審査員は確認すべきポイントを整理することで、その後の現場審査や書類審査がスムーズに進む準備を整えます。
審査
審査は、ISO審査の中心的なステップで、経営者や管理職、現場の従業員へのヒアリングを通じて進められます。
審査員は、組織の運用がISOの要求事項に沿っており、PDCAサイクルを適切に回せているかどうかを確認します。
文書や記録の確認だけでなく、実際の業務プロセスや改善活動の実態をチェックすることで、組織のマネジメントシステムの有効性や課題を評価します。
クロージング
クロージングは、ISO審査の最後のステップで、審査員がこれまでの審査で確認した所見を対象企業と共有します。
ここでは、審査で指摘された事項や改善点について確認し、必要な対応や期限、審査後の手続きについても説明されます。
企業はこの段階で疑問点を解消し、次の改善や登録手続きに向けた準備を整えることができます。
ISO審査の結果の種類
ISO審査の結果には3つの種類があります。
本項目では、各結果の詳細について解説します。
重大な不適合
重大な不適合とは、ISO規格の要求事項に対して組織の仕組みや運用に重大な欠陥があると判断された状態を指します。
重大な不適合と判断された場合、審査はその時点で続行できず、認証を取得することはできません。
ただし、指摘を受けた事項について、再審査をおこない、是正処置の状況を示すことができれば、改善が確認され次第、改めて認証を取得できる可能性があります。
軽微な不適合
軽微な不適合とは、ISO規格の要求事項を部分的に満たせていない、または運用に小さな不備があると判断された状態を指します。
重大な欠陥ではないため、適切な修正や是正措置を行えば、認証を受けられる可能性が高いとされています。
審査後には改善計画を提出し、実施状況を確認されることで是正が認められれば、正式にISO認証を取得することができます。
観察事項
観察事項とは、ISO規格の要求事項に対して現時点不適合ではないものの、今後不適合になるリスクがあると審査員に判断された状態を指します。
重大な指摘ではないため是正措置の実施は企業の判断に任せられていますが、改善を怠ると次回審査で不適合とみなされるリスクがあります。
そのため、是正しない場合には理由を説明できるよう準備しておくことが重要です。
ISO審査のよくある質問
ISO審査をはじめて実施する際には不明点も多々あるかと思われます。
本項目では、ISO審査を実施する際によくある質問を2つピックアップし、回答を紹介します。
ISO審査用に準備することはある?
ISO規格の種類ごとにISO審査の内容は変わりますが、どの規格の審査を受けるとしても、ISO審査に向けて特別に業務を大きく変える必要はなく、基本的には日常業務がISO規格の要求事項に沿っているかを確認することが重要です。
さらに、より万全な体制を整えたい場合には、外部のコンサルタントや専門家などの人材を活用し、効率的に準備を進めることも有効な方法です。
ISO審査に落ちる可能性はある?
ISO審査では、重大な不適合が見つかった場合でも、すぐに適切な是正措置をおこなうことができれば審査に落ちる可能性は低いです。
ただし、重大な法令違反や社会的信用を損なう事態が発覚した場合には、是正の有無にかかわらず認証が取り消されるリスクがあります。
したがって、普段から法令順守を徹底し、改善体制を整えておくことが重要です。
ISO審査で認証を取得し、企業の社会的信用を高めよう
ISO審査は、組織の仕組みや製品が国際規格に適合しているかを確認し、認証を通じて信頼性を対外的に示す重要なプロセスです。
登録審査・維持審査・更新審査を経て認証を取得・継続することで、企業は品質や環境への取り組みを継続的に改善し、社会的信用を高めることができます。
また、自社に合った審査機関を選び、適切な準備と改善をおこなうことが、ISO活用の大きな第一歩となります。
ぜひ、ISO審査で認証を取得し、企業の社会的信用を高めてみてはいかがでしょうか。