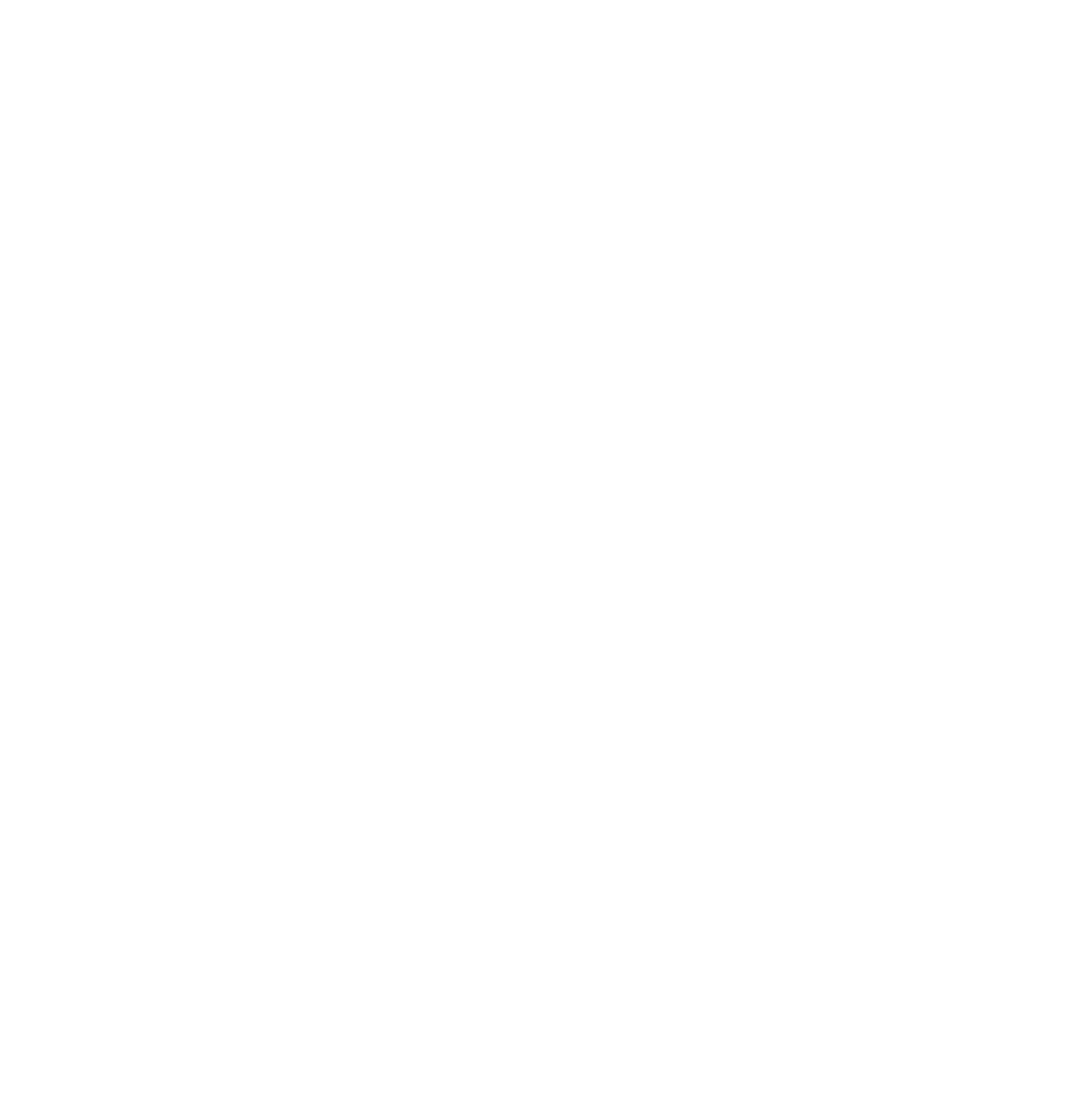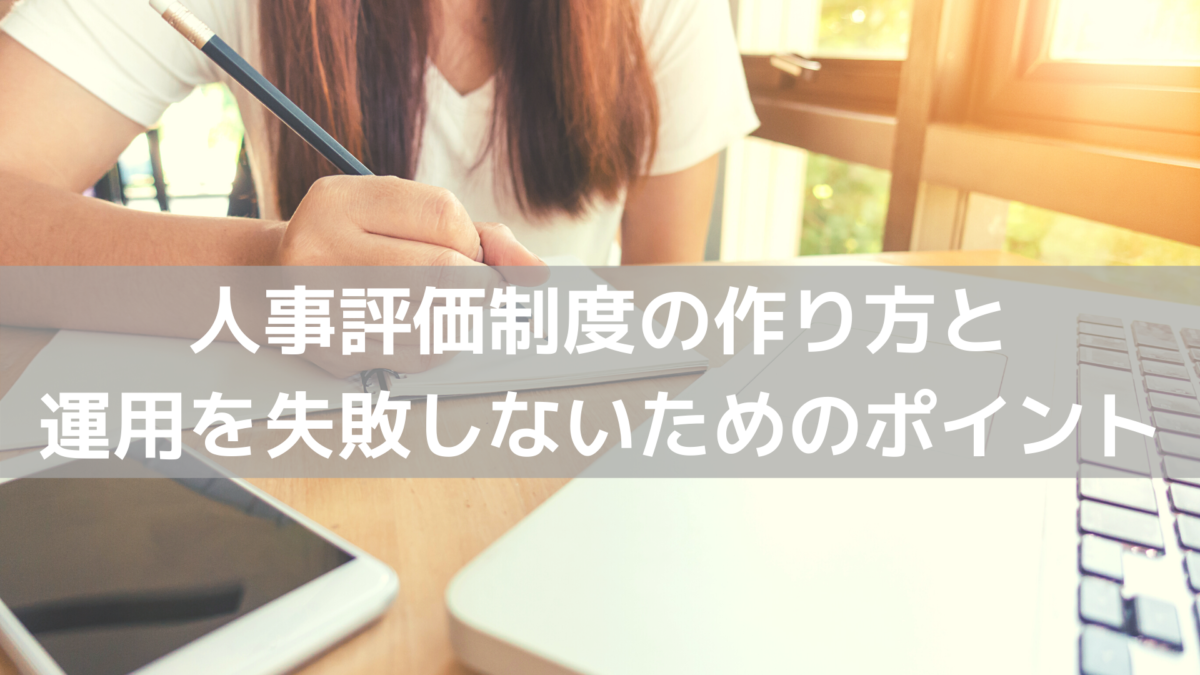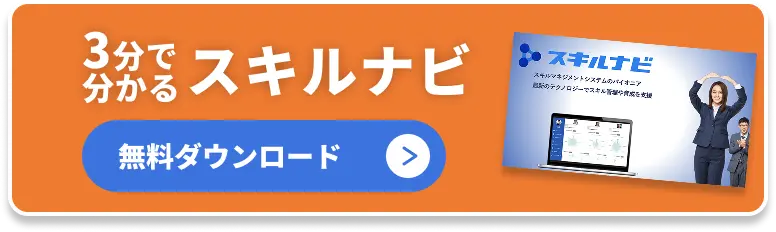人事評価に目標設定が必要な理由!職種ごとの設定例も紹介

企業の成長と従業員のモチベーション向上を両立させるために、人事評価における「目標設定」は欠かせません。目標を設定することで評価基準が明確になり、従業員は自分が何を目指すべきかを理解できます。
また、評価者側も公平かつ納得感のある判断ができるようになり、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
本記事では、人事評価での目標設定の意義から、具体的な設定方法、職種ごとの例、失敗しないためのポイントまで詳しく解説します。
人事評価における目標設定とは?
人事評価における目標設定とは、組織の戦略と個人の行動をつなぐ橋渡しの役割を果たします。
目標がなければ何を評価すべきかが不明確となり、評価の納得感も損なわれます。
具体的な目標を設定することで、社員は行動の方向性を理解し、自分の業務が組織の成果にどう貢献しているかを意識しながら取り組むことができます。
効果的な目標設定のための事前準備
良い目標は思いつきで立てられるものではなく、現状の把握や課題の整理といった準備があってこそ実効性が高まります。
ここでは、適切な目標を設定するために必要な事前準備のポイントを解説します。
現状分析と課題の洗い出し
効果的な目標設定には、まず自分やチームの現状を客観的に振り返ることが欠かせません。
売上や成果といった実績データ、日々の行動面などを多角的に分析し、「何が課題なのか」「どの部分を伸ばす必要があるのか」を明確にします。
分析結果を言語化することで、具体性のある目標設定につながり、実行可能な改善策が見えてきます。
進行状況の把握
立てた目標を達成するためには、進捗の可視化と定期的な振り返りの仕組みづくりが重要です。
月次や週次で進行状況を確認し、必要に応じて計画を見直すことで、目標達成に向けた軌道修正が可能になります。
また、上司との定期面談を通じてフィードバックを受け、課題の再整理や改善策の検討を行うことで、着実な成長につなげられます。
人事評価で目標設定を行うメリット
人事評価における目標設定には、評価される従業員と評価を行う管理者の双方に大きなメリットがあります。
従業員は評価基準が明確になり、自身の成長やキャリア形成につながる行動がとりやすくなります。一方で管理者は、公平で納得感のある評価ができ、チーム全体のパフォーマンス向上にもつなげられます。
評価される側が得られるメリット
目標設定は、評価される従業員にとって働く意義や成長の方向性を明確にする重要なプロセスです。
何を達成すれば評価されるのかが具体的にわかることで、日々の行動指針が定まり、自らのキャリア形成にもつながります。また、評価への納得感が高まり、モチベーション向上にも大きく寄与します。
評価基準の明確化
目標が明確に設定されていることで、従業員は「何を達成すれば評価されるのか」「何を重視して行動すべきか」を具体的に理解できます。
これにより、評価の基準が曖昧なまま進むことを防ぎ、不公平感の少ない納得度の高い評価が可能になります。
評価される側にとっても安心感が生まれ、行動の優先順位をつけやすくなる点が大きなメリットです。
従業員のモチベーションアップ
明確な目標が設定されることで、従業員は自分が目指すべきゴールを具体的にイメージでき、日々の業務に目的意識を持って取り組めるようになります。
達成すれば評価や報酬に反映されるという見通しが、挑戦意欲や主体性を高める効果もあります。
結果として、モチベーションが持続しやすくなり、個々のパフォーマンス向上につながります。
能力・スキルの向上
目標は単なる評価基準にとどまらず、自己成長のための指標としても機能します。
従業員は目標を達成する過程で必要な知識やスキルを習得し、専門性や業務遂行力を高めることができます。
また、定期的な振り返りの軸にもなるため、自分の成長度合いや課題を客観的に把握でき、次のステップへの具体的な行動計画につなげられます。
組織への理解度アップ
企業や部門の方針と個人目標を紐づけることで、自分の業務が組織全体の成果にどう貢献しているのかを理解できるようになります。
このつながりが明確になることで、一人ひとりの行動が戦略的になり、全社的な方向性に沿った具体的なアクションが取れるようになります。
結果として、組織全体の一体感や目標達成への推進力が高まります。
評価側が得られるメリット
人事評価における目標設定は、評価する管理者や経営層にとっても大きな利点があります。
あらかじめ明確な目標があることで、感覚や主観に頼らず公平な評価が可能となり、フィードバックもしやすくなります。
さらに、チーム全体の動きを可視化できるため、組織のパフォーマンス向上や人材育成の戦略設計にも役立ちます。
組織全体の生産性向上
目標設定により、業務の優先順位が明確になり、従業員は成果に直結する行動へ集中できます。
成果に対する意識が高まることで業務改善も促進され、チーム全体の効率が向上します。
さらに、定期的なフィードバックや進捗確認によってPDCAサイクルが円滑に回り、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
従業員の帰属意識・主体性の向上
明確な目標設定は、従業員が自らの役割や期待値を理解するきっかけとなり、主体的な行動を促します。
自分の取り組みが組織の成果に直結するという実感が得られることで、会社への帰属意識も高まります。
さらに、上司との面談や定期的なフィードバックを通じて、自ら改善策を考え実行する姿勢が育まれ、組織全体のエンゲージメント向上にもつながります。
人事評価で使われる目標の種類
人事評価で設定される目標にはいくつかの種類があり、評価の目的や役割に応じて適切に使い分けることが重要です。
数値で測定できるものから行動や姿勢を評価するものまで、多角的な視点で設定することで、従業員の成果と成長の両方をバランスよく評価できます。
定量目標・定性目標
定量目標は売上額や件数、進捗率など、数値で測定できる成果を指します。客観的に達成度を把握できるため、評価の透明性が高まります。
一方、定性目標は顧客満足度の向上やチームワークの強化、リーダーシップ発揮といった、数値化が難しい行動や姿勢を評価するものです。
両者を組み合わせることで、業績と成長の双方をバランスよく評価できます。
業績目標・能力目標・情意目標
業績目標は売上やプロジェクト達成など、成果に直結する数値や結果を指します。
能力目標は業務遂行に必要な知識・スキルの習得や専門性の向上を評価対象とします。情意目標は主体性や協調性、リーダーシップなど、業務への姿勢や取り組み方を評価するものです。
これら3つを組み合わせることで、結果だけでなく成長や行動面も含めた総合的な評価が可能になります。
目標設定の基本①SMARTの法則とは?
効果的な目標を立てるためには、抽象的な理想ではなく、実行可能で測定できる具体的な指標が必要です。
そこで役立つのが「SMARTの法則」です。
Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限)の5つの観点で目標を設計することで、実効性の高い目標設定が可能になります。
Specific(具体的)
目標は誰が見てもわかる具体的な内容で設定することが重要です。
「売上を上げる」ではなく「新規顧客を月5件獲得する」「問い合わせ件数を前月比20%増加させる」といったように、曖昧な表現ではなく明確な行動や成果を示します。
具体性を持たせることで、従業員が自分の役割を理解しやすくなり、達成に向けた行動計画も立てやすくなります。
Measurable(測定可能)
目標は達成度を客観的に判断できる指標で設定することが大切です。
「頑張る」「改善する」といった曖昧な表現ではなく、「売上1,000万円達成」「顧客満足度を80%以上に向上」など、数値や具体的な成果で測定できる形にします。
測定可能な目標は進捗管理もしやすく、達成度を評価する際の基準としても機能します。
Achievable(達成可能)
目標は高すぎても低すぎても効果が薄れてしまいます。従業員のスキルや業務環境を踏まえ、現実的に達成可能な水準で設定することが重要です。
少し努力すれば手が届くレベルの目標は、挑戦意欲を高めながらも無理のないパフォーマンス発揮を促します。
こうした達成可能な目標は、モチベーションの維持と継続的な成長につながります。
Relevant(関連性)
目標は個人の成長だけでなく、企業や部門の方針・戦略と関連性を持たせることが重要です。
自分の業務が組織全体の成果にどう貢献するのかを理解できる目標であれば、従業員の納得感が高まり、行動が戦略的になります。
個人目標と組織目標が連動することで、一体感を持って業務に取り組むことができ、成果創出にもつながります。
Time-bound(期限)
目標には必ず達成期限を設定することが重要です。
「いつまでに」という期限がなければ、行動が後回しになりやすく、効果的な進捗管理もできません。
「3か月以内に」「今期末までに」といった具体的な期限を設けることで、優先順位を明確にし、計画的に取り組めるようになります。期限を区切ることで、達成への緊張感や行動のスピードも高まります。
目標設定の基本②ベーシック法とは?
ベーシック法は、目標設定を「項目」「達成基準」「期限」「達成計画」の4つの要素に分解して設計する方法です。
SMARTの法則が目標の質を高めるためのチェックリストであるのに対し、ベーシック法は目標達成に必要な具体的ステップを整理する実践的なフレームワークです。シンプルながら抜け漏れのない目標設定が可能になるため、多くの企業で活用されています。
目標項目
ベーシック法の第一ステップは、達成すべき目標の項目を明確化することです。
具体的な業務や成果物を特定し、「売上向上」「業務効率化」「顧客満足度改善」などテーマを設定します。
ここで重要なのは、抽象的な理想ではなく、組織や部門の方針に沿った具体的なゴールを掲げることです。明確な目標項目があれば、チーム全体の認識を揃えやすくなります。
達成基準
次に、目標の達成度を判断するための基準を明確に設定します。
「売上を伸ばす」ではなく「新規契約数を月10件獲得」「業務処理時間を20%短縮」といった数値や具体的成果で示すことがポイントです。
達成基準が明確であれば、進捗管理や評価時の判断がしやすくなり、従業員も目指すべき水準を具体的にイメージできます。
期限設定
目標には必ず達成期限を設けます。
「できるだけ早く」ではなく「3か月以内」「今期末まで」といった具体的な期限を設定することで、計画的な行動が可能になります。
期限があることで業務の優先順位が明確になり、日々の進捗管理もしやすくなります。また、適切な期限は達成への意識を高め、行動スピードを促進する効果もあります。
達成計画
設定した目標を実現するために、具体的な行動計画を立てます。
必要なリソースやステップを明確化し、「誰が・いつまでに・どのように実施するか」を整理します。
達成計画があることで、目標が単なる理想で終わらず、現実的な行動に落とし込まれます。チームで共有することで進捗の確認もしやすくなり、達成に向けた一体感も高まります。
人事評価における目標設定例【職種ごと】
目標設定は職種や役割によって求められる成果やスキルが異なるため、それぞれに応じた具体例を参考にすることが重要です。
ここでは営業職や事務職、企画・マーケティング職など、さまざまな職種ごとに実際の目標設定例を紹介します。
具体的なイメージを持つことで、自身やチームの目標をより現実的かつ効果的に設定できるようになります。
営業職
営業職では、売上や新規顧客獲得数など、成果が明確に数値化できる目標が中心となります。
例として「新規顧客を月5社開拓」「既存顧客への追加提案で月間売上を20%向上」「商談化率を前期比10%改善」といった目標が考えられます。
これらは業績への直接的な貢献が測定できるため、評価基準としても適しています。
事務職
事務職では、業務効率や正確性の向上を目的とした目標が適しています。
例として「月次報告書の作成期間を従来の5日から3日に短縮」「入力ミス率を0.5%以下に削減」「社内問い合わせへの初回対応を1営業日以内に実施」などが挙げられます。
業務の質とスピードを高める目標を設定することで、部門全体の生産性向上につながります。
管理部門・バックオフィス職
管理部門やバックオフィス職では、組織運営を支える仕組みづくりやリスク管理が重要です。
例として「契約書管理フローを見直し、承認までの期間を20%短縮」「月次決算を従来より2営業日早く完了」「社内規程の改訂案を四半期ごとに1件提出」などが考えられます。
業務プロセスの改善や制度整備に直結する目標が評価の軸となります。
企画・マーケティング職
企画・マーケティング職では、施策の成果やブランド価値向上を数値化した目標が適しています。
例として「新規リードを月50件獲得」「キャンペーン施策でサイト訪問者数を前期比30%増加」「新商品の企画提案を四半期で2件実施」などが挙げられます。
施策の効果を測定可能な指標で設定することで、戦略的な評価が可能になります。
コンサルタント・研究職
コンサルタントや研究職では、専門知識の活用や成果創出につながる目標が求められます。
例として「クライアント向け改善提案を月3件提出」「調査レポートを四半期ごとに1本発表」「新規研究テーマのプロジェクトを年内に1件立ち上げ」などが考えられます。
専門性を発揮し、顧客価値や知見の蓄積に直結する目標が評価の基準となります。
サービス職
サービス職では、顧客満足度の向上や応対品質の改善を重視した目標が適しています。
例として「顧客満足度アンケートで平均4.5点以上を維持」「クレーム件数を前期比30%削減」「新人スタッフの教育プログラムを3か月以内に策定・実施」などが挙げられます。
顧客対応の質を数値や具体的行動で評価することで、サービスレベルの向上につながります。
クリエイティブ職
クリエイティブ職では、制作物の品質やプロジェクト進行の効率化に関する目標が重要です。
例として「デザイン提案の初回採用率を50%以上に向上」「制作プロジェクトの納期遵守率を95%以上に維持」「新しいデザイン手法やツールを四半期ごとに1件導入」などが挙げられます。
クリエイティブの質と業務遂行力を両立する目標が評価の軸となります。
エンジニア職
エンジニア職では、開発スピードや品質向上、技術習得に関する目標が中心となります。
例として「新機能のリリースサイクルを平均2週間短縮」「バグ発生率を前期比20%削減」「新しい開発言語やフレームワークを半年以内に習得」などが挙げられます。
開発の効率と品質を高める目標を設定することで、プロジェクト全体の成果に貢献できます。
医療・保育職
医療・保育職では、安全性の確保や利用者満足度向上を重視した目標が重要です。
例として「事故・インシデント件数を前年より20%削減」「保護者アンケートで満足度90%以上を維持」「定期研修を半年以内に2回受講し、最新の専門知識を習得」などが挙げられます。
現場の安全性とサービス品質の向上を両立する目標が評価の基準となります。
公務員職
公務員職では、市民サービスの質や行政手続きの効率化を目的とした目標が重視されます。
例として「窓口対応の平均待ち時間を20%短縮」「市民アンケートで満足度80%以上を達成」「新しい業務改善提案を四半期ごとに1件提出」などが挙げられます。
公共性と効率性の両立を目指す目標を設定することで、住民サービスの向上につながります。
管理職・マネージャー
管理職やマネージャー職では、チームマネジメントと組織成果の両立を重視した目標が重要です。
例として「部門の業績目標を達成(前年比売上110%)」「メンバーとの1on1を月2回実施」「離職率を前期比10%削減」などが挙げられます。
チームの成果創出と人材育成の両面から評価できる目標設定が効果的です。
人事評価の目標設定でよくある失敗と対策
人事評価の目標設定は、組織や個人の成長を促す重要なプロセスですが、設定の仕方を誤ると形骸化してしまうことがあります。
目標が曖昧だったり、現実とかけ離れていたりすると、従業員のモチベーション低下や評価への不満につながりかねません。
ここでは、目標設定で陥りやすい失敗と、それを防ぐための具体的な対策を解説します。
評価基準が明確でない
評価者ごとに基準が異なると、同じ成果でも評価が分かれ、不公平感や不信感を招く恐れがあります。
こうした状況は評価制度そのものへの信頼を損ない、従業員のモチベーション低下にもつながります。
この問題を防ぐためには、評価基準を明文化し、全員に共有することが不可欠です。誰もが納得できる基準を設定することで、公平で透明性の高い評価が実現します。
目標が曖昧になっている
「頑張る」「努力する」といった抽象的な目標は、評価者と被評価者の間で解釈のズレが生じやすく、評価時の納得感を損ねます。
こうした曖昧さを防ぐには、SMARTの原則を活用し、具体的かつ測定可能な目標を設定することが重要です。
誰が見ても達成度を判断できる目標を設けることで、評価の客観性と公平性が高まります。
目標が高すぎる/低すぎる
現実的でないほど高い目標は達成意欲を削ぎ、逆に簡単すぎる目標は挑戦性がなく成長の機会を失わせます。
どちらも従業員のモチベーション低下や評価制度の形骸化につながる恐れがあります。
そのため、従業員の能力や業務内容、組織の状況を考慮し、適切な難易度で達成可能かつ成長を促す目標を設定することが重要です。
フィードバックが不足している
評価結果の通知だけで具体的なフィードバックがないと、従業員は自分の課題や改善点を理解できず、成長の機会を逃してしまいます。
この状況を避けるためには、評価後の定期的な1on1ミーティングを実施し、具体的なフィードバックと今後のアクションプランを共有することが重要です。
対話を通じて理解を深めることで、成長意欲と改善行動につながります。
目標と経営戦略が連動していない
個人の目標が経営戦略や部門方針と結びついていない場合、組織全体の方向性と乖離した取り組みになりかねません。
結果として、個人の努力が組織成果に直結せず、評価制度の意義も薄れてしまいます。
この課題を防ぐためには、経営目標を部門・個人レベルにブレイクダウンし、全員が戦略に沿った行動を取れるように目標を設計することが重要です。
目標設定で従業員の成長と組織成果を両立させよう
人事評価における目標設定は、従業員一人ひとりの成長と組織全体の成果を両立させるための重要なプロセスです。
明確で適切な目標は、業務への納得感やモチベーションを高めるだけでなく、経営戦略の実現にも直結します。こうした仕組みを定着させるには、目標の見える化や進捗管理、フィードバックの仕組みが欠かせません。
スキルナビなら、OKRやMBOを活用した目標設定を基にした進捗モニタリング、評価管理をシステムで一元化でき、従業員と組織の成長を同時に支援します。
人事評価の効果を最大化したい方は、ぜひスキルナビの導入をご検討ください。