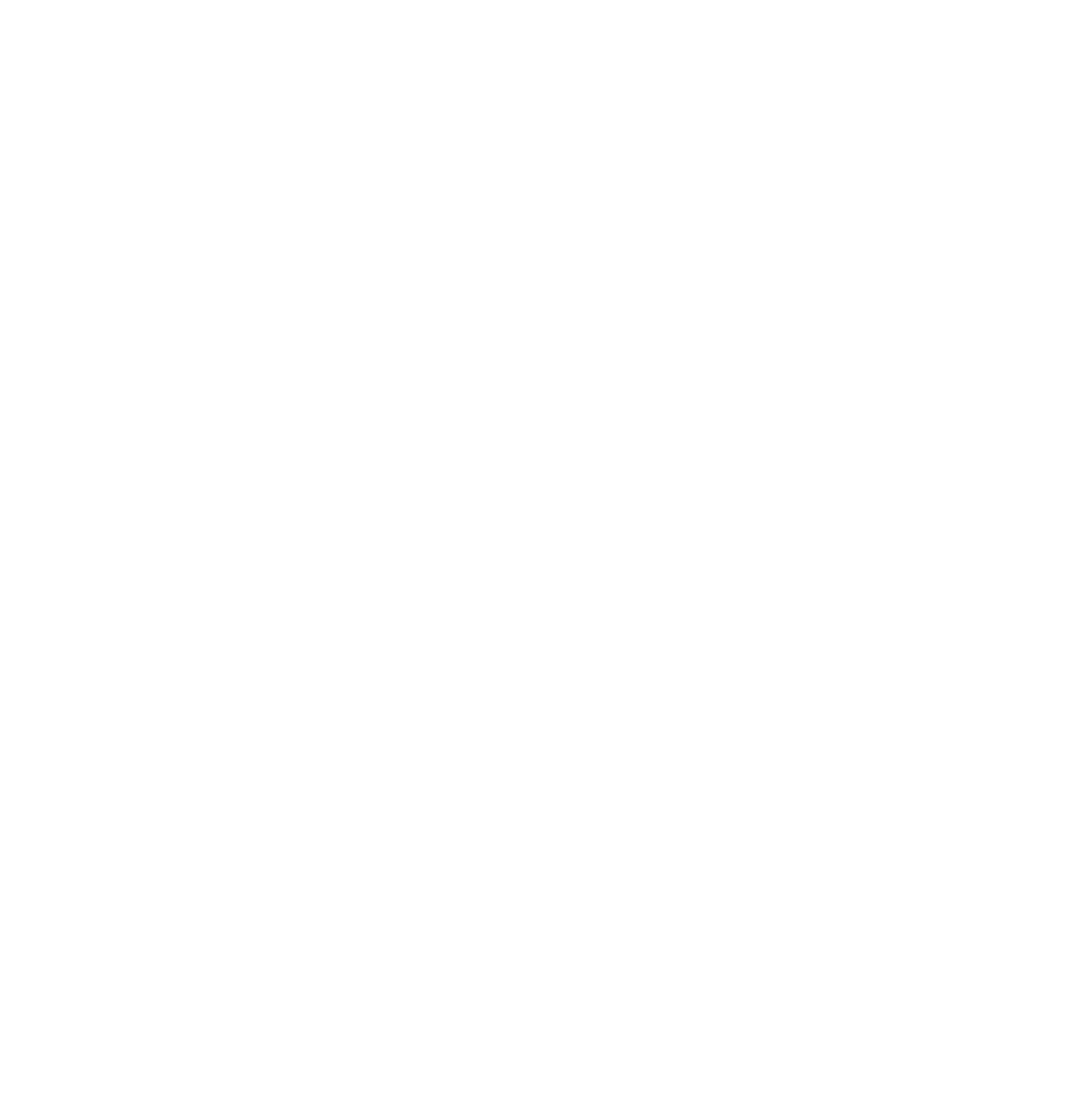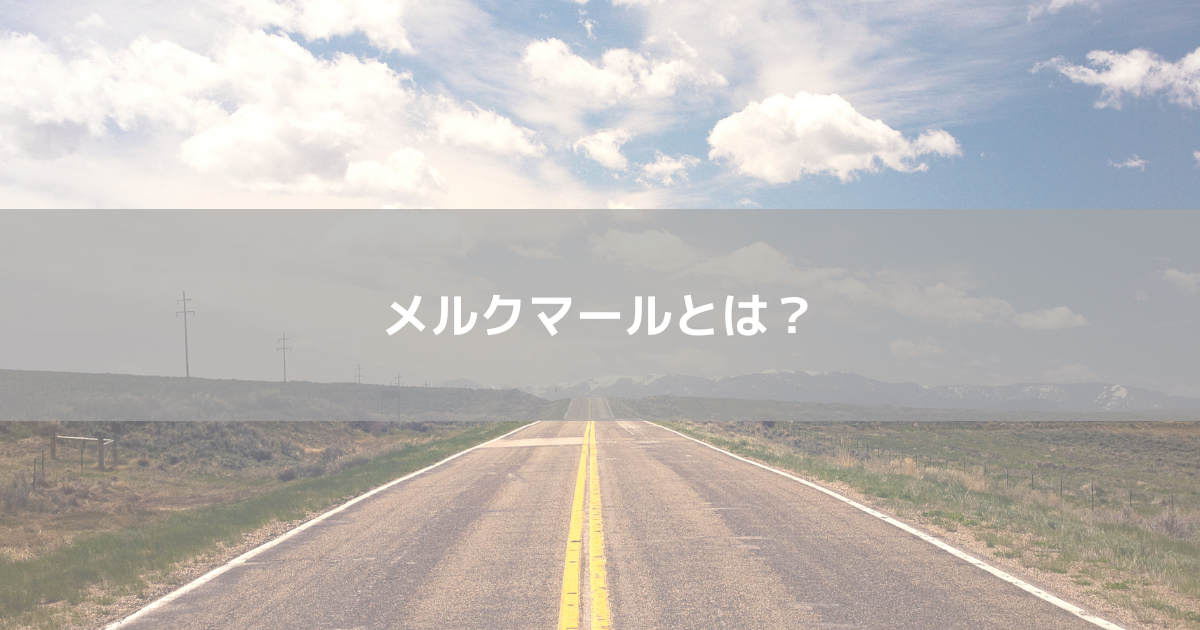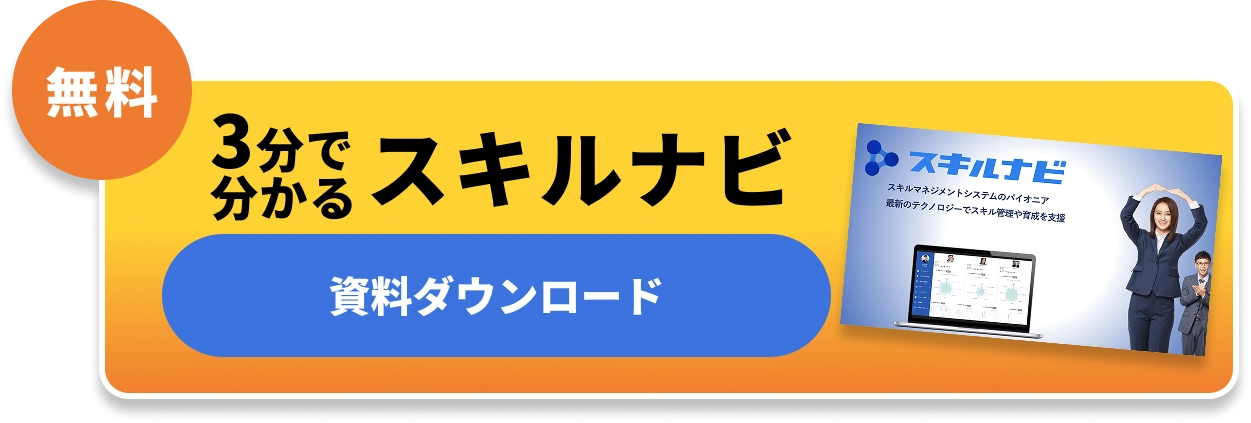暗黙知と形式知って?違いや具体例、変換手法も解説
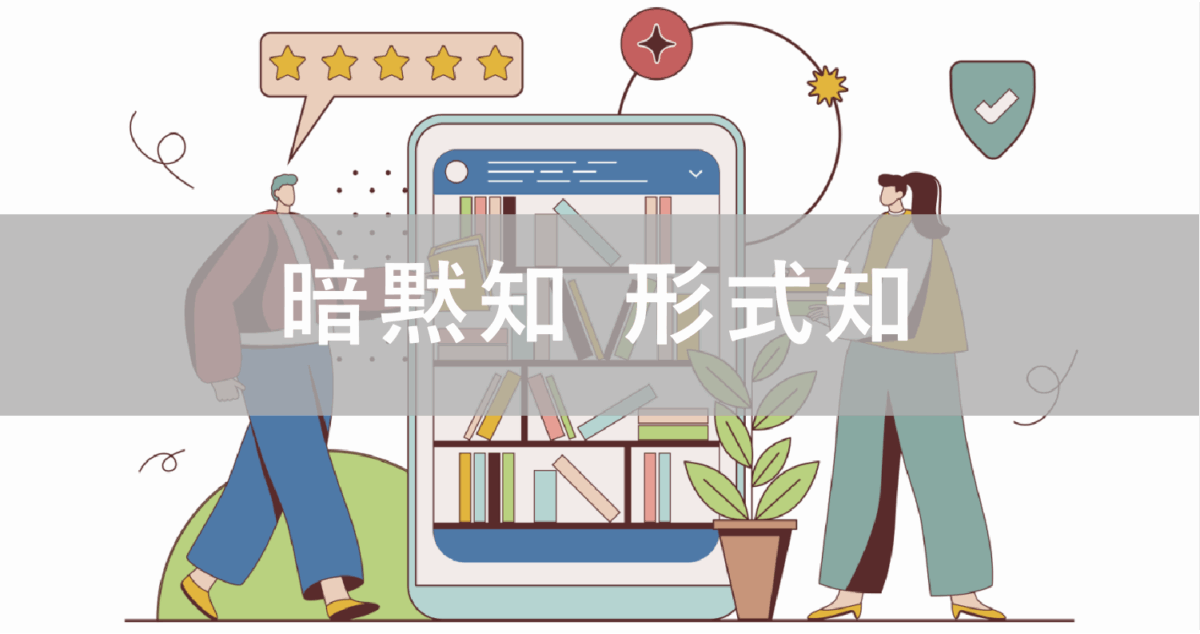
ビジネスでは、経験や勘に基づく「暗黙知」と、マニュアルやデータとして共有できる「形式知」の両方が存在します。
これらは違う概念ですが、それぞれをうまく活用することで業務効率や人材育成、組織の競争力向上につながります。
本コラムでは、暗黙知と形式知の違いや具体例、そして暗黙知を形式知へと変換する方法についてわかりやすく解説します。
暗黙知と形式知とは?
そもそも暗黙知と形式知とはどのようなものなのでしょうか。
本項目ではそれぞれの定義と具体例から、その違いについて解説します。
暗黙知の定義と具体例
暗黙知とは、ハンガリーの学者マイケル・ポランニーが著書『暗黙知の次元』で提唱した概念で、言葉や図式では表現しにくい、暗黙的な知識のことを指します。
たとえば職人が培った熟練の技術、営業現場で磨かれる臨機応変なトークスキル、デザイナーが持つ美的センスなどは、マニュアル化が難しい典型的な暗黙知の例です。
形式知の定義と具体例
形式知とは、暗黙知の対義語であり、言語や数値、図式などを用いてマニュアルやデータとして体系的に表現、言語化された客観的な知識を指します。たとえば売上データや、機械の操作マニュアル、業務手順書などは、形式知の代表的な例であり、他者に説明・共有しやすいことが特徴のひとつといえます。
暗黙知と形式知の違い
暗黙知と形式知の違いを表で整理すると以下のようになります。
| 暗黙知 | 形式知 | |
| 定義 | 言葉や図式で表現しにくい、経験や感覚に基づく知識 | 言語や数値、図式で明確に表現された客観的な知識 |
| 特徴 | 個人に内在しやすく、伝達や共有が難しい | マニュアルやデータ化しやすく、伝達や共有が可能 |
| 具体例 | 職人の技術、営業のトークスキル、デザイナーのセンス | 売上データ、操作マニュアル、業務手順書 |
| 伝達方法 | OJTや観察、体験など身体経験を伴う共同作業を通じた学習 | 文書、マニュアルなどの言語化された資料や、口頭指導などの言語的媒介を通じた学習 |
暗黙知を放置することによるリスクと弊害
暗黙知を放置するとさまざまなリスクや弊害が生じる可能性があります。
本項目では具体的な例について解説します。
業務のブラックボックス化
暗黙知が共有されず個人の中に留まると、その人しか分からない業務や手順が増え、いわゆる「ブラックボックス化」が生じます。
その結果として、担当者が不在になると業務が滞ったり、突発的なトラブルに対する緊急対応ができなかったりと、組織全体の機動力や柔軟性が著しく低下するリスクがあります。
人材育成スピードの低下
暗黙知に依存し、経験や勘に頼る明けでは、スキル習得のペースが遅くなり、人材育成のスピードが低下してしまいます。
その結果、同業他社と比べて相対的に自社の人材成長が後れを取り、ノウハウの蓄積や人材の即戦力化が進まなくなります。
その結果として、将来的には、組織全体の競争力低下につながるリスクを抱えることになってしまうでしょう。
公平な評価の阻害
暗黙知が共有されず表に出ないままでは、社員が持つスキルや日々の貢献度が正しく評価されにくくなります。
その結果、評価制度の信頼性が損なわれ、社員のモチベーション低下を招く要因となります。
さらに、努力や成果が適切に認められない環境は、優秀な人材の流出リスクを高め、組織の持続的成長を阻害する可能性があります。
貴重なノウハウの消失
熟練者が持つ高度な技術や知見が形式知化されないまま退職や異動が起こると、その価値あるナレッジは組織内で共有されず、事実上失われてしまいます。
失われたノウハウを再構築するには多大な時間とコストが必要となり、業務品質の低下や後継人材の育成の遅延を招くリスクが高まります。
リスクを解消!暗黙知を形式知化するメリット
暗黙知のままだと共有や継承が難しいため、形式知化することが望ましいです。
暗黙知を形式知化することには、属人化の改善や業務効率の向上、人材育成の効率化などさまざまなメリットがあります。
本項目ではそれぞれのメリットについて詳しく解説します。
属人化を改善する
暗黙知が多いと特定の担当者にしか遂行できない業務が増え、そのような属人化が進むことで組織全体の柔軟性が低下します。
また、担当者の不在時に業務が停滞したり、品質が不安定になるリスクも高まります。
そこで暗黙知を形式知化することで、誰もが同じ基準で業務を遂行でき、業務遅延や品質低下を防ぎながら、安定的かつ効率的な組織運営が可能になります。
業務効率が向上する
業務が暗黙知のままになっていると、他の従業員が対応するときに都度個別で指導や説明が必要となり、時間的なロスが発生し、業務の効率が低下してしまいます。
これを形式知化することにより、手順やノウハウが文書やマニュアルとして整理され、誰でも迅速に理解・実行できるようになります。
その結果、教育や引き継ぎの負担が軽減され、組織全体の業務効率が大きく向上します。
人材育成が円滑化する
暗黙知を形式知化することで、従来は経験や勘に頼っていたスキル習得を体系的に学べるようになります。
その結果、育成にかかる時間を短縮でき、また、マニュアルや研修資料として知識を共有することができるようになるため、研修コストの削減や教育の均質化も可能となります。
結果として、人材育成がより円滑かつ効率的に進められるようになるでしょう。
従業員のスキルアップにつながる
暗黙知を形式知化することで、全従業員がいつでも形式知化された必要な情報やノウハウを得ることのできる環境が整います。
これにより、業務のクオリティや生産性が向上するだけでなく、自分のペースで学びたい時にスキルを習得できるため、個々の能力向上にもつながります。
結果として、組織全体の底上げが進み、従業員一人ひとりの成長と組織力強化の両立が可能になります。
暗黙知を形式知へ変換する4つのナレッジマネジメント
暗黙知を形式知へ変換するためにはナレッジマネジメントが必要です。
ナレッジマネジメントは企業内の個人が持つ知識や技術などを組織全体で共有・活用する手法のことを指し、本項目ではその手法を4つ紹介します。
SECIモデル
SECIモデルは、経営学者の野中郁次郎氏が提唱したナレッジマネジメントのフレームワークです。
「共同化(Socialization)」「表出化(Externalization)」「連結化(Combination)」「内面化(Internalization)」の4つのプロセスを繰り返していくことで、個人の経験や知識を組織全体で共有・活用できる知識に変換し、継続的な学習と新たな知識や技術の創出を支援します。
場
「場」とは、経営学者の野中郁次郎氏らが提唱した概念で、組織内の情報や知識は人が集まり、交流する「場」で生まれるという考え方です。
単なる物理的な空間だけでなく、会議やプロジェクトチーム、オンラインコミュニケーションなど、意見交換や協働が活発に行われる環境も含まれます。
この「場」を意図的に設けることで、暗黙知の共有や形式知化が促進されます。
知識資産
「知識資産」とは、組織内の「場」で共有・蓄積された知識やノウハウを指し、企業にとっての重要な知識資産です。
これらの知識資産は、単に情報として存在するだけでなく、蓄積され、組織内で継続的に活用されることで、業務効率の向上や意思決定の質の向上、イノベーションの創出に寄与します。
そのため、知識資産の蓄積と活用は、現代の経営戦略において欠かせない重要な要素となっています。
ナレッジリーダーシップ
「ナレッジリーダーシップ」とは、組織におけるナレッジマネジメントを成功させるためにリーダーを置くことを指します。
リーダーがナレッジの共有や暗黙知の形式知化といったプロセスを主導し、組織内の知識循環を促進するとともに、その活用方法や発展の方向性を示す役割を担います。
ナレッジリーダーの関与が、ナレッジマネジメントの定着と組織全体の成長に直結するでしょう。
ナレッジマネジメントの効果を高めるには?
前項ではナレッジマネジメントの例について解説しましたが、ナレッジマネジメントを進める際はどのような点に注意すればよいのでしょうか。
本項目では、ナレッジマネジメントの効果を高めるための2つのポイントを解説します。
ナレッジ共有に適したツールを使用する
ナレッジを効果的に共有するためには、情報を蓄積するだけでなく、必要なときに誰もが容易に検索・活用できるツールを活用するのがおすすめです。
たとえば、社内Wikiやコンテンツ管理ストレージ、グループウェアなどがナレッジ共有ツールとしてあげられます。
ツールを活用することで、社員に負担をかけず、組織全体でナレッジを蓄積・共有させやすくなり、学習や業務効率の向上にもつながります。
ナレッジ共有を評価に反映する
ナレッジ共有は組織の成長に不可欠ですが、ナレッジ共有に抵抗感がある従業員もしばしば存在します。
そのため、そういった従業員がいることを想定し、ナレッジ共有の必要性や目的を丁寧に説明し、理解を促すことが重要です。
また、ナレッジ共有を評価制度に反映させることで、ナレッジ共有への従業員の協力を促し、ナレッジマネジメントの効果を高めることができるでしょう。
ナレッジマネジメントの成功事例
実際にナレッジマネジメントを導入し、成果をあげた例はさまざまあります。
本項目では、具体的に2つの企業の例を紹介します。
株式会社豊田自動織機
豊田自動織機は、同社全体の売上高の約7割を占めるトヨタL&Fカンパニーにおいて、サステナビリティや循環型経済への対応強化のための情報収集の効率化を目的に、日経ザ・ナレッジを導入しました。
導入の結果、AIによるプッシュ型配信で幅広い情報が速やかに得られるようになり、情報収集のスピードと深さが飛躍的に向上し、これによって、メンバー間の関心や価値観の理解が深まり、チームビルディングにつながっています。
また、新入メンバーの早期戦力化や、専門的知識の底上げにも寄与したほか、日々の記事チェックがルーティン化され、ワークスペースやバインダーを通じて情報を整理・共有する仕組みが定着しました。
結果として、チーム内の自然なコミュニケーションも促進され、知識の循環が進んでいます。
さらに、こうした情報活用が、経営トップへの説得ではなく共感を得る説明にもつながり、参謀役としての部門の役割を強化する原動力となっています。
花王
花王は1978年に「花王エコーシステム」という独自の消費者対応情報システムを導入し、顧客からの問い合わせや意見をデータベースに蓄積し、全社で共有する仕組みを構築しました。
このシステムは、消費者相談窓口が受け付けた声を翌日には社内の各部門が閲覧・活用できる状態にしており、マーケティングや商品企画、研究、生産、品質保証などの部門がその情報をもとに迅速に商品改善をおこなえるように促進しています。
また、相談内容の解析機能やトラブルの予兆を示唆する機能を備えており、品質改善や商品開発につながるナレッジ創出に貢献しています。
2024年の相談件数は約17万5千件にのぼり、電話による相談だけでなく、チャット(LINE)やWebサイトでのご意見箱への投稿など、世界各国から幅広い問い合わせや意見を集約し、そのナレッジを活かした製品開発につなげています。
※参考:花王生活者コミュニケーションセンター活動報告書2025
https://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/support/pdf/kao_consumer_2025J.pdf
社内の暗黙知を形式知化して企業価値を高めよう
社内に眠る暗黙知は、共有されなければ属人化やノウハウの消失などのリスクを招きます。
これを形式知化することで、知識を組織全体で活用することができるようになり、業務や人材育成の効率化促進につながるでしょう。
結果として、企業価値の向上も目指すことができるため、暗黙知の形式知化は企業戦略のうえで非常に重要です。
みなさんもぜひ本コラムの内容を参考にして、社内の暗黙知の形式知化に取り組んでみてはいかがでしょうか。