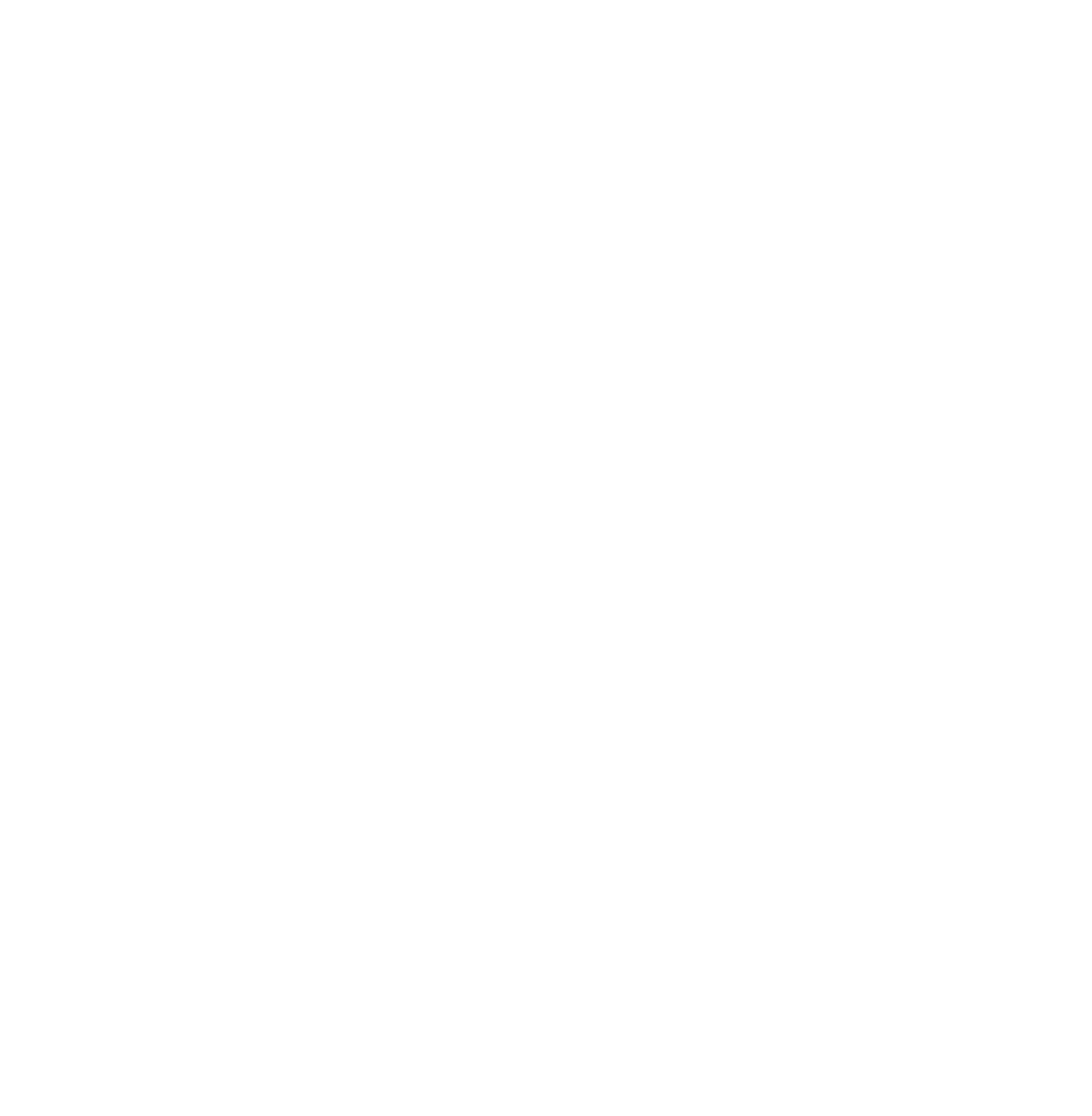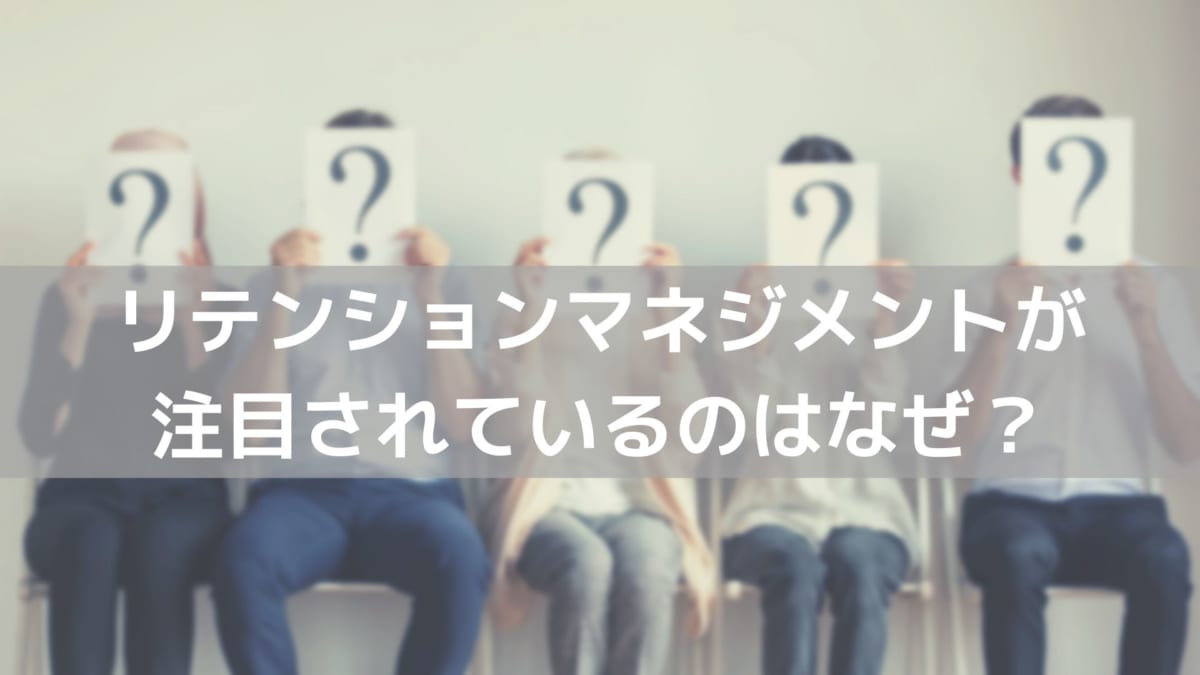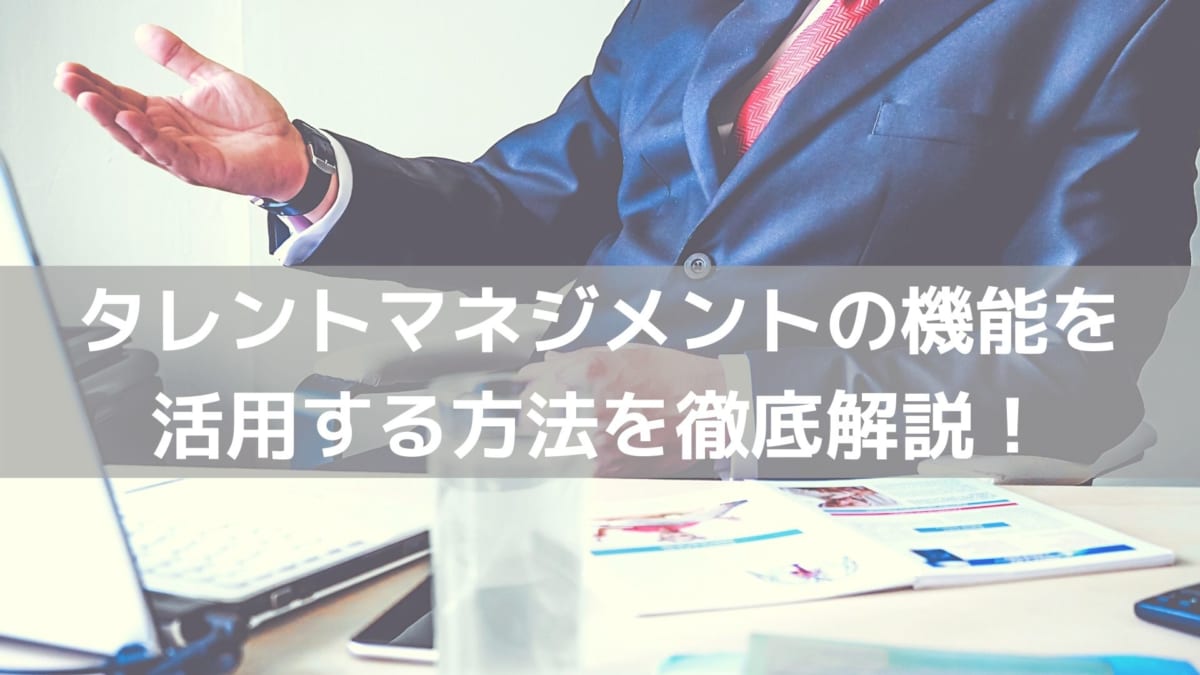ジョブ型人事制度とは?メリット・デメリットや導入時のポイントを解説

近年、多くの企業が「ジョブ型人事制度」の導入を進めています。
終身雇用や年功序列といった従来の人事慣行が見直される中で、「職務に基づく評価と処遇」を行うジョブ型の仕組みは、組織の生産性向上や専門性の高い人材確保において注目されています。
とはいえ、「具体的にどういう制度?」「導入には何が必要?」「実際に導入している企業はどうしているのか?」と疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ジョブ型人事制度の基本的な考え方から、メリット・デメリット、導入のステップ、そして代表的な企業の導入事例までを分かりやすく解説します。人事制度を見直したい方、人的資本経営を推進したい方は、ぜひご一読ください。
ジョブ型人事制度とは?
ジョブ型人事制度とは、職務内容(ジョブディスクリプション)を明確に定義し、その職務に必要なスキルや責任に応じて報酬や評価を決定する制度です。
社員個人ではなく「業務内容」に紐づけて雇用契約を結ぶことが特徴で、グローバル企業や専門職を中心に導入が進んでいます。
ジョブ型とは
ジョブ型とは、職務内容(ジョブ)を明確に定義し、職務に応じて採用・評価・報酬を決定する人事制度です。
個人の属人的な要素ではなく「仕事」に軸を置くことで、専門性や成果に基づいた公平な運用が可能となり、リモートワークや専門職の人材確保とも親和性が高い点が特徴です。
ジョブ型とメンバーシップ型における人事制度の比較
人事制度には大きく分けて「ジョブ型」と「メンバーシップ型」の2つがあります。
ジョブ型は職務内容を明確に定義し、それに応じて採用・評価・処遇を行うのに対し、メンバーシップ型は人に着目し、長期的な育成や柔軟な配置を前提としています。
欧米で一般的なジョブ型に対し、日本では長らく新卒一括採用であるメンバーシップ型が主流でしたが、働き方の多様化や専門人材の確保を背景に、近年ジョブ型への移行が進んでいます。
ジョブ型人事制度が重視されている理由
近年ジョブ型人事制度が注目されていますが、本項目では、その理由について解説します。
リモートワークの普及
近年、働き方の多様化によりリモートワークが急速に普及しました。
出社を前提としない働き方では、業務の過程よりも成果や役割が重視されるようになり、職務範囲が明確なジョブ型人事制度との親和性が高まっています。
従業員の仕事内容と責任が明確であれば、物理的な距離に関係なく評価・マネジメントが可能となり、柔軟な働き方を支える制度基盤として注目されています。
終身雇用制度の崩壊
かつて日本の雇用を支えていた終身雇用制度は、経済の不確実性や企業の競争環境の激化、少子高齢化により持続が難しくなっています。
年功序列型の処遇や長期的な雇用保障は、企業側にとって大きな負担となりつつあります。
その結果、職務に応じた処遇を行うジョブ型人事制度が注目されるようになりました。雇用の「安定」から「自律」へと意識が変化する中で、職務内容に基づく制度への移行が加速しています。
専門職の不足
AIやデジタル技術、グローバル経営などの分野で専門スキルを持つ人材の需要が高まる一方で、日本ではその供給が追いついておらず、専門職の人材不足が深刻化しています。
こうした中、職務内容とスキル要件を明確にし、報酬や評価を職務ベースで設計できるジョブ型人事制度は、即戦力人材の確保に有効です。
専門性を正当に評価できる制度があることは、優秀な人材にとって魅力となり、採用・定着の両面でメリットがあります。
国際競争力の強化
グローバル市場での競争が激化する中、国際水準に見合った人事制度の構築が日本企業にも求められています。
欧米ではジョブ型人事制度が一般的であり、優秀な人材を職務内容と報酬でマッチングさせるのが常識です。
日本企業が国際的な人材獲得競争に参入するためには、役割と成果に基づく評価制度が必要不可欠です。
ジョブ型人事制度は、採用・処遇の透明性と公平性を高め、グローバル基準での競争力強化に貢献します。
日本政府による指針発表
2024年、日本政府は企業に対し、職務内容や成果に応じた「職務給」を中心とする給与体系への移行を促す指針を発表しました。
人的資本経営の推進や国際競争力の強化を背景に、ジョブ型人事制度の導入が公的にも後押しされており、制度移行への機運が高まっています。
参照:ジョブ型人事指針|内閣官房 経済産業省 厚生労働省https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/jobgatajinji.pdf
ジョブ型人事制度のメリット
ジョブ型人事制度は、従来のメンバーシップ型制度では実現しづらかった「職務に応じた公正な評価」や「専門性の活用」を可能にし、組織と従業員の双方にとって多くのメリットがあります。
ここでは、企業がジョブ型を導入することで得られる代表的な効果を紹介します。
従業員のモチベーションアップにつながる
ジョブ型人事制度では、職務内容や評価基準が明確に定義されているため、成果やスキルが公平に評価されやすくなります。
これにより、高スキルな人材にとっては自身の市場価値を発揮しやすい環境となり、モチベーションやエンゲージメントの向上につながります。
企業の人事戦略を効率化できる
ジョブ型人事制度では、職務に必要なスキルや期待される成果が明確になるため、的確な人材配置や採用が可能になります。
無駄な異動やミスマッチを減らすことができ、組織全体の生産性向上や人事戦略の効率化に大きく貢献します。
ジョブ型人事制度のデメリット
ジョブ型人事制度は多くのメリットを持つ一方で、すべての企業や従業員にとって万能な仕組みではありません。
職務の固定化によるキャリアの不安や、柔軟な人材運用の難しさ、制度構築にかかるコストや専門性など、導入に際しては慎重な検討が必要です。
ここでは、ジョブ型導入に伴う代表的な課題を紹介します。
キャリアに対する不安が生まれやすい
ジョブ型人事制度では、職務ごとにスキルや成果が明確に求められるため、専門性が乏しい人にとっては不利になりやすい側面があります。
キャリアの幅が限定されるだけでなく、成果を出せなかった場合に評価や立場が厳しくなるという不安が生じやすくなります。
柔軟な人材運用が難しくなる
ジョブ型人事制度では、職務が明確かつ固定されるため、異動や配置転換がしづらくなります。
その結果、組織横断での人材活用や臨機応変な役割変更が難しくなり、社内の柔軟な動きや部署間の連携が制限されやすくなる点が課題となります。
制度設計・運用にコストと専門性を要する
ジョブ型人事制度の導入には、職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成に多くの時間と労力がかかります。
また、職務ごとの評価制度や給与体系の整備も必要となるため、制度設計が複雑化しやすく、一定の専門知識と運用体制が求められます。
ジョブ型人事制度を導入するには?
ジョブ型人事制度の導入には、明確な職務定義や評価制度の整備など、段階的かつ計画的な準備が欠かせません。
単なる制度の置き換えではなく、組織全体の人材戦略や運用体制とも連動させる必要があります。ここでは、ジョブ型を導入するための基本的なステップを順を追って解説します。
適用範囲を決定する
ジョブ型人事制度を導入する際は、まず適用範囲を明確にすることが重要です。
全社一括で導入するのか、専門職や管理職など一部職種から段階的に進めるのかによって、準備や運用体制も大きく異なります。
自社の人材構成や目的に応じた導入スコープを検討しましょう。
職務記述書を作成する
職務記述書では、職務の目的や業務内容、必要なスキル・資格、責任範囲、成果指標(KPI)などを明記します。
これにより、職務と人材要件のミスマッチを防ぎ、評価や報酬の基準も明確化されます。制度全体の公正性を支える重要なステップです。
職務評価をおこなう
作成した職務記述書をもとに、各職務の価値や重要度を評価するのが職務評価です。
業務の難易度や影響度、責任の重さなどを基準に比較・分類することで、等級や報酬体系の基礎となる職務の「重みづけ」が可能になります。制度の公平性を支える重要な工程です。
職務価値を等級に分ける
職務の評価が完了したら等級に分けていきましょう。
等級においてポイントとなるのが幅の持たせ方です。等級の幅にはナローバンドとブロードバンドがあります。
ナローバンドは等級の幅を狭く、より細かく設定する手法。レベル別に職責を分けやすいものの、降格になる人事異動はしづらいと言えます。
一方、ブロードバンドは等級の幅を広くし、等級をおおまかに分ける手法です。降格になる異動はしやすいですが、等級の明確な差がうまれにくいデメリットもあります。
どちらを選ぶかは自社の従業員数や職務内容によって決めていきましょう。
職務に応じた賃金を決定する
職務評価の結果をもとに、各職務の価値に応じた賃金レンジを設定します。
仕事内容や責任の重さ、必要スキルなどに応じて処遇を決定することで、納得感と公平性の高い報酬体系が実現できます。評価・報酬の一貫性が、制度定着のカギとなります。
社内への制度浸透を図る
職務評価によって得られた職務の価値をもとに、等級や報酬レンジを設定し、賃金を決定します。
職務の重みや責任に応じた報酬体系を構築することで、処遇の透明性と納得感が高まり、優秀な人材の確保や定着にもつながります。人事制度の信頼性を左右する重要な工程です。
試験導入を実施する
ジョブ型人事制度をいきなり全社導入するのではなく、まずは一部の部署や職種で試験的に導入することで、実運用における課題や反応を確認できます。
制度の効果や運用上の問題点を把握した上で改善を重ねることで、本格導入時のスムーズな定着が期待できます。
定期的に制度を見直す
ジョブ型人事制度は一度導入すれば終わりではなく、環境や組織の変化に応じて定期的な見直しが欠かせません。
職務内容の変化や人材戦略の見直しに応じて、職務記述書や評価基準、報酬体系を柔軟に更新することで、制度の形骸化を防ぎ、継続的な制度運用が可能になります。
ジョブ型人事制度の導入事例
ジョブ型人事制度は、すでに多くの企業で導入が進められており、その目的や運用方法、得られた効果は企業ごとにさまざまです。
ここでは、実際にジョブ型を取り入れた代表的な企業の事例を紹介し、制度導入によってどのような変化が生まれたのかを見ていきます。
KDDI株式会社
KDDI株式会社では、2020年より管理職層を対象にジョブ型人事制度を本格導入しました。
職務内容や成果に基づいた評価制度へと移行し、社員のキャリア自律を促進。ジョブディスクリプションを活用することで、専門性の高い人材の育成や適正な配置を可能にしています。
三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社では、全社員を対象にジョブ型人事制度を導入しています。
職務定義に基づく評価と処遇を実現するため、ジョブディスクリプションを全職務に整備しました。
役割とスキルに応じたキャリア形成を支援し、専門性と成果に基づく公正な制度運用を進めています。
株式会社メルカリ
株式会社メルカリでは、ジョブディスクリプションを全社的に整備し、ジョブ型人事制度を推進しています。
フルリモート体制でも職務と成果に基づく評価を実現し、職務内容に応じた柔軟な報酬設計や配置が可能に。専門性と自律性を重視した人事運営が特徴です。
ジョブ型人事制度には飛躍的な企業成長の可能性がある
ジョブ型人事制度は、専門性の高い人材の活用や公正な評価を通じて、組織の生産性向上と持続的な成長を支える仕組みです。
制度設計やスキルの可視化には、実践的な支援ツールの活用が効果的です。導入・運用にお悩みの方は、ぜひ「スキルナビ」をご覧ください。