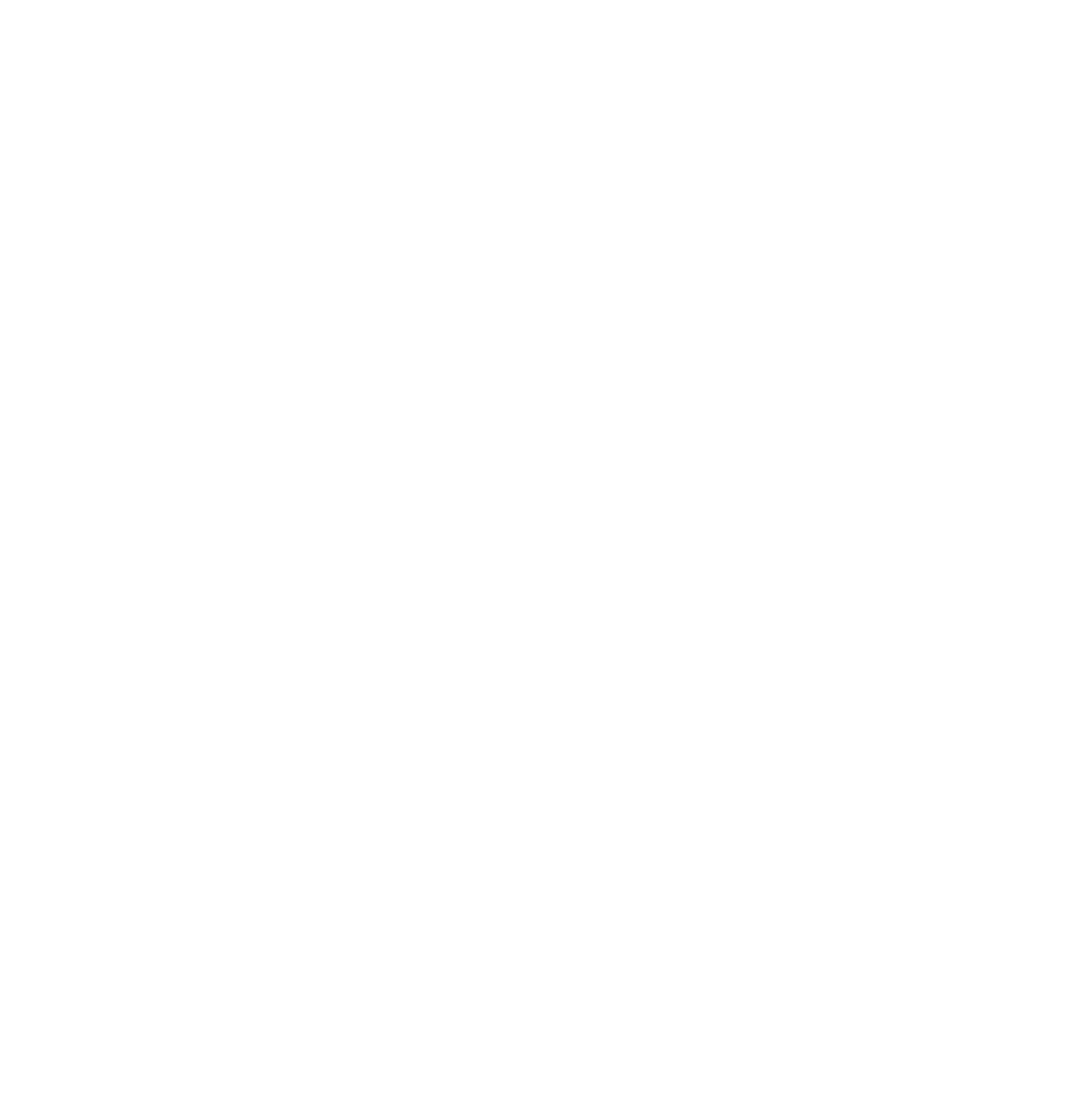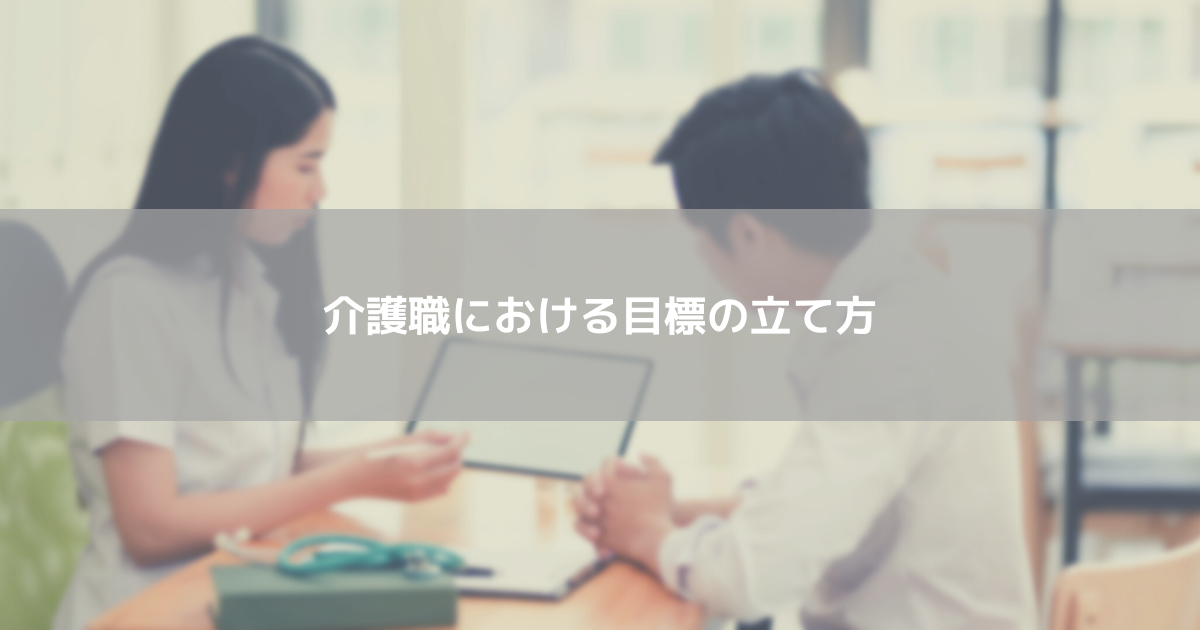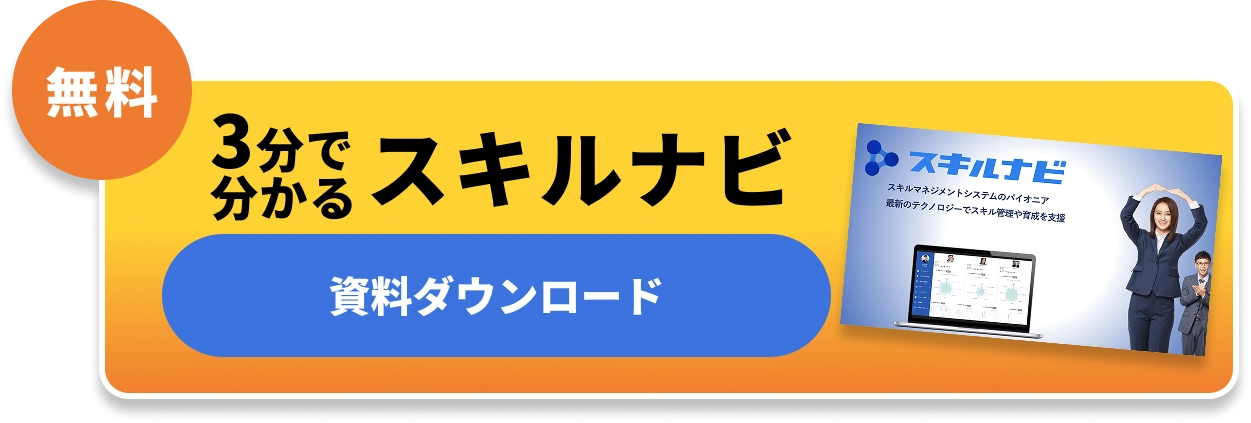人手不足を対策するには?原因や影響、解消するための方法を解説
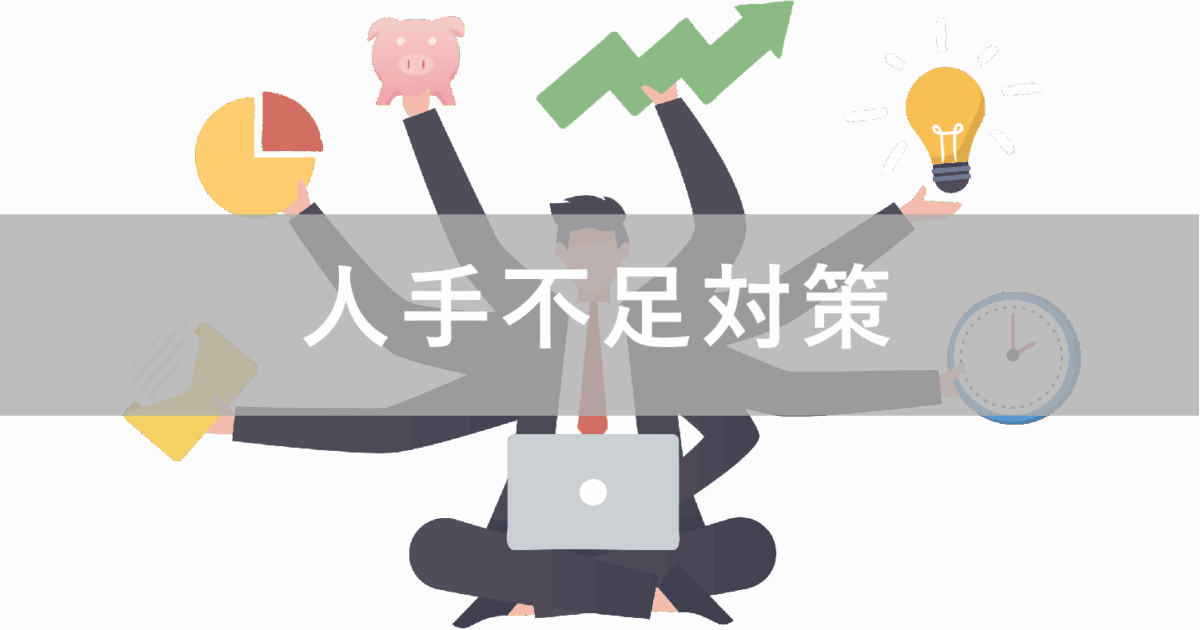
近年、日本の多くの企業で深刻な人手不足が問題となっており、業務の負担増や生産力低下、離職率の上昇など、さまざまな影響が生じています。
その背景には少子高齢化や働き方の変化、職場環境の課題など複数の要因が絡んでいます。本コラムでは、人手不足の原因と企業に与える影響を整理するとともに、労働環境の改善や採用戦略の見直し、DX推進やスキル習得支援など、具体的な解消策について解説します。
人手不足が深刻化する日本の背景と要因
近年日本では人手不足が深刻化していますが、それはなぜなのでしょうか。
本項目ではその背景と要因について解説します。
少子高齢化
厚生労働省が発表した高齢化の推移と将来推計によると、2023年10月時点で総人口は1億2,435万人、2060年には1億人を切り、9,615万人にまで落ち込むと予測されています。
更に日本の少子高齢化は世界的にみても急速に進行が続き、人口は減少していく一方で、65歳以上の人口割合は増加を続け、2070年には人口の約40%を占めると予想されています。
※参考:内閣府「令和6年版高齢社会白書」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf
スキルやニーズのミスマッチ
企業と求職者の間でスキルやニーズが一致しないミスマッチが発生すると、人手不足に陥ってしまう場合がしばしばあります。
例えば、土木・介護・サービス業などに関しては、有効求人倍率が2〜6倍程度と人材が不足している一方で、一般事務や会計事務などの職種では有効求人倍率が1を切るなど、人材の余剰が発生している状況にあります。
※参考:「一般職業紹介状況(令和7年5月分)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/001507875.pdf
若者の仕事観の変化
若者の仕事観の変化も人手不足の大きな要因のひとつとなっています。
以前は安定した収入などが重要視されていましたが、現在の20代を中心とした世代では、ワークライフバランスや自身のスキルや知識を高められる環境を重視する傾向が強まっています。
そのため、長時間労働が常態化していたり、年功序列など古い企業文化を持つ企業は、若手人材の確保や定着が難しくなり、人手不足を深刻化させる一因となっています。
職場環境の課題
「若者の仕事観の変化」で解説したように、若者が企業に求めるものが変化しているため、企業が求める人材を確保するには職場環境などの変化が必要とされています。
また、労働環境が過酷であったり、給与や福利厚生が不十分である場合、働きたいと考える人材が少なくなるだけでなく、既存社員のモチベーション低下や離職につながる恐れがあり、人手不足をさらに深刻化させてしまいます。
DX導入の停滞
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、社会における活動や業務に対して新しい技術を取り入れ、デジタル化を推進しようという取り組みを指します。
近年、情報通信業で特に人手不足が発生していますが、DX推進をおこなう企業が増える一方で、IT・デジタル人材の供給が追いつかず、人材獲得競争が激化していることがその背景にあります。
※DXに関しては下記記事もご参照ください。
人手不足の現状と発生しやすい業界
厚生労働省ではD.I.(Diffusion Index(ディフュージョン・インデックス)という、変化の方向性を表す指標)を公表しています。
正社員等労働者の場合は令和7年5月1日時点、調査産業計で+44ポイントの不足超過となっており、特に学術研究、専門・技術サービス業、建設業、情報通信業で人手不足が高くなっています。
| 産業 | 令和7年5月調査(単位:%,ポイント) | ||
| 不足 | 過剰 | D.I. | |
| 調査産業計 | 47 | 3 | 44 |
| 建設業 | 59 | 1 | 58 |
| 製造業 | 45 | 4 | 41 |
| 情報通信業 | 57 | – | 57 |
| 運輸業、郵便業 | 57 | 2 | 55 |
| 卸売業、小売業 | 31 | 3 | 28 |
| 金融業、保険業 | 31 | 2 | 29 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 46 | 2 | 44 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 61 | 2 | 59 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 45 | 2 | 43 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 38 | 3 | 35 |
| 医療、福祉 | 53 | 3 | 50 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 52 | 1 | 51 |
また、パートタイム労働者の場合、調査産業計で+28ポイントの不足超過となっており、特に宿泊業,飲食サービス業、サービス業(他に分類されないもの)、生活
関連サービス業、娯楽業で人手不足が高くなっています。
人手不足の企業に見られる特徴
人手不足におちいりやすい企業にはさまざまな特徴があります。
本項目では代表的な3つの特徴を解説します。
業務量に対して報酬や待遇が適正でない
業務量、労働負荷に対して給与や待遇といった見返りが少なすぎる企業は、新規採用を行ったとしても離職率が高くなってしまいます。
長時間労働や休日出勤の他にも、心身に負担がかかるような労働環境であるにもかかわらず、それに見合った給与や待遇が与えられない場合、不満が蓄積しやすく、結果的に離職につながりやすい傾向があります。
効率化に対する意識が低い
近年、デジタル技術を活用して業務の効率化をおこなう企業が多くなってきています。
一方で、依然としてアナログ志向が抜けない状況を続ける企業は、従業員から時代遅れと捉えられやすくなります。
その結果、将来への不安を抱かせるだけでなく、モチベーションやエンゲージメントの低下につながり、定着率の悪化などを招いてしまう可能性が高まります。
評価基準が公平でない
人事評価の基準に公平性がない企業では、従業員の努力や成果が正当に認められにくく、不満が蓄積しやすくなります。
その結果、優秀な人材が離職してしまう、新たに採用した人材も早期退職してしまうなど、人手不足につながる状況が繰り返されてしまいます。
このような状況を防ぐためにも、公平で透明性のある評価制度を導入、運用することが重要といえるでしょう。
人手不足が企業にもたらす影響
人手不足は企業にさまざまな影響をもたらすため注意が必要です。
本項目では主に4つの影響を解説します。
労働環境や働きがいの悪化
人手不足になると、一人当たりの業務の負担が増加し、長時間労働や有給休暇取得の困難など、労働環境の悪化を招きやすくなります。
その結果、従業員のモチベーションが低下し、ストレスが溜まることによって早期退職が発生するリスクが高まります。
こうした状況が続くと、さらに人手不足が進行するという悪循環に陥る恐れがあります。
生産力や競争力の低下
人手不足が発生すると、商品やサービスの生産・製造に関わる部門へ適切な人員が配置できなくなってしまうため、生産力の低下を招きます。
また、企業の中長期的な成長のために必要なコア業務にまで人員が行き渡らなくなり、マーケティングや新規事業開発などの取り組みが停滞します。
その結果、競合他社に後れを取り、企業全体の競争力が低下する恐れがあります。
事業縮小や倒産の危機
人手不足が深刻化すると、生産力が低下し、受注量を抑えなくてはならなくなるため。売上や利益の低下、事業の縮小を余儀なくされるケースも少なくありません。
最悪の場合、経営の継続が困難となり倒産に至る恐れもあります。
実際に、帝国データバンクが公表したデータによると、2025年上半期の「人手不足倒産」は202件発生し、上半期としては2年連続で過去最多を更新しています。
※参考:株式会社帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2025年上半期)」
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250704-laborshortage-br25h
組織の成長率の低下
「事業縮小や倒産の危機」で記載した倒産のような深刻な事態に至らなくても、人手不足は組織の成長に長期的な影響を及ぼします。
人員に余裕がない状況では、人材育成や組織の新陳代謝において長期的な影響が発生することが懸念され、研修や自己学習の機会が減少し、教育が不十分となってしまいます。
その結果、社員の戦力化が遅れたり、成長実感の欠如から離職が進んだりすることで、組織全体の成長率が低下してしまう恐れがあります。
人手不足を解消するために必要な対策法
人手不足を解消するためにはなにをすればいいのでしょうか。
本項目では具体的な対策方法を5つ解説します。
労働条件や職場環境の見直し
まず自社の労働条件や職場環境を見直すことが重要です。
有休などの休暇を取得しやすい制度設計や、給与面の改善、リモートワークや短時間勤務制度の導入など、柔軟で働きやすい環境を整えることで定着率の改善につながります。
特に女性社員にとっては、家庭と仕事を両立できるような環境を整えることが働きやすさにつながり、人材確保の大きな鍵となります。
採用方法や雇用対象の見直し
採用方法や雇用対象の見直しも欠かせません。
採用する際に求める人材像が明確になっていない場合、ミスマッチが発生し早期離職につながる恐れがあるため注意が必要です。
また、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用など、企業側から積極的に求職者へアプローチする手法を活用することや、雇用対象を幅広くし、シニア層や外国人の雇用を検討することにより、より多くの採用が期待できるでしょう。
制度や職場風土の見直し
福利厚生や企業制度の見直しも重要であり、福利厚生を充実させることで従業員の満足度や労働意欲が高まり、離職を予防することが期待できます。
また、社内風土の改善も重要です。長時間労働が評価されるなどのよくない面は見直しをおこない、コミュニケーション不足の課題がある場合は、社員同士が気軽に意見交換や相談ができる環境を整えることで、働きやすく活気ある職場づくりが実現します。
DX推進による業務効率化
人手不足を補う手段として、DXの推進による業務効率化も有効です。
ITツールやシステムを導入することで、定型業務を自動化し、限られた人員をコア業務に回すことができます。
さらに、業務のデジタル化によって業務制度の向上が期待できるため、生産性の向上だけでなく、顧客満足度や業務品質の向上にもつながります。
学び直しや新たなスキル習得の促進
従業員のスキル向上で効率化をはかることも重要です。
新しい学びを得る過程では一時的に業務効率は落ちることもありますが、長期的には人手不足の解消に繋がっていきます。
また、学びの方法には下記2つの種類があります。
・リカレント
就業と学習を繰り返しながら、長期的に学び続ける仕組みや考え方
・リスキング
従業員が新たな業務や役割に対応できるように、必要なスキルや知識を新たに習得すること
これらの学びを実践することで、IT技術やAIスキルなどを身に着けてもらうことが可能になるでしょう。
人手不足の課題を解決した企業例
※例があれば記載する
効果的な対策をおこない人手不足を解消しよう
人手不足の対策として、現在の企業の労働環境や条件を見直すことが重要です。
そのうえで、幅広い世代や多様な条件の人材を採用し、一人ひとりに合わせた働き方や教育方法を導入することで、効率的な人材活用が可能になります。
これにより人手不足の解消とともに職場環境の改善も期待することができるでしょう。
当社が提供するスキルナビは、従業員データや面談履歴を一元管理できるほか、教育方法の検討にも役立つツールです。ツールを利用することで、より効果的な現状分析・対策立案が可能となります。
ご興味をお持ちの方は、下記よりお問い合わせください。