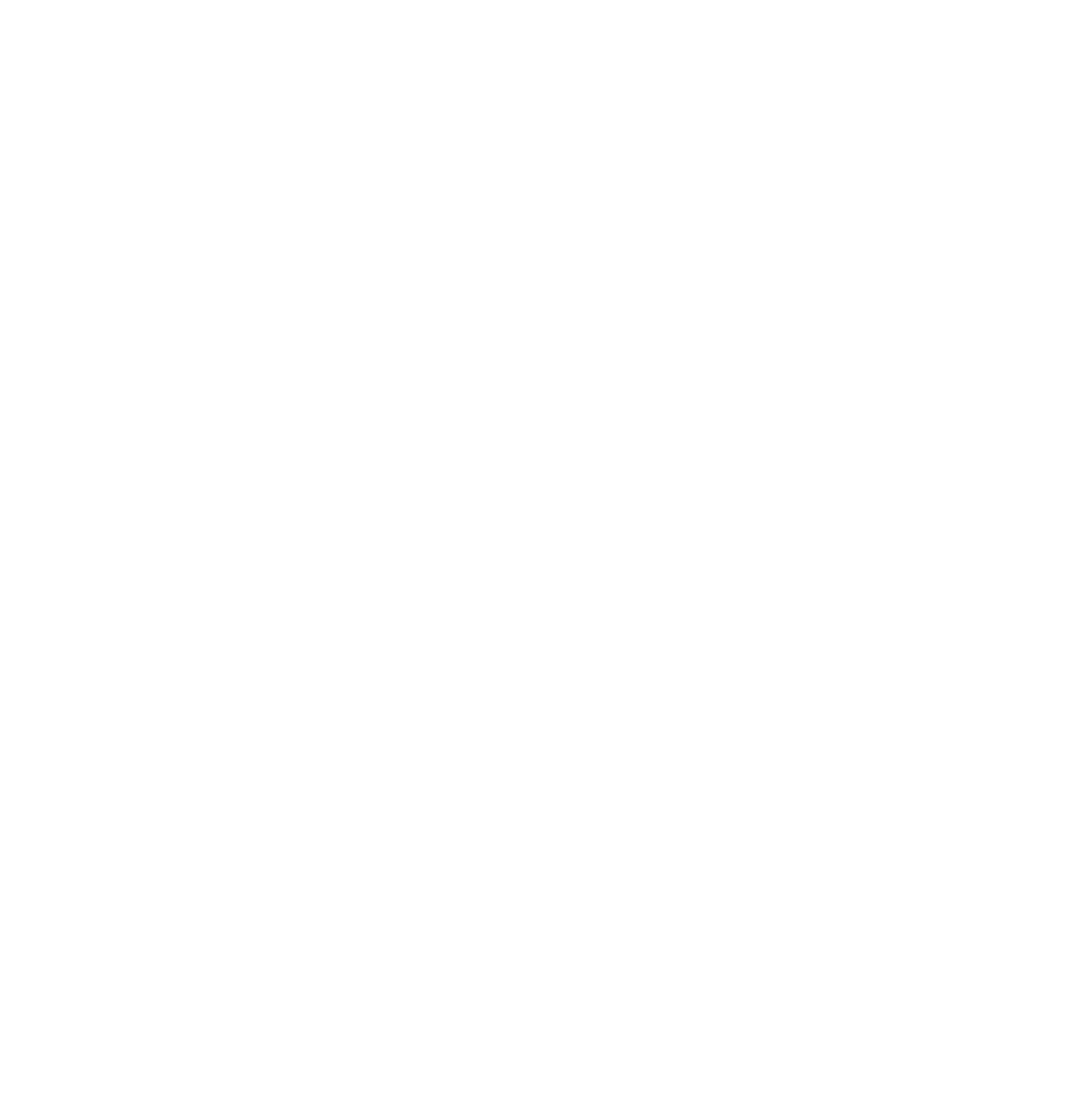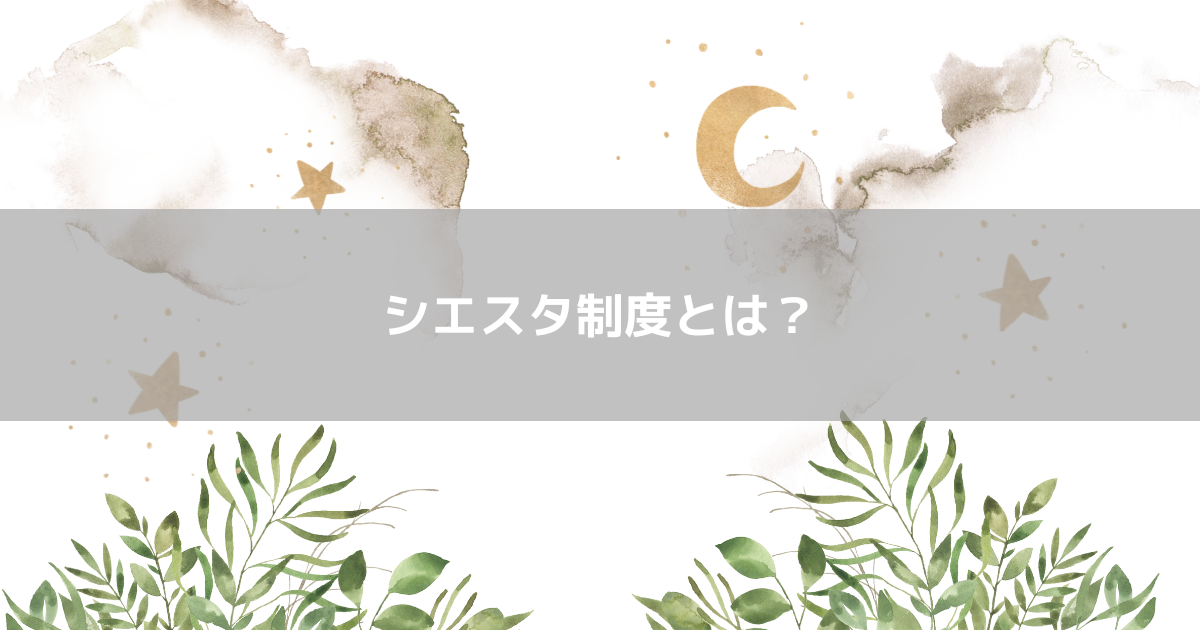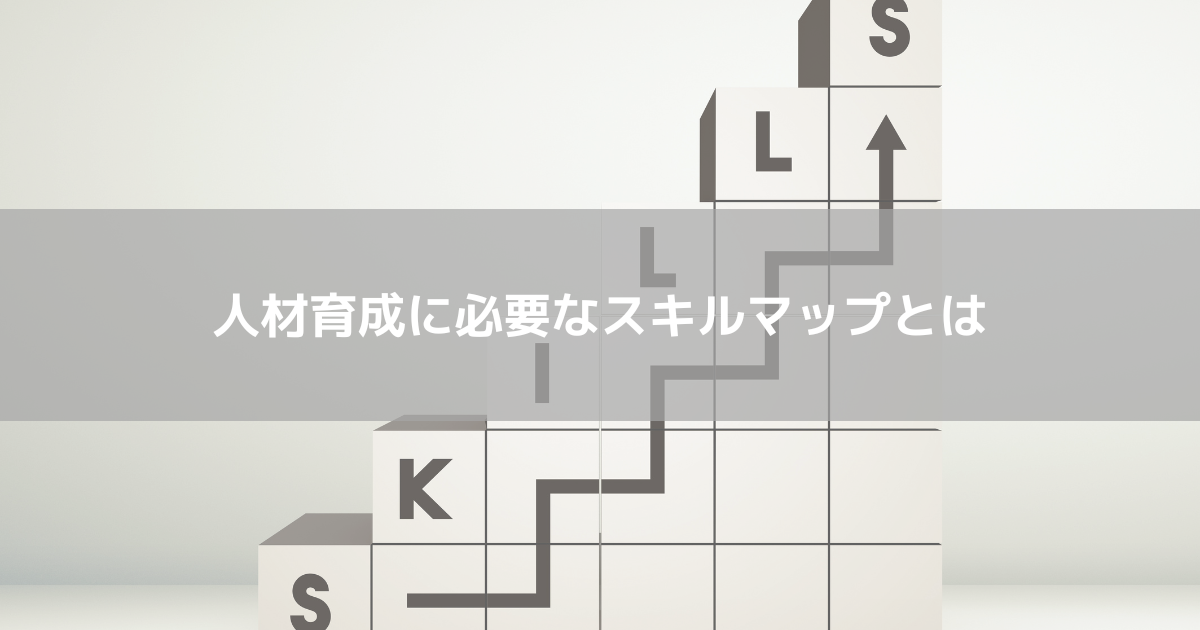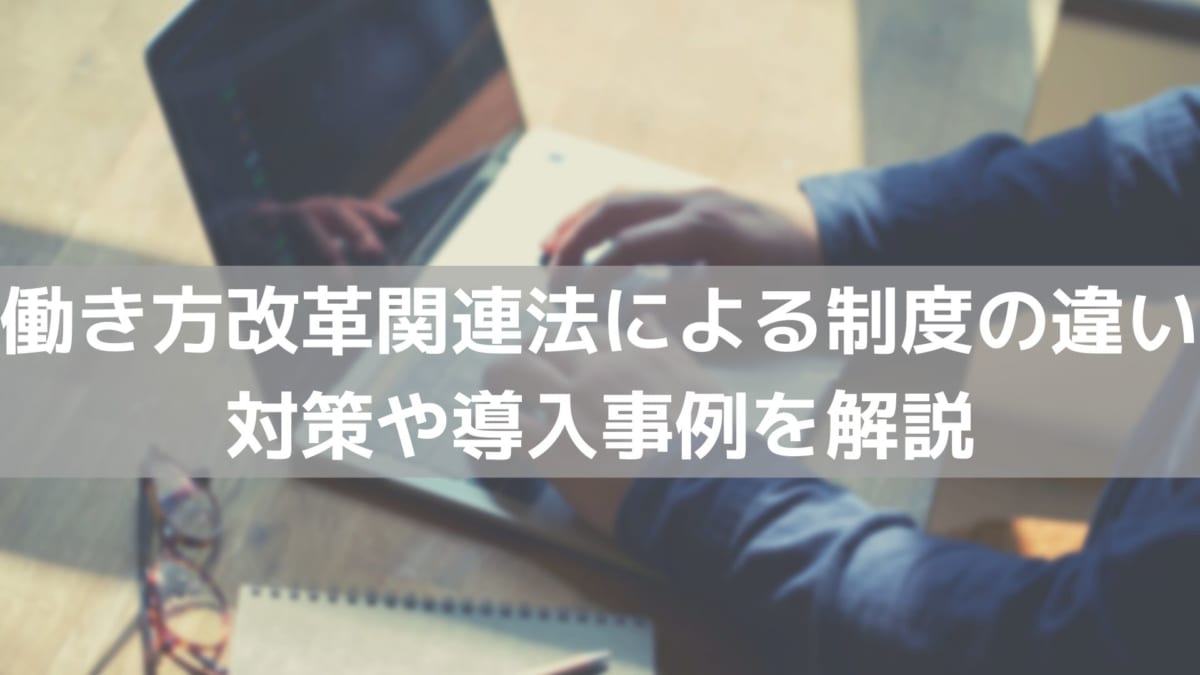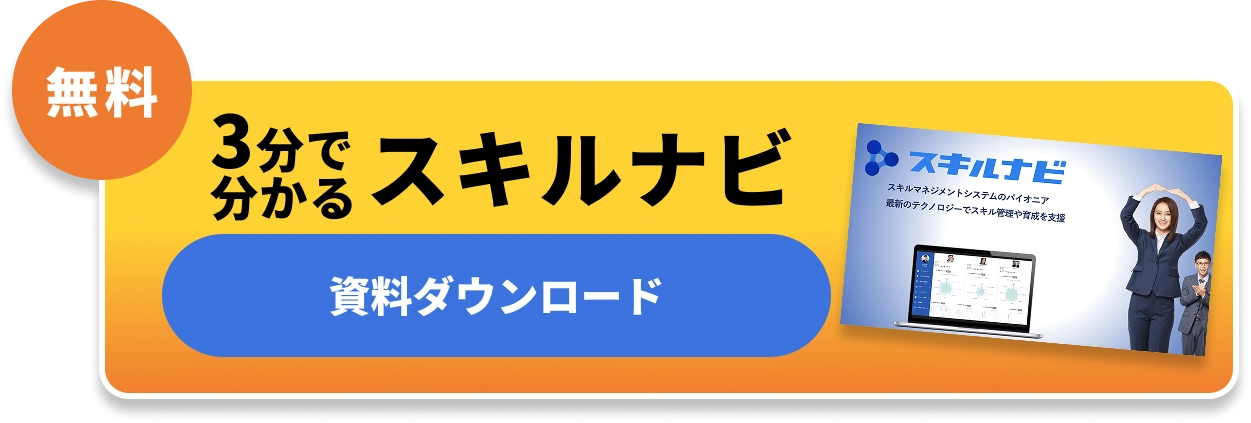人事異動内示とは?伝えるタイミングや伝え方、伝える際のポイントを紹介!

人事異動内示は、従業員に異動の方針を正式発表前に伝える重要なプロセスです。
円滑な引き継ぎや心理的な準備を促すためにも、適切なタイミングと伝え方が求められます。
本記事では、内示の基本的な内容・目的から、内示を伝える際のポイントまで詳しく解説します。
人事異動の内示とは
そもそも人事異動の内示とはどのようなものなのでしょうか。
本項目では、内示の意味と、内示を行う目的や重要性・効果について解説します。
内示について
内示とは、一般に公表する前の段階で、内々に伝えることを意味する言葉です。
人事異動における内示は、準備などの関係上ある程度の期間の余裕を持って、上司や人事担当者から本人に伝えられることが一般的です。
内示の目的となる理由と重要性
人事異動を行う最大の目的は人事異動を円滑に進めることです。
正式な発令前に本人へ異動の方針を伝えることで、心の準備や引き継ぎの計画を促すことができるため、円滑な異動と業務の継続性を確保するためにも、内示は組織運営上欠かせない役割を担っています。
内示がもたらす効果
人事異動の内示は、従業員に心構えや業務引き継ぎの準備期間を与えると同時に、異動内容が正式発表前であることを伝え、口外禁止のルールを徹底する効果もあります。
また、内示を行うことで従業員との意思確認や調整を行う効果もあります。
内示は強制されるものではない
人事異動の内示を行うことにはさまざまなメリットがありますが、内示を義務付ける法律は存在しません。
そのため、企業による内示は義務ではなく、状況に応じて内示を行うかどうかを判断することが重要です。
内示と誤解しやすい言葉
本項目では、内示と誤解しやすい言葉を紹介します。
辞令と発令の違い
内示と誤解しやすい言葉に「辞令」と「発令」があります。
辞令とは「人事異動を知らせる公文書や内容」を指し、発令は「辞令を出す行為自体のことをいいます。
内示は従業員本人に行う一方で、辞令は全従業員へ通知を行うなどの違いがあります。
内示と内定の違い
内示も内定も公表前の段階で、本人に対して伝えること自体に違いはありません。
しかし、内定が昇進や採用が決まったことを伝えるために行われるのに対して、内示は通常準備のために行われる点で違いがあります。
内々示とは
内々示(ないないじ)とは、内示の前に非公式に伝えることです。
内示から辞令までの期間が短い場合や、海外転勤で引っ越し準備に時間がかかる場合に早めに伝えるという意味合いを込めて、内々示を行う場合があります。
人事異動内示の一連の流れとつながり
人事異動の内示は正式発表でない内容を伝えるため、辞令や発令よりも前に行われます。
一般的な人事異動内示の一連の流れとしては、おおまかに以下のようになります。
人事異動の検討
▼
人事異動の決定
▼
(内々示)
▼
内示
▼
辞令の発令
▼
異動
通知前に知っておきたい人事内示の主な分類
人事内示には昇進・昇格や解雇、異動などさまざまな種類があります。
本項目では、代表的な人事内示の分類を6つに分けて紹介します。
キャリアアップ(昇進)
昇進は課長が部長、部長が本部長や役員など、現在よりも相対的に上のポジションに移ることをいいます。
必ずしも昇格が必須ではなく、従業員のモチベーション向上や人材育成、組織力向上を目的にリーダーやマネジメントを抜擢するために実施されます。
ランクアップ(昇格)
昇格とは、昇進とは異なり、異動対象者の絶対的なランクが上がることをいいます。
等級や職能資格制度をおいている会社において、従業員の職務遂行能力や業績に応じて等級やグレードが上がり、同時に給与が上がることが一般的です。
職位の降格・役職のダウン
職位の降格や降職も人事内示のひとつです。
降職とは役職を解くこと、降格は人事制度上の等級を引き下げることを意味し、必ずしもネガティブな理由によって発生するものではありません。
職務からの解任・雇用終了
解任や雇用終了といった解雇・免職は、従業員にとってはきわめて大きな影響を及ぼす人事異動です。
基本的には対象者本人の望まない処遇であり、解雇・免職の対象者が不満のあまりモラルに欠ける言動を行ってしまうことも想定されるため、発令後に周囲の従業員に対するケアを行うことも重要です。
転職先へ異動
転勤のほうがポピュラーな言い回しですが、「転勤」の場合、勤務地で異動前と同じ業務をする場合があり、「転任」は勤務地とともに業務内容も変更になることを示すため区別して用いられることがあります。
転居を伴う場合もあるため、事前準備を入念に行うことが重要です。
職場の異動・役職変更
部署異動や、役職変更といった配置転換は、人事異動の中で最も想像しやすい類型です。
ジョブローテーションによる異動もあれば、社内での抜擢などを含めた戦略的な異動・役職変更も近年は多く行われています。
内示を伝える時期やタイミング
内示を伝える時期やタイミングは、その内容や企業によって異なります。
本項目では一般的なケースについて紹介します。
転居が必要な場合
異動や転勤・出向などの場合は、就業先の変更に伴う引越しが必要となります。
従業員の家族にも関係してくるため、異動する1〜2ヵ月前など、余裕をもったタイミングで内示を知らせ、準備期間を設けることができるようにするのが一般的です。
転居を必要としない場合
昇進や昇格・降職や降格等で転居を伴わない場合は、1ヵ月前〜数週間前に内示を知らせることが多いとされています。
業務の引き継ぎ準備もあるため、遅くても1週間前には内示するようにしましょう。
企業によって異なる場合もある
一部の業界や企業文化によっては人事異動の時期が異なるケースもあるため、内示のタイミングも異なります。
大手企業や公務員ですと4月が年度始まりとなるケースが多いため、3月や9月に行われるケースが多く、ベンチャー企業などでは組織の変化が早いため随時内示が行われるなど、さまざまなパターンがあります。
人事異動の通知方法
人事異動の通知方法は複数あります。
本項目では人事異動の通知方法と注意するべき点について解説します。
個別にお知らせをする
人事異動が決まったら、1対1で直接伝える方法があります。
直接口頭で話すことで、相手との認識のずれを生じにくく、理解を得やすいというメリットがあります。
ただし、1対1での話し合いを設けることで、他の従業員にばれてしまう可能性があるため、細心の注意が必要です。
電子メールや文書で通知する
電子メールや文書で内示を伝える方法もあります。
メールや文書で伝えると簡潔かつ迅速な通知が可能というメリットがありますが、無機質で冷淡な印象を与えるというデメリットもあります。
重要な内容であるため、通知後のフォローなどもふくめて検討することが重要です。
異動の意図を明確に伝える
内示を伝える際に、人事異動の事実のみを伝えては批判やトラブルを招くおそれがあるため、目的をきちんと提示することが重要です。
目的をきちんと伝えることで、対象者の納得を得ることができ、トラブルを防ぐことができるでしょう。
内示の実施に向けて準備すること
人事異動の内示を行ううえでは、事前準備が重要となります。
本項目では準備が必要な2つの事項について紹介します。
情報の漏洩を防ぐため、厳重な対策を実施する
人事異動の内示を行ううえで、情報漏えいは回避しなければなりません。
万が一広まってしまった場合、社内の混乱や従業員のモチベーション低下を招いてしまうおそれがあります。
情報漏えいを防ぐために、事前にいつ・どこで・どのように内示を行うかを十分に検討する必要があるでしょう。
人事異動の判断が正しいか最終確認を行う
内示を行う前に、人事異動が適切かどうか最終確認を行うことも重要です。
たとえば人事担当者の主観が入っていたり、本人の希望にあまりにも考慮していない異動であったりすると、「この会社では自分のやりたいことができない」と判断されてしまい、結果的に退職を促してしまうおそれもあります。
人事異動の内示を伝える際の重要な注意点
本項目では、人事異動の内示を伝える際の重要な注意点について解説します。
企業の戦略的ビジョンを共有する
人事異動の内示を伝える際には、従業員本人が企業の経営方針や経営戦略を深く理解し、それに基づいて異動の意図や目的を具体的に理解していることが重要です。
そのため、内示を伝える際には従業員へ企業の戦略的ビジョンを明確に共有するようにしましょう。
人事異動の理由を説明する
人事異動の内示を伝える際に最も重要なのは、異動の目的を社内で明確に共有することです。
異動の目的を社内で明確に共有することで、従業員は異動の必要性や意図を理解することができ、組織全体での一体感が向上します。
異動先の詳細を具体的に説明する
上司や人事労務の担当者として従業員に明確な説明ができるように、内示の詳細を把握することも重要です。
内示により、従業員が不安や不満を抱えるケースもあるため、そのような不安や不満を解消できるよう、内示の詳細を具体的に伝えられるように準備することが必要でしょう。
情報の漏洩を防ぐために厳重な管理を行う
内示は機密情報と同様に取り扱う企業が多いため、情報が漏洩しないように対策を行いましょう。
特に、重要なポジションの人事異動があった場合、社内だけでなく取引先や株主に影響を与える可能性もあるため、従業員に対して内示を口外しないように厳重に注意を行うことが重要です。
内示が断られた際、理由を尋ねる
もし従業員から内示を断りたい・検討したいと言われた場合は、拒否できない旨を伝える前に、理由を確認しましょう。
内示を断る理由によっては、労働契約法や育児・介護休業法に抵触するものもあるうえ、一方的に内示を行うことは企業への不信感や、ひいては退職につながるリスクもあるため、まずは理由を確認したうえで判断することが重要です。
人事異動を円滑に進めるための内示のコツ
人事異動を円滑に進めるためには、内示の方法にも気をつける必要があります。
本項目では内示のコツやポイントについて紹介します。
プロセスを一貫させる
内示は秘密性の高い行為である一方で、会社が行うものであるため、一定の責任が生じます。
内示でもたらされる情報は口外禁止であるからといって、手順まで不透明では統制が及ばなくなってしまいます。
したがって、会社のルールとして内示の手順を設定し、一貫したプロセスで内示を行うことができるように準備する必要があるでしょう。
ガイドラインを設定する
内示の手順だけでなく、守るべきルール・ガイドラインも明文化して設定しておくとよいでしょう。
内示の定義・目的や、内示の対象となりうる相手は誰か、内示を受けた人の義務や責任はどのようなものか、といったガイドラインを設定することで、情報漏えいなどを防ぐことができます。
人事異動に関連する知っておきたい法的事項
人事異動を行う際に、従業員とトラブルが発生することを防ぐためには、関係する法律の規定に注意する必要があります。
本項目では、人事異動に関連する知っておきたい法的事項を紹介します。
労働契約に関する第3条の規定
労働契約法第3条は、労働者と使用者間の契約に関する基本原則を規定しており、人事異動においても、この法律を遵守することが必要です。
特に、入社時の労働契約において、職種や勤務地が特定されている場合、契約外の異動命令は権利の濫用として法令違反となる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
男女雇用機会均等法第6条に基づく義務
男女雇用機会均等法第6条は、人事異動において重要な法的基準です。
同条では、労働者の配置、昇進、降格、教育訓練において性別による差別を禁止しています。
従って、人事担当者や管理職が異動を検討する際には、性別に関する公平性を確保することが不可欠です。
育児・介護休業法の第26条に従った規定
育児・介護休業法第26条は、労働者が育児や家族の介護をおこなっている際の配置には配慮を必要とする規定です。
特に人事異動においては、労働者の育児や介護の状況を十分に考慮することが求められます。
就業場所の変更により、育児や介護を行うことが困難となる場合は、状況に合わせた配慮を行う必要があるため、事前に状況の把握を十分に行うことが重要です。
まとめ
人事異動の内示は、円滑な異動と業務継続のために欠かせない重要なステップです。
内示を行うことで従業員のモチベーション低下やトラブルが生じることを防ぐために、事前に十分な準備を行ったうえで内示を行うことが重要です。
適切に内示を行うことで、人事異動を円滑に進め、従業員と組織の成長につなげていきましょう。