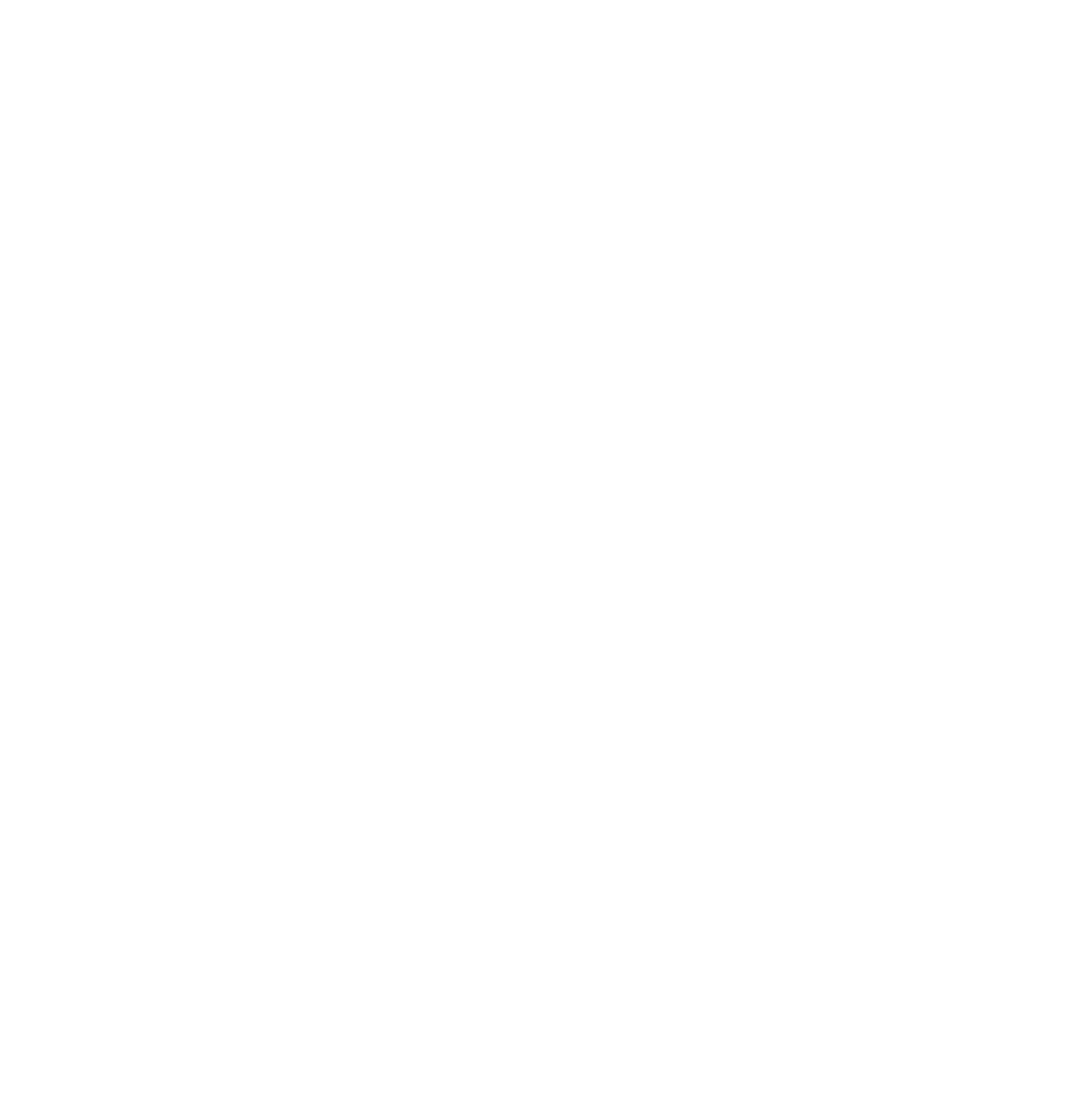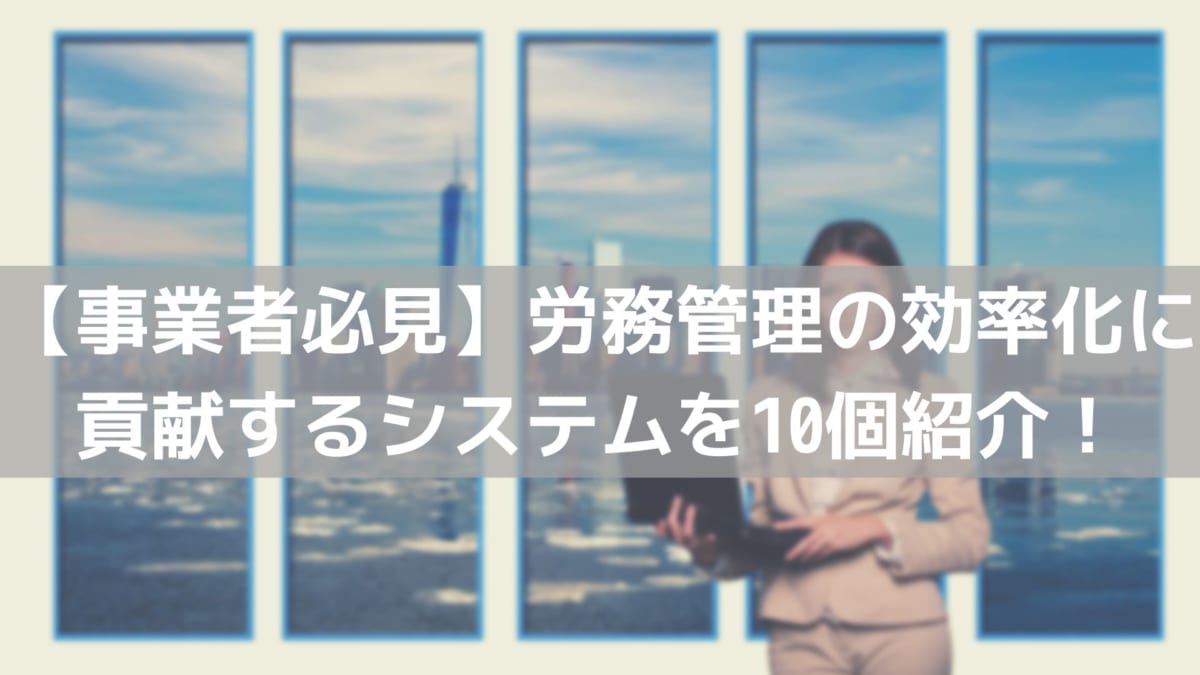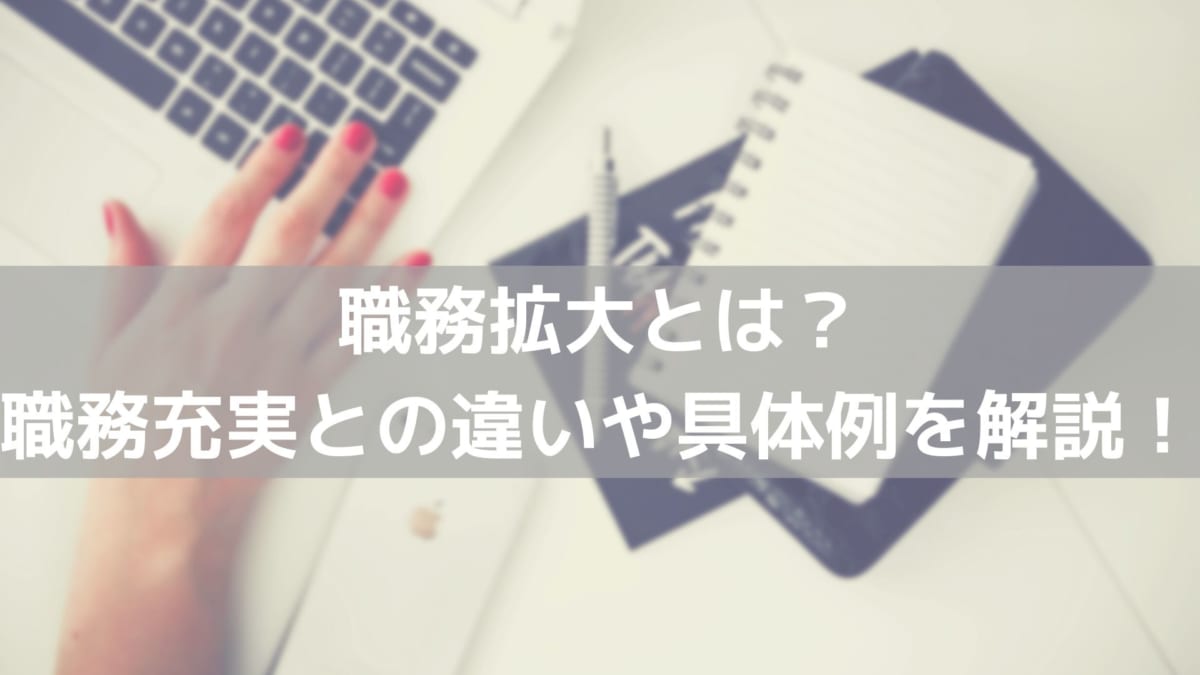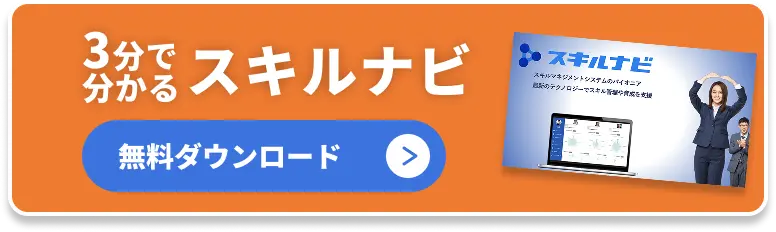生産性向上とは?生産性向上がなぜ必要なのかや推進するための手法を解説!

企業の業務効率や生産性を高めることは、今の社会では必須となっています。その背景には人口問題や海外の参入など、さまざまな変化が要因となっています。その変化に対応しなければ、日本の企業は衰退の一途を辿ってしまうでしょう。
今回は「効率化」と「生産性の向上」の違いや、その2つを達成できる方法について解説します。
生産性向上とは
低いコスト(資金や人材)を利用して高い結果を得ることで生産性は向上します。企業が支払うコストが低ければ低いほど、あるいは結果が大きければ大きいほど生産性は高いといえるでしょう。生産性に悩んでいる企業では、費用対効果が割に合わないことが原因と考えられます。
そのためには新しいツールやシステムを最大活用し、コストパフォーマンスを高める必要があります。
生産性向上の意味と目的
生産性とは、投資したリソース(人材や資金など)に対してどのくらいの結果を得たのかを表したものです。
リソースが少ない、あるいは高い結果だと生産性は向上します。生産性と似た言葉で「効率性」があります。効率性とは作業のムダを省き、その分の労働時間を削減することです。
そのため業務の効率化はあくまで「過程」であり、生産性の向上が「最終的な目標」といえます。「生産性」と「効率性」は似ているようでまったく意味が異なります。では企業が生産性向上を図る目的とは何でしょうか。
高齢化社会が進んでいる関係で、労働人口も次第に減少してきています。
人材の流動性も高くなっており、長期間企業に定着することは少なくなってきています。限られた人材で企業の成長につなげるためには、生産性の向上が必要不可欠です。今は人材の「量」より「質」が求められる時代となっています。
また競合となる企業は世界中に数多くありますが、日本の企業は決して優位性が高いわけではありません。時代の流れに乗ってニーズの変化に対応するには、競合に対して優位的な立場を確保する必要があります。優位性を確立するためには、企業が確保しているリソースをうまく活用して生産性を高めていくことが大切です。
業務効率化との違い
作業をスムーズに行うことが効率化であり、生産性を高めることが「最終目的」としたら「過程」ともいえるでしょう。効率化のみならず、結果的にどのような成果をどの程度高められるかを検討する必要があります。
生産性向上が必要な理由
効率化との違いを理解したうえで、生産性を高める理由について解説します。
労働人口の減少
少子高齢化社会により、日本は高齢層の割合が増え、若い世代が減少しています。労働人口も減少傾向し、企業の人材不足が深刻化しています。企業は限りある人的資源を活用し、生産性を高める方法を模索しなければいけません。そのためにはトレンドや最新技術を取り入れ、時代の流れを先取りすることが重要です。
会社を存続させるには、社会の変化に対して柔軟に適応するスキルを身につける必要があります。
海外企業との競争の激化
グローバルな時代である今、競合相手は国内だけではありません。国外の企業に対しても生産性で立ち向かう必要があります。もし国外に遅れをとってしまうと、日本の市場はすべて国外に占領されてしまいます。他の国と比較すると日本の生産性は低いので、一刻も早く生産性を高めなくてはいけません。
生産性向上のための具体的な取り組み
生産性向上の目的について説明しましたが、実際にどのような取り組みを行えばいいのかわからない方もいると思います。今回は5つに分けて生産性向上のための取り組み事例と方法を説明します。
人材の適材適所の配置
従業員のスキルにあわせた配置を行うことで、最大限のパフォーマンスを発揮できるでしょう。スキルにあわない配置だと、効率が悪化しエラーが増加するリスクがあります。
また適切な配置は従業員のモチベーション維持にも関わります。パフォーマンスが十分に発揮できない業務の継続は、やる気が低下し離職につながりかねません。
業務配置の重要性を理解し、慎重に検討する必要があります。
ツールやシステムの導入
「人材データの管理システム」や「コミュニケーション円滑ツール」といったサービスは豊富にあります。しかし「便利だから」という理由で導入しても、活用できなかったら意味がありません。
まずは自社の不足している点を探してみましょう。
- 業務に必要なコストが多い
- ミスが多発して非効率な業務がある
- 人材の細かい情報が把握できていない など
不足している点・伸ばしたい点を探すことで、必要なサービスが明確化します。ツール・システムを最大限に活かすためには、課題点を把握する必要があります。
テクニックの共有化
人材のスキルや経験は1人1人異なるので、同じ業務でも効率に差が生まれます。とくにベテランと新人では顕著に現れることが多いでしょう。業務効率の差を埋めるためには、テクニックを共有する機会を設けることが大切です。従業員の教育体制を作り、企業の生産性を高める取り組みを行う必要があります。しかし企業によっては教育体制を作るコストが足りないことが多いです。
その場合はアウトソーシングなどをうまく活用し、コストの削減を図りましょう。
業務の可視化と断捨離
生産性を高めるためには、不要な作業を省いてムダな時間を短縮させる必要があります。個人業務の可視化ができたら、次第に非効率な業務、ムダな業務などが浮き彫りになっていきます。その段階になったら業務の断捨離を行いましょう。不要な業務は排除し、非効率な業務は自動化したり、他の業務と関連づけたりすれば生産性の向上につながります。
ここで注意したいのが、やみくもに業務時間を減らすことと生産性が向上することはイコールではないということです。ムダを取り除くには、以下の点を意識してみましょう。
- 必要性がない業務か
- ツールの活用で効率が高まる業務か
- 業務の流れを簡略化できるか
自社の方針にあわせて断捨離の基準を作っておくことも大切です。また個人が抱えている業務の偏りにも注目してみましょう。業務を見直しても、従業員ごとに抱えている業務の量が異なる場合もあります。1人1人のマネジメントも生産性を高めるきっかけになります。
アウトソーシング
自社での効率化が難しい場合は、外注を利用するのもおすすめです。外注のメリットとして以下のことがあげられます。
・外注により作業の効率化が図れる
・従業員は重要な業務に専念できる
・費用対効果が得られやすい など
適切な外注で企業の生産性を高めやすくなるので、選択肢の1つとして検討してみましょう。
補助金の利用
資金面が原因で効率を高められない場合は、補助金の利用もおすすめです。ツールの導入時や人材教育の支援といった、さまざまな目的に応じて補助金を受けられます。補助金の利用には条件があるので、条件に当てはまっているか確認してから申請をしましょう。
取り組む際の注意点
さまざまな効率・生産性を高める方法を説明しましたが、実行には注意点があります。場合によってはマイナス効果になることもあるので、各ポイントに気をつけましょう。
マルチタスクによる逆効果
マルチタスクは一見作業効率がいいと思われがちです。しかし実際は効率が悪く、脳にかかる負担も大きいです。人の脳は2つ以上のタスクを同時に考えると、思考能力が大幅に低下するといわれています。生産性にも関わることなので、作業をするときは必ずシングルタスクを心がけましょう。
優先順位を決めてから、1つずつ着実にタスクに取り組んだ方が効率は高まります。
個人の生産性を重視しすぎない
業務効率が人材によって異なるように、生産性にも差が出ます。注意したいのが「個人の生産性を求めすぎる」という点です。生産性の向上はチーム全体で達成するもので、個人のみの課題ではありません。1人1人にフォーカスするだけでは、逆効果の場合があります。
全体を意識するためには以下の取り組みがあげられます。
・データ分析では具体的な数字を提示する
・ミーティングの目的を明確にする
・業務配置を見直す
視野を広げて、チーム全体の生産性を高めるような取り組みを考えましょう。
会議時間の短縮が目的化しないようにする
会議の質がよく、簡潔にまとまっていることに越したことはありませんが、決して早ければいいわけではありません。むやみに会議を短くすると、生産性が低下してしまうことがあります。
会議の質を高めるためには、以下の点を意識してみましょう。
・参加者はなるべく絞る
・あらかじめ概要を共有する
・空いた時間で会議を行う
会議のムダを省き、効率を高めるような工夫が大切です。
生産性向上の成功事例
企業がどのような方法を用いて効率化・生産性を高めることができたのか、その詳細について説明します。
GROVE株式会社
マーケティングの事業では多数のインフルエンサーを保有しているため、企業のネームバリューを広げることが必要でした。そのための手段として、営業のアウトソーシングを利用。コストが必要なリストやメール作成といった定型業務に対しては、自動化による効率化を図りました。従業員のノンコア業務の負担を減らすことで、自社製品の宣伝などの重要な業務に集中ができました。結果的に低コストで生産性を高めることに成功しています。
株式会社notteco
シェアリングエコノミーサービスの管理などの業務に対して、アウトソーシングを利用していました。しかし修正点が多発し、逆に負担が大きくなっていたので、専門のアシスタントが対応する別のアウトソーシングに切り替えました。結果的にコストを大幅にカットすることに成功。外注を依頼する際は、事前にどの程度まで業務を把握し、アクティブに実施してくれるかをチェックする必要があります。
株式会社サイバーエージェント
幅広いIT事業を手がけているこの企業では、チャットツールを導入することで生産性向上に成功しました。株式会社サイバーエージェントの今までの悩みは、メールを使用して具体的な説明を行ったり、解決策のアドバイスを行ったりする際に手間がかかることでした。その悩みを解決するために、よりカジュアルにやり取りができるようなチャット機能を搭載したツールを導入。その結果コミュニケーションにかかる業務の大幅な短縮が可能となり、集中すべき業務の時間を確保できるようになりました。
日本航空株式会社
日本航空株式会社では、業務の見直しで長時間労働となる原因を取り除き、生産性向上に成功しています。取り組み内容として、「20時には退社する」というルールを作りました。もう1つは企業に設置している固定電話は撤去し、Wi-Fi環境を整えたうえで従業員それぞれにスマートフォンを支給。この取り組みで残業を減らすとともに、従業員の勤務形態の選択肢を広げられるように環境を整えていきました。その結果時間外労働が減少し、従業員の満足度も高くなりました。
株式会社日立マネジメントパートナー
株式会社日立マネジメントパートナーではRPAの導入で生産性向上に成功しました。今までの悩みとして、企業が増えるごとにノンコア業務の処理が間に合わなくなることに頭を抱えていました。そのためRPAを導入した結果、ノンコア業務にかかる時間が短縮しコア業務へのリソースを十分に割けるようになりました。生産性に直結しないような業務にはRPAが効果的だということを、あらためて実感できる事例といえるでしょう。
まとめ
「効率化」と「生産性の向上」は似て非なるものであり、その違いを明確に理解する必要があります。この2つを高めるためには、限りある資源をうまく活用しなければいけません。
自社の特徴を理解したうえで、適切な方法を検討してみましょう。