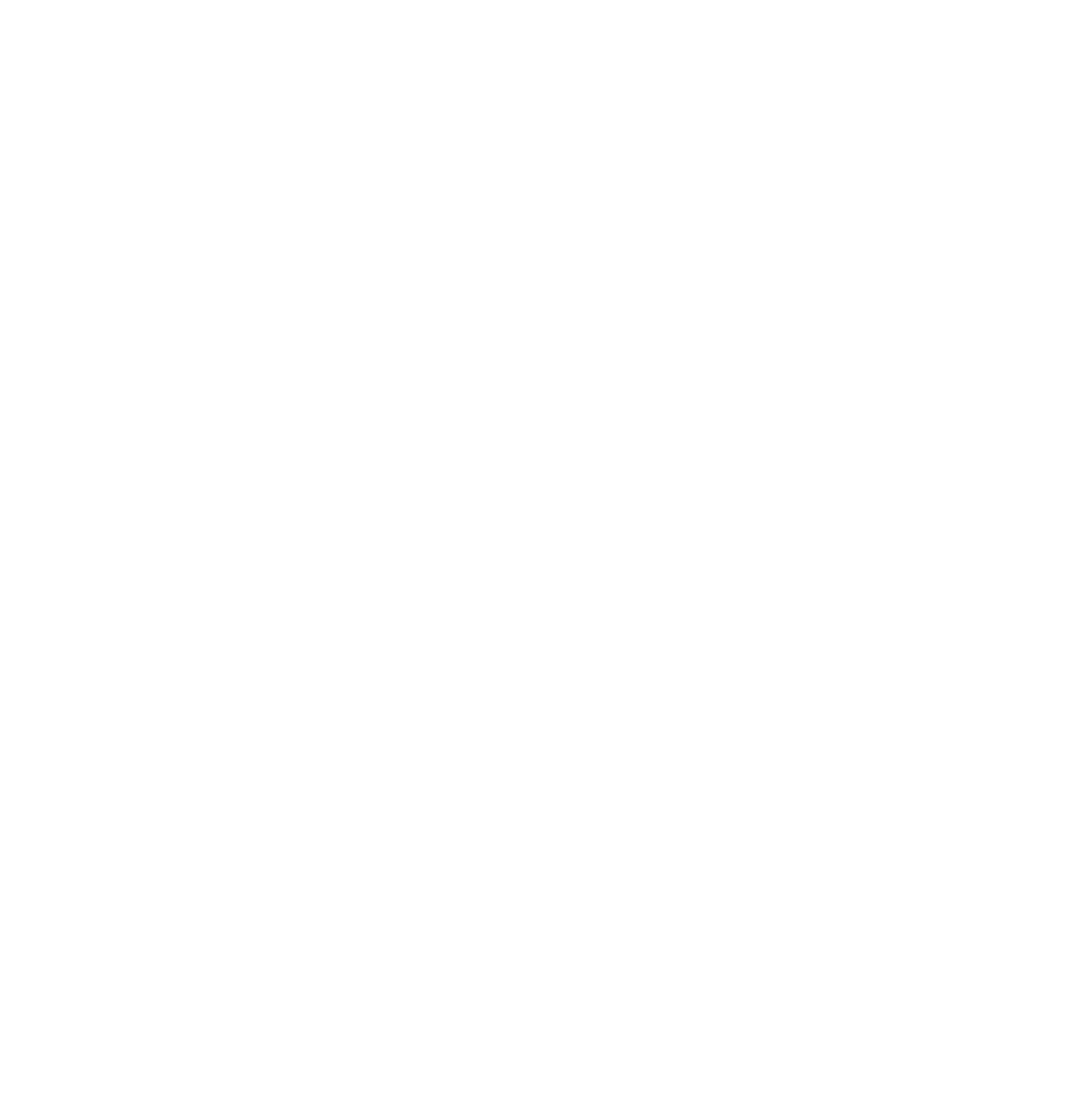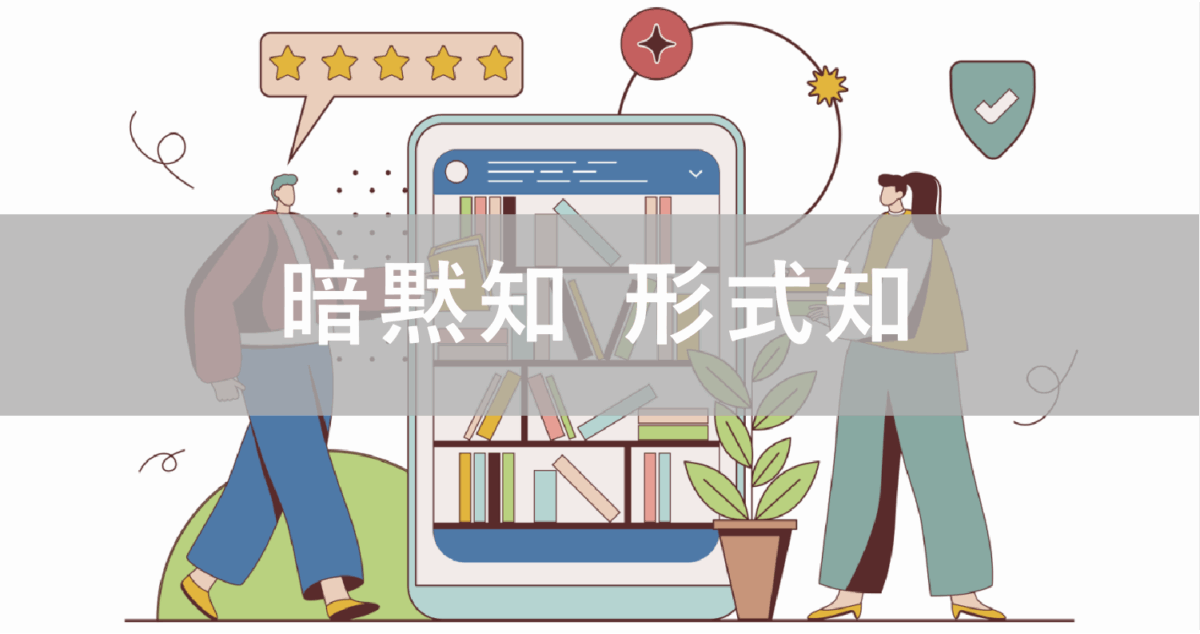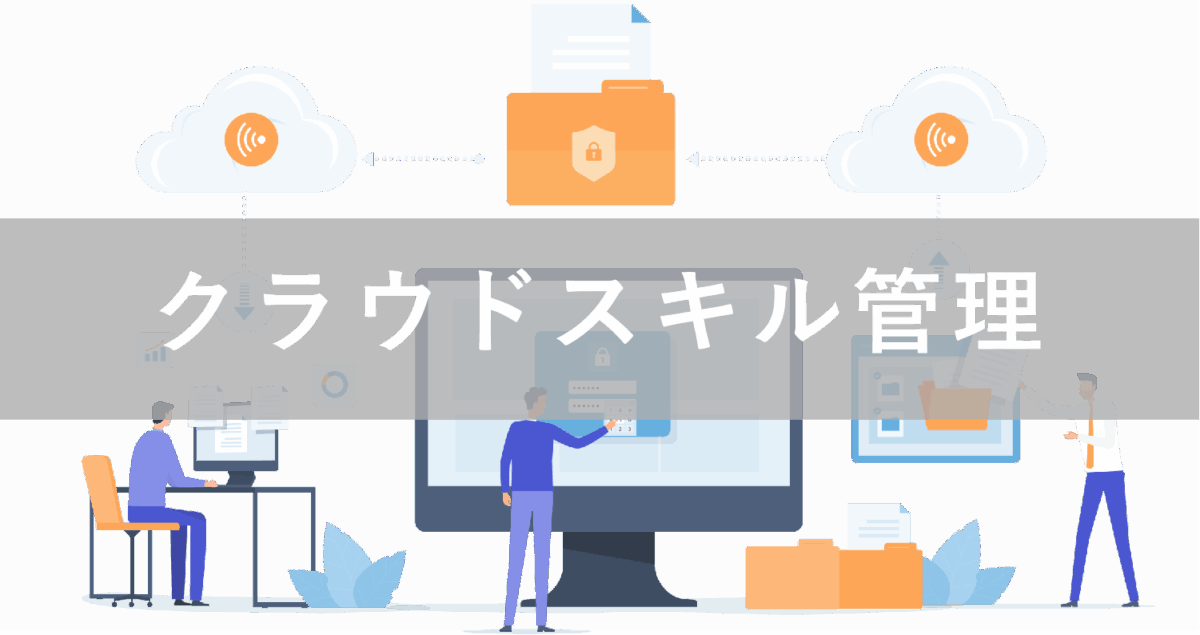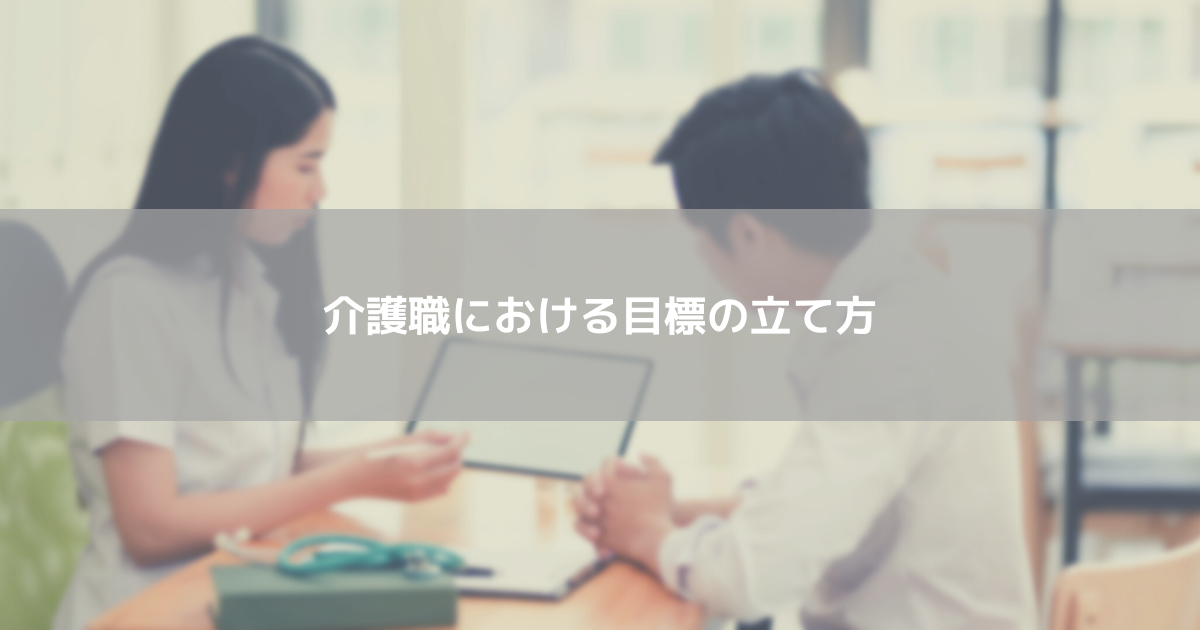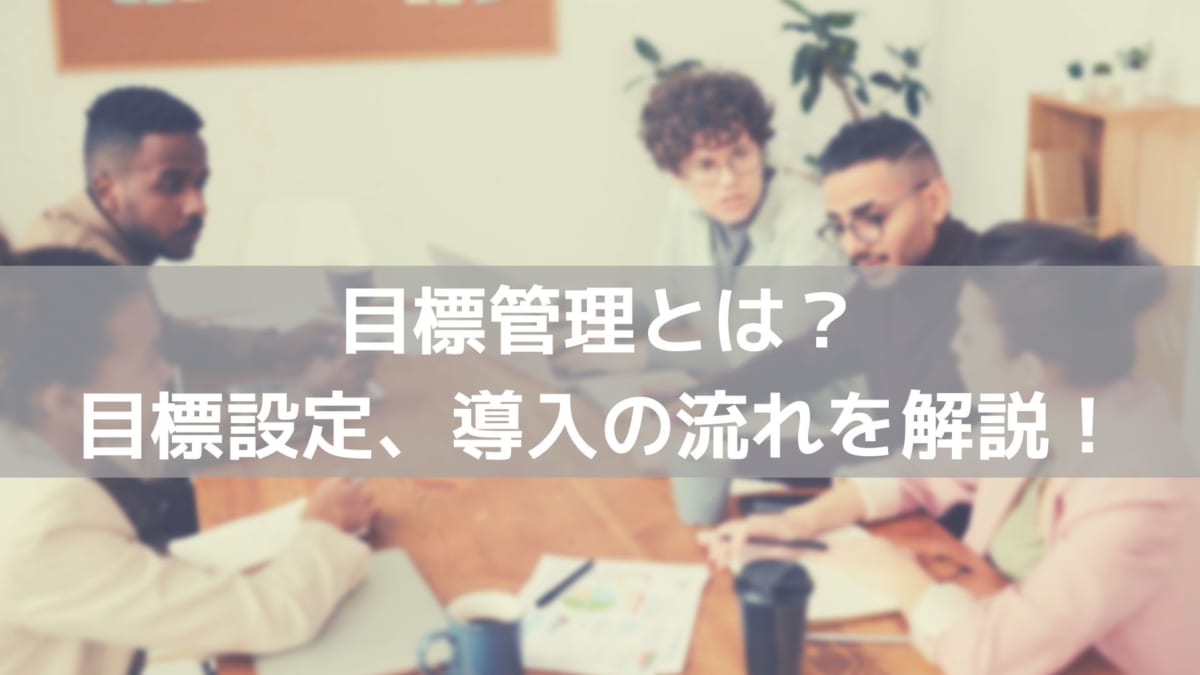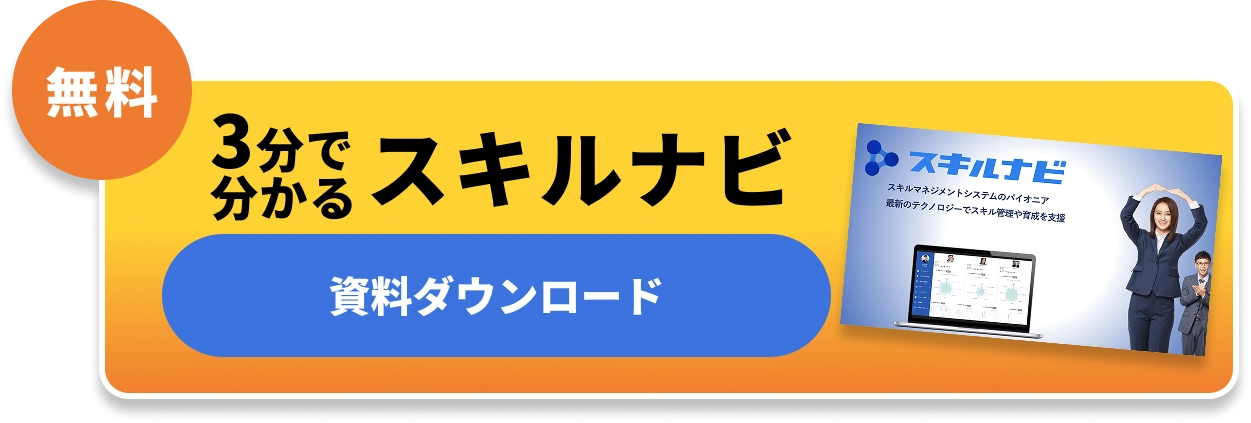スキル管理とは?目的やメリット、導入方法をわかりやすく解説

従業員一人ひとりのスキルを正しく把握し、戦略的に育成や配置につなげることは、多くの企業に共通する課題です。
その解決策として注目されているのが「スキル管理」です。
スキル管理を行うことで、人材育成計画の精度向上、従業員の納得感の醸成、さらには組織全体のエンゲージメント向上にもつながります。
本記事では、人材育成を担う方に向けて、スキル管理の目的やメリット、実践方法をわかりやすく解説します。
スキル管理とは
スキル管理とは、従業員が保有する知識・技術・資格・経験などのスキルを体系的に把握・整理し、育成や配置に活用する仕組みのことを指します。
単なる一覧表作成にとどまらず、組織の戦略目標や人材育成方針と連動させて活用する点が特徴です。
例えば「どの従業員がどの業務を担えるか」「将来のリーダー候補は誰か」といった視点で情報を活かすことで、計画的な教育や適材適所の人員配置が可能になります。
人材不足やスキルの属人化が課題となる企業にとって、スキル管理は組織力を高める基盤といえるでしょう。
タレントマネジメントとの関係
タレントマネジメントは、従業員が持つ才能や資質を経営資源とし、それらの有効活用によって組織や個人の成果を最大化し、経営目標の達成を目指す考え方です。
タレントマネジメントを効率的に実行するためには、従業員が保有しているスキルを組織で適切に管理し、把握をすることが重要です。
タレントマネジメントを経営目標達成の目的とするのであれば、スキルマネジメントはそれを実行するための手段の一つであるといえます。
人的資本経営との関係
人的資本経営は、企業や組織が人材を重要な資産として捉え、その能力や知識を最大限に活用する経営戦略のことを指します。
人材を資本として捉える人的資本経営は、企業の持続成長性や競争優位性を確保する基盤となります。
国際規格ISO30414では、企業経営においては人的資本開示が重要であると明記されており、スキル管理を実施することで、人的資本開示への説明性確保にもつなげることが可能となります。
スキルの種類
スキルとは、「技能」「技術」のことを表します。特に、「教育や訓練によって獲得した能力」を指し、使用されることが多い言葉です。その中でも、人事部門が管理すべきスキルは、コミュニケーション能力から業務に必要な専門知識まで、幅広く存在します。
では、具体的にはスキルにはどのような種類があるのでしょうか?本項目では、管理すべきスキルの種類を説明します。
1.ヒューマンスキル
ヒューマンスキルとは、良好な人間関係の構築・維持に必要なスキルです。一般社員ならコミュニケーション能力やチームワーク、管理職ならリーダーシップをはじめとする教育や調整にまつわるスキルが該当します。
2.テクニカルスキル
テクニカルスキルとは、業務上必要な専門知識や技術を指し、職種によって内容が異なります。例えば、下記が挙げられます。
・営業職であれば、自社の商材知識や、説明力
・生産技術職であれば、行程管理力や、商品知識
・マーケティング職であれば、分析力、企画力
3.コンセプチュアルスキル
コンセプチュアルスキルとは、様々な事象の本質を見極める能力を指し、ロジカルシンキングや柔軟性が該当します。論理的に思考するためのスキルであるロジカルシンキングや、物事への柔軟性など、特にトップの管理職層に求められるスキルです。
スキル管理の必要性
企業を取り巻く環境は、技術革新や人材不足、働き方の多様化などにより大きく変化しています。
こうした中で従業員のスキルを正しく把握できていないと、適切な人材配置や育成計画が立てられず、組織の成長が停滞してしまいます。
そのため、戦略的な人材活用を進める上で、スキル管理の重要性が高まっているのです。
ISO9001への対応
ISO9001では、従業員が業務を遂行するために必要な「力量(コンピテンシー)」を明確化し、継続的に維持することが求められます。
スキル管理は、この要求事項に対応するための有効な手段であり、各従業員のスキルを可視化・更新することで審査対応をスムーズにします。
また、適切な人材配置や教育計画につなげられるため、業務品質の向上や顧客満足度の改善にも直結します。
経営戦略と人材開発の連動
スキル管理は、企業の中長期的な事業計画と人材戦略をつなぐ重要な役割を担います。
経営目標を実現するために必要なスキルを定義・整理することで、人材育成の方向性を明確化できるだけでなく、人的資本経営の観点からも組織の投資価値を示せます。
経営視点を踏まえたスキル管理により、持続的な成長と競争力強化につながります。
組織力の向上
人材不足が深刻化する中で、限られた人員が持つ能力を最大限に引き出すことが組織には求められています。
スキル管理により従業員の保有スキルや不足分を把握することで、計画的な教育・育成を進められます。
また、スキルデータを基にした客観的な人材配置が可能になり、適材適所の実現を通じて組織全体のパフォーマンス向上につながります。
スキル管理の目的
スキル管理は、タレントマネジメントや人的資本経営にも良い影響をもたらします。
透明性が高い健全な経営を実施する一つの要素であることを踏まえると、スキル管理は社内外に影響力があります。本項目で、5つに分けてスキル管理の目的を解説します。
組織全体のスキル把握
スキル管理を実施することによって組織全体のスキルが把握できれば、自社の事業を進めるうえで、プロジェクトに携わっている個々の従業員や、組織が必要なスキルを保有しているかどうかを判断することが可能です。
実施することによって組織全体のスキル総量が把握し、人的資本の情報開示 ISO30414内の「スキルと能力」に対応することができます。
スキル維持
スキル管理を実行することで、どのようなスキルが従業員と組織に不足しているかの可視化ができるため、対策としてスキル維持のための研修や、従業員の育成方針などを立てやすくなります。
中長期的に伸ばしていきたいスキルや、失われるスキルの可視化を行うことによって、組織の実態把握が容易になるので、スキルの維持に役立ちます。
人材配置の最適化
スキル管理は、人材配置の最適化にも役立てることができます。
従業員一人ひとりがどのようなスキルや資格を保有しているかを可視化し、管理することができれば、プロジェクトのアサインや柔軟な人員移動にも効果を示します。
部署単位での配置はもちろんのこと、営業所や工場単位での大規模なアサインにも柔軟に対応できます。最適な配置を行うことで、例えば育成工数なども削減できるため、結果的に業績の向上にも繋がります。
スキル継承の効率化
スキル管理を行うことによって、事業において重要なスキルを持つ従業員が組織を去る場合でも、継承すべきスキルが可視化されていれば、スキル継承を効果的に進めることが可能です。
失われるスキルの可視化を事前に行うことによって、臨機応変な対応が可能になるうえ、技能伝承や多能工といった、スキルの継承にも効果を示します。
人事評価の公正化
従業員や組織が保有するスキルが可視化されると、客観的で公平な人事評価が可能になります。
これまで人事評価を上司の独断で実施していたり、評価基準が確立されていなかった場合、スキル管理を実施することで組織全体が保有するスキルを俯瞰しながら比較することができるので、結果的に属人化を防ぐことが出来ます。
公平な評価は人事評価に対する従業員の不満の減少にもつなげることができるので、結果的に働く従業員のモチベーションアップにもつながります。
スキル管理を導入しないリスク
スキル管理の重要性は理解していても、「導入しなくても業務は回る」と考える企業も少なくありません。
しかし、スキルを可視化せずに放置すると、組織に思わぬリスクが生じます。ここでは、スキル管理を導入しない場合に起こり得る問題を整理します。
適材適所の配置ができない
従業員のスキルを把握できていないと、誰がどの業務に最も適しているかを判断できず、人材配置が偏りやすくなります。
その結果、一部の従業員に負荷が集中したり、能力を活かしきれない配属が生じたりして、業務効率や成果の低下につながります。
スキル管理を導入することで、従業員の強みや不足を客観的に把握し、適材適所の配置を実現できるのです。
人的リスクが高まる
業務知識やスキルが個人に依存している状態では、担当者が退職や異動をした際にノウハウが途絶えてしまうリスクがあります。
結果として、後任への引き継ぎが不十分になり、業務の停滞や品質低下を招きかねません。
また、新しい人材の育成に余分な時間とコストがかかるため、組織の持続的な成長を阻害する要因となります。スキル管理はこうした人的リスクを未然に防ぐ有効な手段です。
育成方針が不明確になる
従業員のスキルを把握できていないと、成長度合いや課題を感覚的に評価せざるを得ず、適切な育成方針を描けません。
その結果、教育内容が属人的になり、効率的なスキル向上が難しくなります。
本人も成長の道筋を実感できず、モチベーションの低下や不公平感につながりやすいため、最終的には離職率の上昇を招くリスクもあります。スキル管理は育成を客観的に支える基盤となります。
社内リソースが有効活用できない
スキル管理を行わないと、実は活躍できる力を持つ人材が社内にいても見過ごされやすくなります。
その結果、他部署で人材が余っていても気づけず、新たな業務ニーズが出るたびに外部採用へと頼りがちになります。
こうした状況は採用コストを押し上げるだけでなく、既存社員の成長機会を奪うことにもつながります。スキル管理は社内人材の潜在力を引き出すための基盤です。
法的要請に対応できない
スキル管理を軽視すると、ISO9001で求められる力量管理や、近年注目される人的資本開示への対応が不十分になりがちです。
必要なデータを迅速に提示できない場合、外部審査や開示の場面で信頼性を損なうリスクがあります。
結果として、取引先や株主からの評価が低下し、企業の信用や競争力に影響を及ぼす可能性もあるため、法的要請に備えたスキル管理は欠かせません。
スキル管理の導入課題
スキル管理の重要性は理解していても、実際に仕組みを導入・運用する際にはさまざまな課題に直面します。
管理項目の設計やデータ収集の負担、現場の協力体制の確保など、事前に検討すべきポイントは少なくありません。ここでは、導入時に企業が抱えやすい課題を整理します。
管理手順や管理項目がわからない
スキル管理の対象項目は組織ごとに異なります。
そのため、管理する手順がわからなかったり、対象となるスキルを明確化できなかったりする企業も存在します。
従業員や組織のスキルを管理する手段として、紙やエクセルなどのアナログ管理を実施している場合は、更新タイミングや取得状況や今後の計画などに落とし込むことが難しいといえます。
スキル管理を実践しようとしても、スタートをする前に管理項目や方法を決められずに躓いてしまうことがあります。実践する際は、管理手順や管理項目を明確化しておくことが重要です。
スキル情報が更新されていない
スキル情報は半年から1年ごとに更新するのが理想的で、そのためには情報更新時のルールを設定しておく必要があります。
更新ルールを定めておかないと、情報が古いままの運用になってしまったり、収集したデータの形骸化につながってしまいます。そうならないためにも、データの維持期間や更新タイミングなどのルールを定めることが重要です。
スキル情報が活用されていない
情報の活用方法がわからなければ、スキル管理をしても成果につなげることができません。
目的をただスキル管理を実践することに定めるのではなく、あくまで目的は、スキル管理を実践した先に何を実現したいのかに定める必要があります。
目的によって、情報の活用方法を自社独自の活用方法を実践していくことが重要です。また、上層部だけでなく、スキル情報の活用方法を従業員に周知することで、全社としての取り組みにつなげることができるでしょう。
スキル管理でやるべき基本ステップ
スキル管理を効果的に活用するためには、行き当たりばったりの運用ではなく、一定の手順に沿って進めることが欠かせません。
スキルの定義からデータ収集、可視化、育成への反映まで、一連の流れを整理することで継続的に成果を出せます。ここでは、スキル管理に取り組む際に押さえておくべき基本ステップを紹介します。
スキルの棚卸
自社で定めている職種や役職などのスキルを棚卸する際は、組織ごとに管理の対象となるスキルを調整する必要があります。
業務に欠かせないスキルや資格を定めることで、新規プロジェクトのアサインや、新規事業へのメンバーアサイン、既存事業の継続にもつなげることができます。
管理対象となるスキルには、さまざまな業種に共通する一般的なスキルもあれば、業種ごとに必要とされる専門的なスキルもあるため、棚卸の際は注意が必要です。
情報管理
スキル管理を実施する際、各従業員の業務経験やキャリア、資格の取得日や期限日なども併せて可視化を行うことで、人材配置や社内教育の参考情報として活用することが可能です。
企業によっては特定のポジションで必須の資格やスキルなどが存在するところも多いでしょう。
スキルマップによるスキル管理の具体的な方法
スキル管理の代表的な方法には、スキルマップ(力量管理表)があります。
スキルマップは、従業員のスキルやそのレベルを可視化するツールやデータのことを指し、多くの企業で採用されているスキル管理方法です。本項目では、スキルマップによるスキル管理方法について、解説します。
1.作成者の設定
まず、管理者となる上司やマネージャー層が、スキルマップを作成します。
上司が部下の保有しているスキルや資格を把握し、設定を行います。
2.項目設定
スキルマップの項目は部署ごとに異なります。
管理者は業務に合う項目を設定する必要があります。資格だけではなく、求められるヒューマンスキル・テクニカルスキル・コンセプチュアルスキルも記載し、幅広く定義を行うことが重要です。
3.レベル設定
スキルマップを実践する際は、評価段階を決める必要があります。
評価段階は、使用される頻度が多い5段階評価である必要はなく、各職種に合ったレベルの設定が重要です。
4.評価者の設定
スキルマップは、評価者を直属の上司だけでなく、他部署の上司も評価者に加えるなどして多角的にステークホルダーが活用できる方式にする必要があります。
どのレイヤーの人物も活用できるものを作成することによって、汎用性が高まります。
5.管理
スキルマップの運用時は、スキルマップ担当者を設定して管理してもらったり、評価者が定期的に更新したりする方法があります。
運用が社内で形骸化しないよう、管理フローを策定することも重要でしょう。
6.更新
スキルマップは一回のタイミングのみで作成するだけで良いものではなく、更新をかけ、常時アップデートを行い続けることによって、より効率的に運用し続けることができます。
スキルマップが必要になった都度更新をかけると、更新の工数が掛かってしまい、運用が形骸化してしまいます。そのため、スキルマップの定期更新は不可欠です。
なぜ更新をするのか、なぜスキルマップを運用するのか?を従業員に動機付けを行ったり、更新タイミングのリマインドの仕組みをつくることが重要です。
スキル管理で従業員の強みを最大限生かそう
スキル管理は、企業のタレントマネジメントや人的資本経営に良い影響を及ぼします。
スキル管理を実施することで、従業員と組織が持つスキルを適切に把握し、スキルをベースとしたデータを有効活用することが可能となります。
当社が提供するサービスのスキルナビは、スキルマネジメントシステムの活用で、戦略的なスキル開発・組織活性化が実現できるサービスです。
既存データをデータベース化し分析・比較ができたり、キャリアパスとの連動や育成施策や資格の紐づけも行うことができます。ご興味をお持ちの方は、下記よりお問い合わせください。