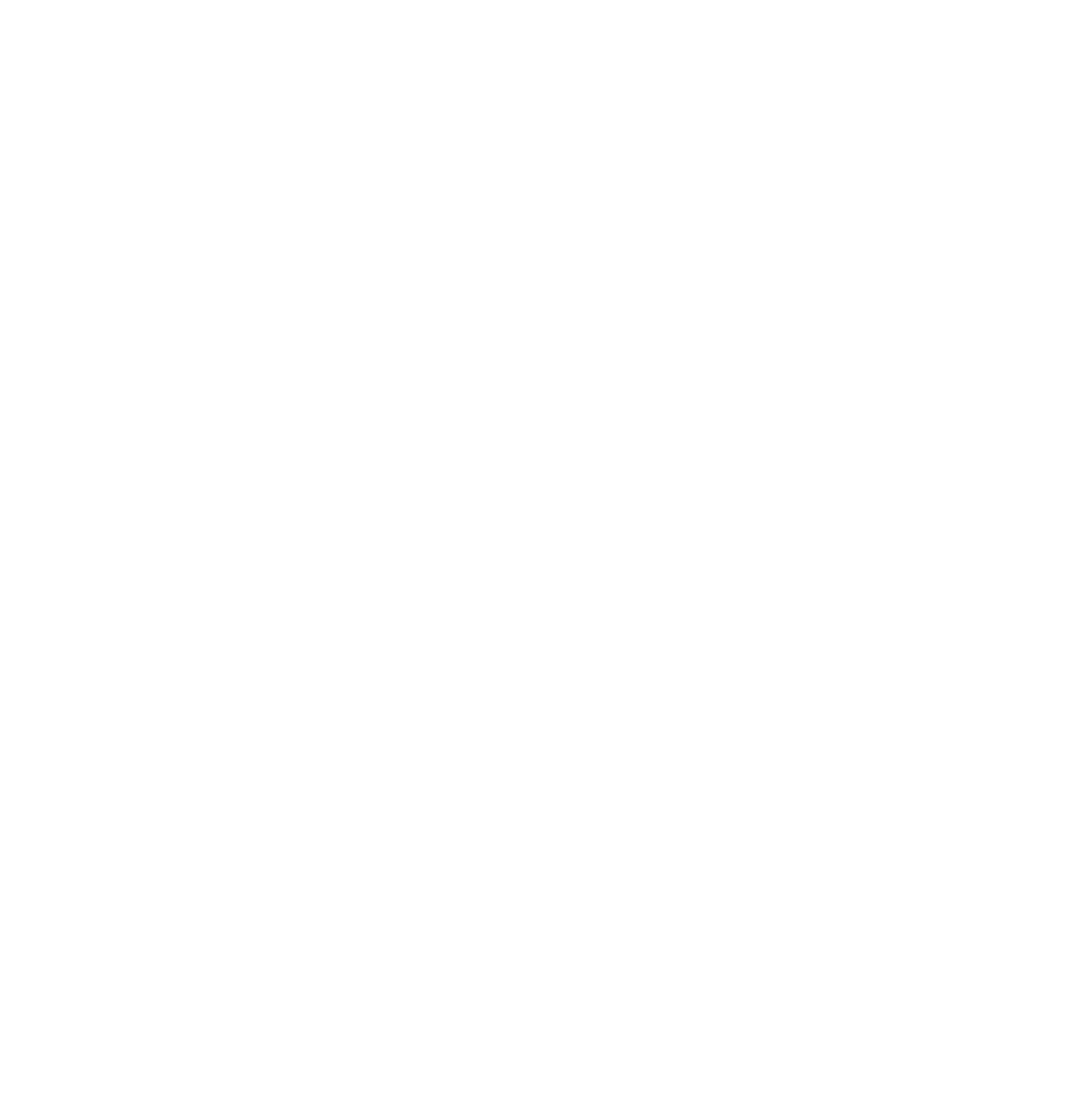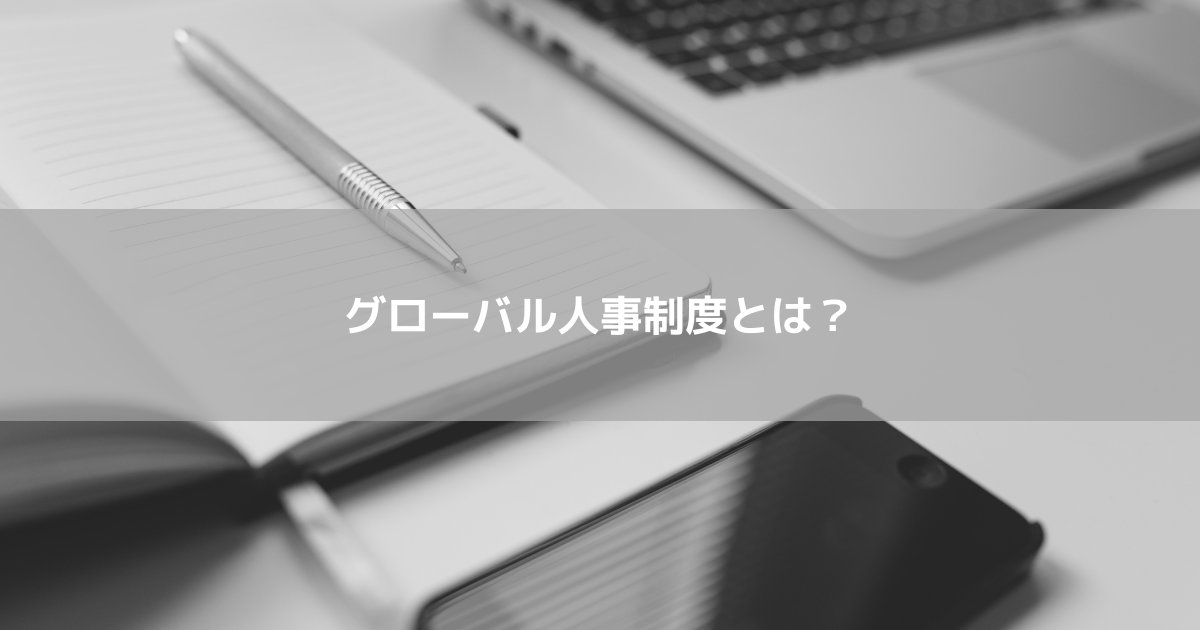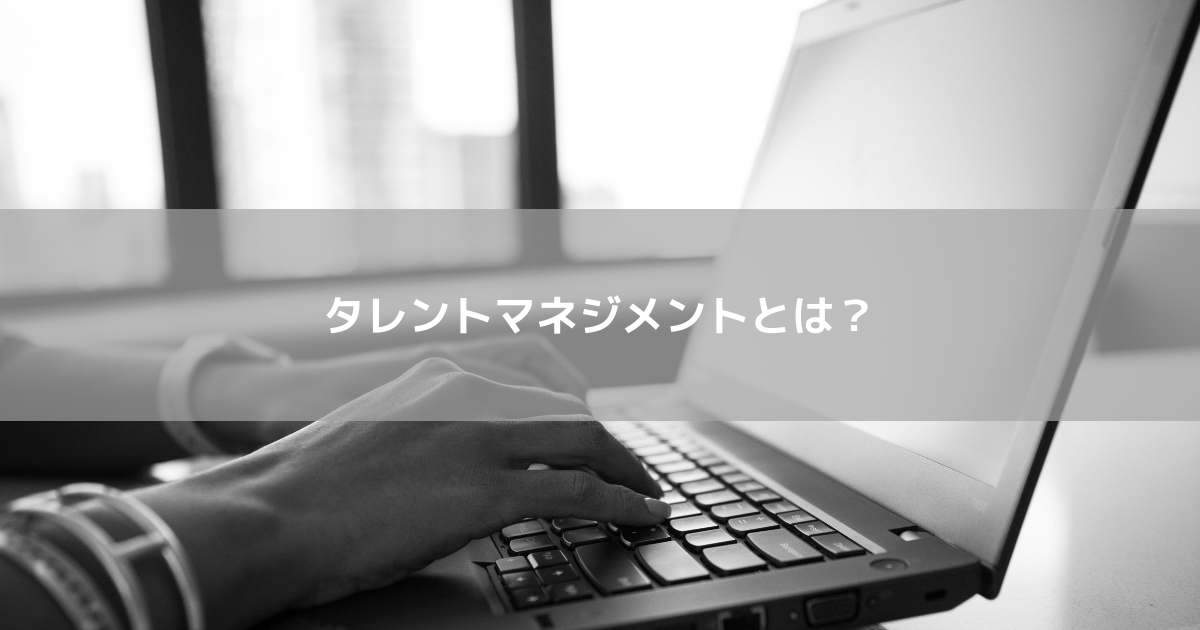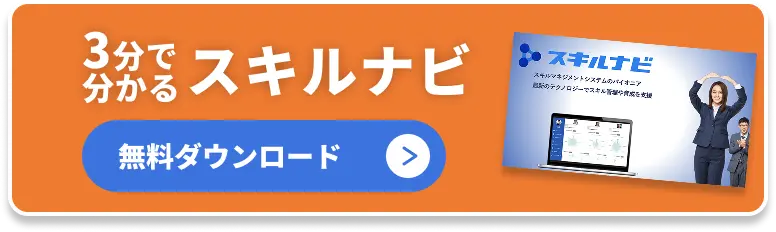タレントマネジメントシステムの成功事例9選|課題解決から導入効果までわかりやすく解説
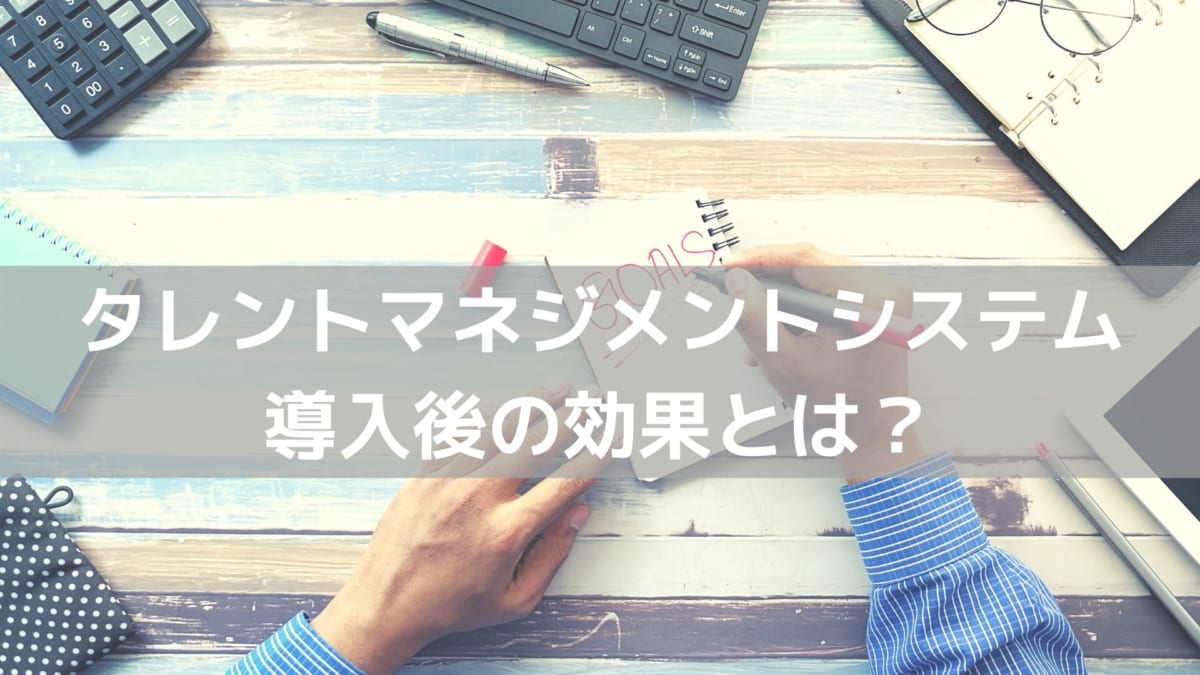
タレントマネジメントシステムの導入は、人材育成や配置の最適化、離職率の改善などに効果を発揮します。
一方で、導入後の運用に課題を抱える企業も少なくありません。
この記事では、実際の成功事例9社を取り上げ、導入前の課題から効果までを具体的に紹介します。これから導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
KDDI株式会社:人財育成への活用
導入前の課題
通信業界は技術革新が早く、社員一人ひとりに求められるスキルも多様化していました。
KDDIでは従来、各部門ごとに人材データが分断されており、社員のスキルやキャリア志向を全社的に把握することが困難でした。
その結果、
・部署異動やプロジェクトアサイン時に適材適所の判断が難しい
・社員のキャリア希望と会社の人事方針をすり合わせづらい
・若手人材の育成・登用計画が属人的になりやすい
といった課題が発生していました。
特に、スキルや経験の見える化が進んでいなかったため、次世代リーダーの育成計画を立てにくい点が大きな課題となっていました。
導入の経緯と工夫
こうした課題を受け、KDDIはタレントマネジメントシステムを活用し、全社員のスキルやキャリア情報を一元化する仕組みを構築しました。
導入にあたっては、システムを“人事部門だけのツール”とせず、社員が自らキャリアを描くためのプラットフォームとして位置づけた点が特徴です。
具体的には、
・スキルやキャリア希望を社員自身が登録・更新できる仕組み
・上司と部下の1on1でのキャリア対話に活用できる設計
・データ活用を前提とした部門間共有のルール整備
といった運用面の工夫を取り入れました。
このように、現場主導の仕組みづくりを進めたことで、社員の納得感を得ながら全社的な定着を実現しています。
導入効果
システム導入後は、人材データをもとにした戦略的人事の意思決定が可能になりました。
例えば、スキルやキャリア志向に応じた配置・育成が行えるようになり、リーダー候補の早期発掘や育成計画の精度が向上。
さらに、社員自身が自分のキャリアを可視化し、自律的に学ぶ姿勢が生まれたことも大きな成果です。
結果として、KDDIでは「個人の成長」と「組織の最適化」を両立する人財マネジメントを実現しています。
ソフトバンク株式会社:エンジニアスキルの可視化と育成支援
導入前の課題
ソフトバンクでは、通信・AI・IoT・ロボティクスなど幅広い事業領域を展開する中で、エンジニアが担う専門分野が多様化していました。
しかし、社内では「誰がどの領域に強みを持つのか」「次世代リーダーをどう育てるのか」といったスキルの全体像を把握する仕組みが不足していました。
その結果、
・プロジェクトに最適な人材をアサインするのが難しい
・技術領域ごとのスキルレベルを客観的に評価しづらい
・エンジニア自身が自分の強みや課題を把握しにくい
といった課題が浮き彫りになっていました。
また、技術の進化スピードが早い中で、どのスキルを優先的に育成すべきかの判断も属人的になっていた点が大きな課題でした。
導入の経緯と工夫
ソフトバンクはこうした課題を解決するため、タレントマネジメントシステムを活用してエンジニアスキルを定量的に可視化する仕組みを導入しました。
導入のきっかけは、「スキルを“見える化”し、育成を戦略的に進めたい」という経営方針によるものでした。
・導入に際しては、単にスキルを一覧化するだけでなく、
・業務ごとに必要となるスキルセットを定義
・自己評価と上司評価の両軸でスキルを登録
データを育成計画やキャリア面談に活用
といった「運用まで含めた仕組みづくり」を行った点が特徴です。
さらに、評価を「査定」ではなく「成長支援」の観点で運用することで、
社員が自発的にスキル登録を行い、“キャリアの棚卸し”を習慣化できるよう工夫されています。
導入効果
システム導入後は、全社的なスキル可視化が進み、エンジニア人材の配置や育成方針がデータドリブンに決定できるようになりました。
特に、スキルデータをもとにした研修設計や学習機会の提供がスムーズになり、スキルギャップの早期発見と育成計画の最適化が実現。
また、エンジニア自身が自分のスキルを客観的に把握し、
「どの技術を学べば次のステップに進めるか」を明確にできるようになったことで、自律的な成長を後押しする文化が根づきつつあります。
結果として、ソフトバンクではエンジニアのスキル開発とキャリア支援を両立し、戦略的人材育成の基盤を確立しました。
三井住友トラスト・システム&サービス株式会社:採用や人財配置への活用
導入前の課題
SMTSS では、従来 自社専用にカスタマイズされた評価・スキル管理システム を使っていたものの、システムが老朽化しており拡張性やメンテナンス性に限界があったという情報があります。
また、汎用性の高いプラットフォームではないため、スキルデータの蓄積・横断検索・分析機能が十分ではなく、“人財配置” や “適性把握” に活用しきれないというジレンマがあったようです。
特に、従業員一人ひとりのスキルや経験、適性を基に 最適な配置を判断する仕組み が弱く、配置ミスマッチのリスクや、育成コストが見合わないケースも想定されていたと考えられます。
さらに、採用と配置を別々のプロセス・システムで管理していた場合は、採用段階で得たデータをその後の社内配置に生かしにくい、という“分断”の問題もあった可能性があります。
導入の経緯と工夫
SMTSS は、これまでの 専用システム+カスタマイズ から、より 汎用的/拡張性のあるシステム への移行を検討したようです。これは、長期的な運用性と将来的な拡張を見据えた判断といえます。
導入時には、既存データ(従業員スキル・評価履歴など)を移行するための マッピング設計 を慎重に行ったと考えられます(たとえば、カスタム項目のマッチング、データクレンジングなど)。
また、運用フェーズで鍵になるのは、“どう社員に使ってもらうか” の仕組みづくりです。可能性として以下のような工夫が考えられます:
・社員自身がスキル登録や更新できる UI を整備
・配置・異動の際にスキルマッチング機能を提示
・上司レビューや適性面談と連動させるルール整備
・データの見える化ダッシュボードを設定し、管理者・現場双方が使いやすいよう権限設計
さらに、システムベンダーや導入パートナーによる伴走支援(初期設定支援、定着支援)を受けながら、現場の声を反映して運用をブラッシュアップした可能性があります。
導入効果
タレントマネジメントシステムの導入により、社員のスキル・経験データを一元管理できるようになりました。これまで部門ごとに分断されていた人材情報を可視化することで、採用から配属までのプロセスがスムーズに。適性や志向に基づいた配置が可能となり、ミスマッチの軽減や育成計画の精度向上につながりました。また、データ分析を通じて人材ポートフォリオを俯瞰できるようになり、戦略的な人財配置と組織全体の最適化を実現しています。
⇒ 詳しい三井住友トラスト・システム&サービス株式会社様の導入事例記事はこちら
日産トレーデイングオペレーションジャパン株式会社:140日分の工数削減
導入前の課題
日産トレーディングオペレーションジャパンでは、従業員のスキルや資格情報、評価データなどをExcelや紙で管理しており、データの更新や照合作業に多くの時間がかかっていました。
また、情報が部門ごとに分散していたため、最新のスキル状況を把握するのが難しく、育成計画や人材配置の判断に時間を要する点も課題でした。
特に、グローバルに展開する企業として、各拠点で管理フォーマットが異なり、データ集計のたびに人事担当者が手作業で確認する必要がありました。
導入の経緯と工夫
これらの課題を解決するため、日産トレーディングオペレーションジャパンは、タレントマネジメントシステムを導入し、人材データの一元管理を進めました。
導入の決め手は、既存のExcel管理を自動化しつつ、全社員のスキル・評価データを統合できる柔軟性にありました。
運用開始後は、社員情報の登録・更新ルールを標準化し、入力ミスを防ぐ仕組みを整備。さらに、管理項目を整理して“見るべきデータ”を絞り込み、日常的に活用できるUI設計を意識しました。
現場と人事部門が共同で要件をすり合わせたことで、定着率の高い仕組みを構築しています。
導入効果
システム導入により、従来Excelで行っていた人材情報の更新・集計作業が大幅に効率化。
年間で約140日分の工数削減を実現しました。
手作業での情報収集や二重入力が不要となり、データの整合性や更新スピードも向上。
人事担当者は管理業務にかけていた時間を、育成や配置戦略といった“より付加価値の高い業務”に振り向けられるようになりました。
また、スキルや評価データがリアルタイムに可視化されたことで、経営層も最新情報をもとに迅速な意思決定を行える体制が整いました。
⇒ 詳しい日産トレーデイングオペレーションジャパン株式会社様の導入事例記事はこちら
エイデイケイ富士システム株式会社:人財育成・目標管理への活用
導入前の課題
エイデイケイ富士システムでは、社員の目標管理や評価プロセスを紙やExcelで運用しており、
進捗確認や評価集計に多くの手間と時間がかかっていました。
また、上司・部下間の1on1や目標面談が形式的になりがちで、人財育成につながるフィードバックの仕組みが十分に機能していないという課題もありました。
加えて、各部署で評価基準や管理方法がばらついており、全社的な育成方針の統一にも課題がありました。
導入の経緯と工夫
こうした課題を解消するため、同社はタレントマネジメントシステムを導入し、目標設定・評価・育成を一元的に管理できる仕組みを構築しました。
導入に際しては、社員一人ひとりが主体的に目標を立て、進捗を記録・更新できるよう、シンプルで直感的な画面設計を重視。
また、評価データと育成履歴を連動させることで、面談時に「成長の過程」が可視化されるよう工夫しました。
運用フェーズでは、上司・部下双方にシステム活用の目的を共有し、“評価のための管理”から“成長のための対話”へと意識を変える取り組みを進めています。
導入効果
システム導入により、目標設定・進捗確認・評価フィードバックがオンライン上で完結するようになりました。
これまで紙やExcelで行っていた管理業務が効率化され、評価集計の手間を大幅に削減。
上司・部下のコミュニケーションも活性化し、定期的な1on1を通じて目標達成に向けた具体的なアクション設計が可能になりました。
また、評価データと育成履歴を紐づけて分析できるようになったことで、人事部門は社員の成長傾向を可視化し、次期育成計画の立案にも活用できるようになっています。
⇒ 詳しいエイデイケイ富士システム株式会社様の導入事例記事はこちら
株式会社エルテックス(ELTEX, Inc.):スキル向上計画の実現
導入前の課題
エルテックスでは、社員一人ひとりのスキルや資格、キャリア志向を紙やExcelで管理しており、
部門ごとの育成方針や教育計画が属人的になっていました。
そのため、誰がどのスキルを保有しているのか、どの領域を強化すべきかを把握するのが難しく、
個人の成長を支援する体制づくりに課題を抱えていました。
また、スキル評価が上司や現場判断に依存していたため、評価のばらつきが生まれ、
社員が自身の成長を客観的に確認できる仕組みも十分ではありませんでした。
導入の経緯と工夫
こうした課題を解消するため、エルテックスはタレントマネジメントシステムを導入し、
スキルの可視化と育成計画の一元管理を進めました。
導入にあたっては、各職種・職位に求められるスキルを定義し、社員が自己評価を通じて現状を把握できる仕組みを構築。
さらに、上司との面談でスキルギャップを明確化し、具体的な成長目標と研修計画を紐づける運用を取り入れました。
運用初期は、スキル登録や評価方法の標準化を図り、社員が自ら育成計画を更新できるよう社内説明会やマニュアル整備を実施。
「自らの成長を“見える化”する」文化づくりを重視しました。
導入効果
導入後は、社員のスキルデータが一元的に管理され、育成計画の立案や進捗確認が効率化。
個人ごとのスキルレベルや目標達成度が可視化されたことで、上司との対話も具体化し、
社員自身が主体的に学習テーマを設定する仕組みが定着しました。
また、部門ごとのスキル分布を分析することで、教育投資の重点領域を明確化。
全社的にスキル開発の方向性を統一できるようになり、人材育成のPDCAが循環する体制が整いました。
結果として、社員の成長意欲向上と、組織のスキル強化を両立しています。
アルプス システム インテグレーション株式会社(ALSI)様:スキルの可視化と効果的なスキルアップ
導入前の課題
ALSIでは、エンジニアを中心に多様なスキルを持つ社員が在籍していましたが、
誰がどの領域に強みを持ち、どのスキルを強化すべきかを定量的に把握する仕組みがありませんでした。
そのため、部門やプロジェクト単位でのスキル管理が属人的になり、
育成施策や研修の効果測定を行うことが難しい状況でした。
また、社員自身も自分のスキルを客観的に評価する指標がなく、
「何を学べばキャリアアップにつながるのか」が見えづらいという課題を抱えていました。
導入の経緯と工夫
こうした課題を受け、ALSIはタレントマネジメントシステムを導入し、
全社員のスキルを可視化・分析できる環境を整備しました。
導入の目的は、スキル情報を一元化して「組織としての強み」と「個々の育成課題」を明確化することにありました。
導入時の工夫として、
・各職種に必要なスキルを定義し、段階的なスキルレベルを設定
・社員の自己評価と上司評価を併用し、客観性を担保
・可視化したデータをもとに、個人ごとのスキルアップ目標や研修計画を作成
といった仕組みを整え、「見える化から行動につなげる」運用設計を重視しました。
また、システムの定着を促すため、社員向け説明会や操作マニュアルを整備し、「スキル登録=キャリア形成の第一歩」と位置づける意識づけを行いました。
導入効果
システム導入により、社員のスキル情報が一元的に管理され、
現状のスキルレベルと育成課題を可視化できるようになりました。
これにより、個人単位での学習テーマや研修参加が明確化し、
社員の自律的なスキルアップが促進。
また、部門ごとのスキル傾向を分析することで、
組織として不足するスキル領域を特定し、重点的な教育施策を立案できるようになりました。
結果として、社員一人ひとりの成長実感が高まり、
企業全体でのスキル基盤強化と育成効率の向上を実現しています。
⇒ 詳しいアルプス システム インテグレーション株式会社の導入事例記事はこちら
株式会社インフォセンス(山九グループ):プロジェクトアサインと能力評価の適正化
導入前の課題
インフォセンスでは、プロジェクトごとに必要とされるスキルや経験値が異なる一方で、
社員のスキル・実績データを統一的に管理する仕組みが整っていませんでした。
そのため、最適な人材配置やプロジェクトアサインを判断する際に、情報が属人的になりやすいという課題がありました。
また、能力評価も上司の主観に頼る部分が多く、スキルや成果が十分に可視化されていなかったため、
社員が「何を基準に評価されるのか」を把握しにくい状況でした。
結果として、評価の納得感が得にくく、モチベーションやキャリア形成にも影響を及ぼしていました。
導入の経緯と工夫
こうした課題を解消するため、インフォセンスはタレントマネジメントシステムを導入し、
スキル・実績・評価データを統合管理するプラットフォームを構築しました。
導入の目的は、客観的なスキルデータをもとに「最適なアサイン」と「公平な評価」を両立することにありました。
導入時には、職種・レベルごとのスキル定義を行い、
社員が自己申告・上司承認の2段階でスキルを登録する仕組みを採用。
また、過去のプロジェクト実績や取得資格も紐づけることで、
経験とスキルの両面から人材を把握できるように設計しました。
評価面では、定量的なスキル指標と定性的な成果コメントを併用し、
上司と部下の面談に活用することで、フィードバックの質を高めています。
導入効果
システム導入により、社員のスキル・実績情報をもとにした最適なプロジェクトアサインが可能になりました。
属人的だった配置判断がデータドリブン化し、必要スキルに応じた人材選定がスムーズに。
また、スキル評価の基準が明確化されたことで、評価プロセスの透明性が向上しました。
社員は「自分の強み・課題」を客観的に把握できるようになり、
キャリア形成への納得感と主体性が高まっています。
さらに、評価データを蓄積することで、将来的には人材育成や後継者計画にも活用できる基盤を整備することができました。
株式会社クロスキャット:テレワーク個別研修の実現
導入前の課題
クロスキャットでは、テレワークの拡大に伴い、新入社員や若手社員へのOJT・研修の機会が制限され、
育成内容や指導の質にばらつきが生じることが課題となっていました。
従来は対面で行っていた教育や進捗確認がオンライン化に対応しきれず、
上司や教育担当者が一人ひとりの習熟度を把握することが難しい状況でした。
また、研修内容や学習履歴を紙やExcelで管理していたため、
「どのスキルが定着しているか」「次に何を教えるべきか」を客観的に判断しづらいという問題もありました。
導入の経緯と工夫
こうした課題を受け、クロスキャットはタレントマネジメントシステムを導入し、
社員ごとのスキル習得状況を可視化しながら、オンラインでも個別最適な研修を実施できる体制を構築しました。
導入時には、業務に必要なスキルを一覧化し、レベル別に定義。
社員が自己評価を行い、上司がそれを確認・更新できる仕組みを整備しました。
また、スキルデータを研修プログラムと連動させることで、
習熟度に応じた課題提示や、リモートでも“今必要な学び”を提供できる仕組みを実現。
さらに、定期的な1on1や進捗レビューを通じて、
上司・教育担当が個々の成長をフォローアップできるよう設計されました。
導入効果
システム導入により、社員のスキル習熟度や研修進捗をリアルタイムで把握できるようになりました。
これにより、テレワーク環境下でも一人ひとりに合わせた研修内容の設計が可能となり、
OJTや教育担当者の負担も軽減。
スキルの定着度を可視化することで、社員自身も成長を実感しやすくなり、
学びへの意欲向上と育成スピードの均質化を実現しました。
また、研修履歴を蓄積することで、将来的には人材育成計画やキャリア支援にも活用できる基盤が整いました。
成功事例に学び、タレントマネジメントを前進させよう
本記事では、各企業がタレントマネジメントシステムを活用して、
人財育成・評価・配置・スキル可視化といった課題をどのように解決したのかをご紹介しました。
成功の共通点は、「データを活かし、人を活かす」こと。
属人的な管理から脱却し、社員一人ひとりの強みを最大限に引き出す仕組みづくりが求められています。
今回の事例を参考に、自社の人材戦略を見直し、タレントマネジメントを次のステージへと進めていきましょう。