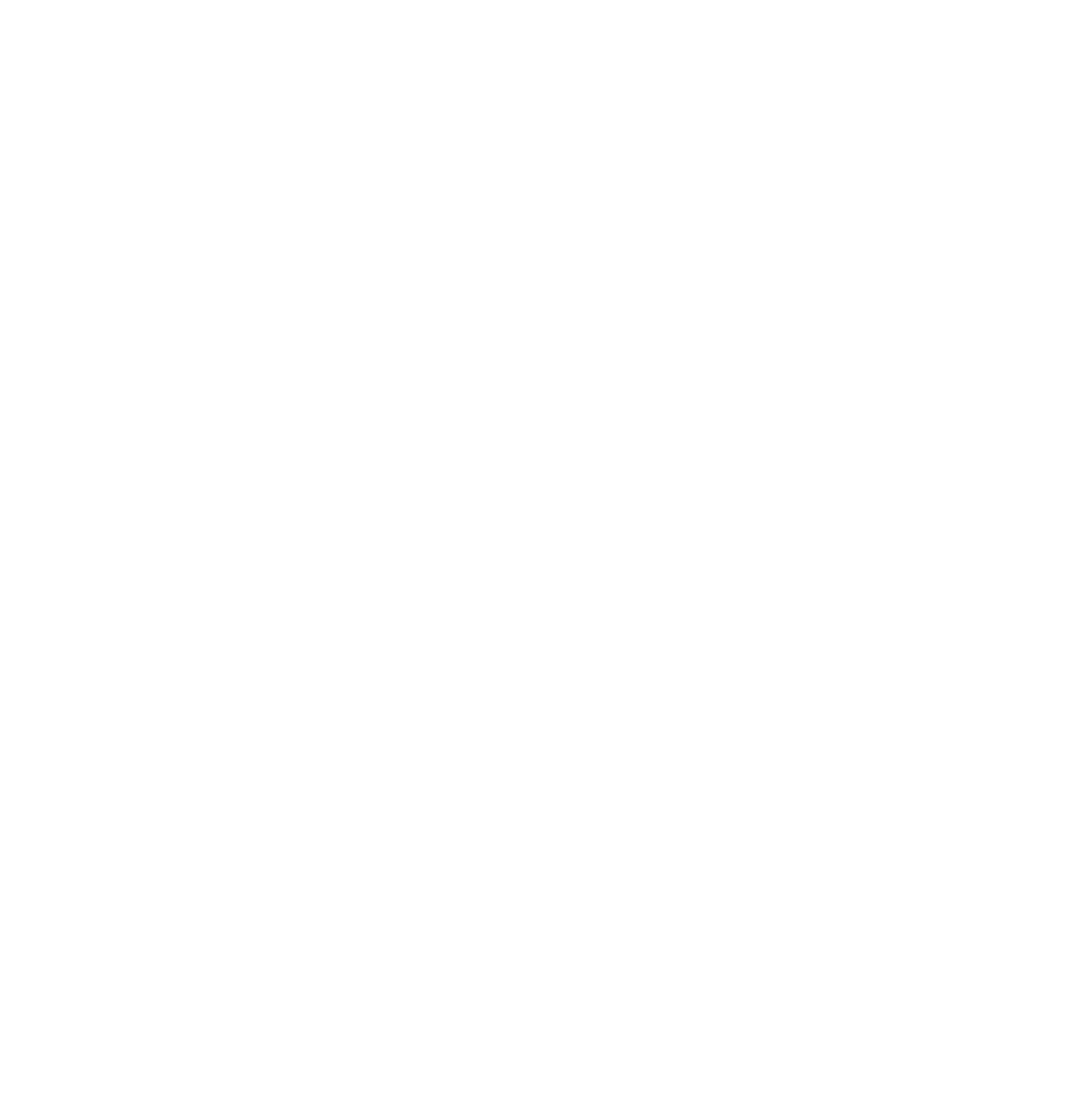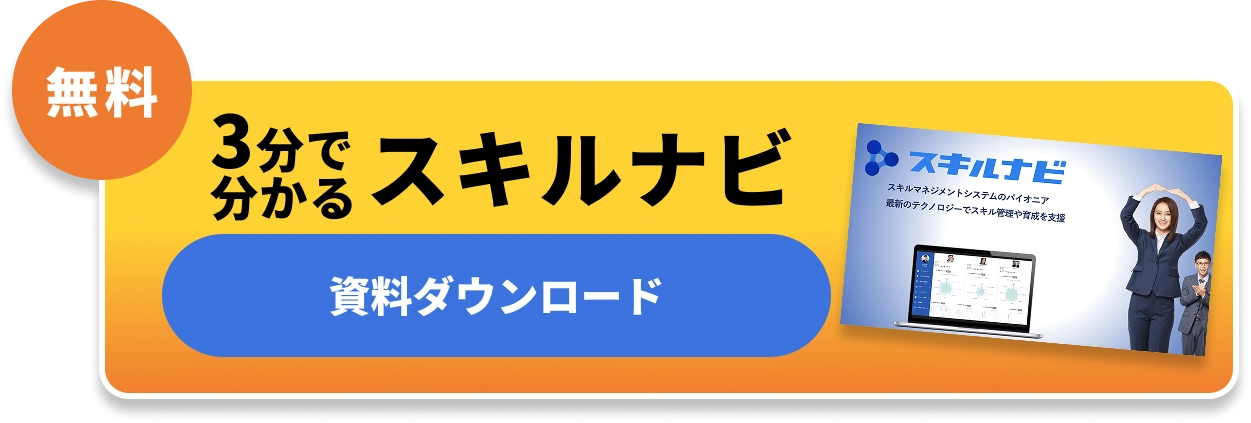人材管理システムとは?メリット・比較方法・導入事例を解説

人材管理システムは、従業員の情報やスキル、評価データを一元的に管理し、採用・育成・配置・評価などの人事業務を効率化するツールです。
近年は人的資本経営や多様な働き方への対応が求められる中で、導入する企業が急速に増えています。
しかし「どんな機能があるのか?」「導入すると何が変わるのか?」「どう選べばいいのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、人材管理システムの概要から導入メリット、比較ポイント、事例までをわかりやすく解説します。
人材管理システムとは
人材管理システムとは、従業員の基本情報・スキル・評価履歴などをデータベースで一元管理し、採用から育成・配置・評価までの人事業務を効率化する仕組みです。
従来は紙やエクセルで分散管理されていた情報を統合することで、人材の見える化や配置最適化を実現し、戦略的人材活用や人的資本経営の推進に役立ちます。
人材管理システムって種類があるの?
近年、リモートワークやジョブ型雇用の普及、さらに人的資本経営への注目の高まりにより、人材管理システムに求められる機能は一層高度化・多様化しています。
基本情報や勤怠の管理に加え、スキル可視化・育成支援・人事評価・タレントマネジメントなど、目的に応じたさまざまな種類が登場しており、自社課題に合った選定が重要です。
人事労務管理
勤怠や給与、社会保険手続きなどの人事労務管理を効率化する機能で、リモート対応の電子申請やペーパーレス化が標準化しています。
採用管理
求人情報の管理から候補者データの一元化まで対応し、採用スピード向上を目的にオンライン面接との連携も進んでいます。
タレントマネジメント
従業員一人ひとりのスキルやキャリア志向を把握し、最適な配置や育成計画を行うタレントマネジメント機能は、近年ますます重要性を増しています。
特に、人的資本開示への対応や、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン(DEI)といった観点を踏まえた戦略的人材活用が求められています。これにより、企業は持続的な成長と従業員のエンゲージメント向上を同時に実現できます。
人事評価管理(目標管理)
従業員の業績や能力、目標達成度を定量的に評価できる機能を備え、公平で透明性の高い評価運用を支援します。
人材管理システムを導入するメリット
人材管理システムを導入することで、人事情報の一元化による業務効率化だけでなく、スキルや評価データを活用した戦略的人材活用が可能になります。
従業員の育成計画や配置の最適化、人的資本開示への対応など、多角的なメリットが得られる点から、近年あらゆる業界で導入が進んでいます。
生産性を向上させる
多岐にわたる人事業務をシステム化することで、ヒューマンエラーを防止し、従業員の作業コスト削減と生産性向上を実現します。
従業員のエンゲージメントを向上させる
人材管理システムでは、従業員の実績や評価をデータとして蓄積・可視化できるため、能力や適性を客観的に把握しやすくなります。
その結果、公平で正しい評価やマネジメントが可能となり、従業員の納得感を高められます。評価やキャリア形成に対する信頼性が向上することで、従業員のモチベーションやエンゲージメントの強化につながり、定着率向上にも効果を発揮します。
人材管理システムを導入するデメリット
人材管理システムには多くの利点がありますが、一方で導入・運用には注意点も存在します。
初期コストや運用体制の構築に負担がかかるほか、自社に合わないシステムを選んでしまうと現場に定着せず、効果が限定的になることもあります。
導入を検討する際には、デメリットを正しく理解したうえで対策を講じることが重要です。
導入・運用にコストがかかる
人材管理システムを導入する際には、初期費用やライセンス費用に加え、運用に伴う保守費用やサポート費用も発生します。
そのため、システムの規模や提供形態によっては想定以上のコストがかかる場合もあります。
導入目的や解決したい課題を明確にし、予算とのバランスを踏まえて費用対効果を検証することが欠かせません。短期的なコストだけでなく、中長期的な投資効果を見極めて判断することが重要です。
定着・中止リスクがある
せっかくコストをかけて人材管理システムを導入しても、現場に定着せず運用が形骸化してしまうケースは少なくありません。
ベンダーとの相性が合わずサポートが不十分な場合や、導入目的が不明確なまま進めてしまうと、中止に追い込まれるリスクもあります。
こうした失敗を防ぐためには、経営・人事の目的に沿った運用設計を行い、現場が「使い続けたい」と思える工夫を組み込むことが重要です。
人材管理システムの導入前にすべきこと
人材管理システムは便利な一方で、準備不足のまま導入すると「思ったように活用できない」「現場に浸透しない」といった失敗につながりかねません。
だからこそ、導入前に自社の課題を整理し、必要な機能や運用体制を明確にしておくことが大切です。
本章では、検討段階で押さえるべきポイントを整理し、次のステップをスムーズに進められるよう解説します。
導入目的を設定する
人材管理システムを有効活用するためには、まず「従業員情報を一元管理したい」「採用プロセスを効率化したい」といった導入目的を明確にすることが重要です。
目的が曖昧なまま導入すると、現場で使いこなせずに形骸化してしまうリスクがあります。
システムで実現したい業務改善や期待する成果を具体化することで、ベンダー選定や運用設計の精度が高まり、定着率向上にもつながります。
導入時期を決定する
導入は現場の混乱や定着失敗を防ぐため、人事業務の繁忙期を避け、余裕を持って移行できる時期に行うのが望ましいです。
どの業務に適用するか考える
人材管理システムは機能が幅広いため、まず自社の人事業務のどの部分をシステム化するのかを明確にすることが重要です。
例えば、従業員データの一元管理を中心に進めるのか、採用・評価・育成まで含めて統合的に運用するのかによって、必要となるシステムの種類や機能は大きく変わります。
適用範囲を決めておくことで、導入効果を最大化しやすくなり、現場の混乱も防ぐことができます。
運用ルールを設定する
人材管理システムを定着させるためには、導入前に運用ルールを明確に決めておくことが欠かせません。
例えば「運用管理者は誰か」「管理者にどの程度の権限を持たせるか」といった基本設計を事前に整えておくことで、権限の不明確さや運用トラブルを防げます。
また、利用者が迷わず活用できる環境を整えることで現場の定着率も高まり、システム投資の効果を最大化できます。
ステイクホルダーの合意を得る
導入にあたっては人事部門だけでなく経営層や現場の合意形成が必要です。個人情報を扱うため、GDPRなど法規制も意識しましょう。
人材管理システムの比較ポイント
数多くの人材管理システムがある中で、自社に最適なものを選ぶには比較の視点を持つことが不可欠です。
価格や機能だけでなく、UI/UXの使いやすさ、セキュリティ体制、導入支援の有無なども判断基準になります。
本章では、導入後に失敗しないための主な比較ポイントを整理し、選定プロセスをスムーズに進められるよう解説します。
提供形態
人材管理システムには大きく分けてクラウド型、パッケージ型、オンプレミス型があります。
クラウド型は初期コストが低く、常に最新機能を利用できる一方、自社要件に完全適合させにくい面があります。
パッケージ型は一定の標準機能を持ち、導入のしやすさが特長ですが柔軟性は限定的です。オンプレミス型はカスタマイズ性やセキュリティに優れる一方で、導入・運用コストが高くなる点に注意が必要です。
使いやすさ
人材管理システムは多くの従業員が日常的に利用するため、誰にとっても操作が簡単で直感的に使えることが重要です。
操作が複雑だと現場での定着率が下がり、結果的に導入効果を得られなくなるリスクがあります。
そのため、導入前にデモ環境や無料トライアルを活用し、実際の操作感や画面の見やすさを確認しておくことが望ましいでしょう。
システムの柔軟性
人材管理システムを導入する際は、自社ですでに利用している勤怠管理や給与システム、基幹システムなどとデータ連携が可能かどうかを確認することが欠かせません。
APIの有無や外部ツールとの連携性が低いと、結局は手作業が残り、効率化効果が薄れてしまいます。
柔軟な連携が可能なシステムを選ぶことで、全社的なデータ活用や業務効率の最大化につながります。
セキュリティ対策
人材管理システムでは、従業員の個人情報や評価データなど機密性の高い情報を扱うため、セキュリティ対策の水準を確認することが不可欠です。
データ暗号化、アクセス権限の設定、ログ管理といった基本機能に加え、ISOやISMSなどの外部認証を取得しているかも安心材料となります。
万が一の情報漏洩は企業の信頼を大きく損なうため、導入前にセキュリティ体制を必ずチェックしましょう。
カスタマイズの汎用性
人材管理システムは自社の要件に応じてカスタマイズできる柔軟性を備えている場合があります。
ただし、過度なカスタマイズはコスト増や運用負担の増大につながる可能性があるため注意が必要です。標準機能でどこまで対応できるかを確認したうえで、本当に必要な部分だけをカスタマイズすることで、コストを抑えつつ長期的に使いやすいシステム運用が実現できます。
価格
人材管理システムの価格は、導入形態や利用人数、搭載機能によって大きく変動します。
クラウド型であれば月額課金制が一般的で、初期費用を抑えつつ利用できる一方、オンプレミス型は導入コストが高額になりやすい特徴があります。
また、ユーザー数や利用範囲が広がるにつれて追加費用が発生するケースもあるため、料金体系を事前に確認し、自社の予算や成長計画に合わせた選定が重要です。
サポート体制
人材管理システムを効果的に活用するには、導入後のサポート体制も重要です。
初期設定やデータ移行の支援、操作トレーニング、定期的なアップデート対応などが整っているかを確認しましょう。
サポートが不十分だと現場に浸透せず、導入効果が限定的になるリスクがあります。専用窓口やチャット対応など、問い合わせ手段や対応スピードも含めて比較検討することが大切です。
導入の負担
人材管理システムは多機能である分、導入初期にはデータ移行や既存業務フローの見直し、従業員への操作教育など一定の負担が発生します。
特に利用部門が多い企業では、関係者の調整やマニュアル整備に時間を要することもあります。
こうした負担を軽減するためには、段階的な導入やパイロット運用を行い、現場の声を反映しながら浸透させる工夫が効果的です。
人材管理システムの導入事例
日産トレーデイングオペレーションジャパン様
日産トレーディングオペレーションジャパン様は、当社スキルナビを導入したことで、多くの人事評価業務を削減されました。
当企業様の事例について紹介しています。是非ご覧ください。
ソフテム様
ソフテム社では、エクセルによる評価シート管理に課題を感じ、スキルナビを導入されています。
ワークフロー機能により能動的なスキルチェック環境を構築し、評価基準の統一やスキルの見える化を実現しました。
キャリアモデル機能を活用することで、会社の求めるスキルと社員の保有スキルのミスマッチを解消し、面談や教育施策にも活かされています。
三井住友信託銀行様
三井住友信託銀行様では、数千名の社員を対象としたスキルチェックをExcelで集計・分析していましたが、工数や分析精度に限界を感じていました。
スキルナビを導入したことで、属性に応じた柔軟な設問設定や回答負担の軽減が可能となり、スキルデータを効率的に可視化。
各支店や部署ごとの強み・弱みを客観的に把握できるようになり、高度な分析や育成施策への活用が進んでいます。
自社の課題に合う人材管理システムを導入しよう
人材管理システムは、人事業務の効率化だけでなく、従業員の育成や適材適所の配置、人的資本経営の実現に大きく貢献します。
ただし、導入効果を最大化するためには、自社の課題や目的を明確にし、それに合ったシステムを選定することが欠かせません。
その点、スキルナビはスキルの可視化や育成計画の設計に強みを持ち、現場で使いやすい設計と柔軟な運用が可能です。自社の人材戦略を支える基盤として、ぜひ導入をご検討ください。