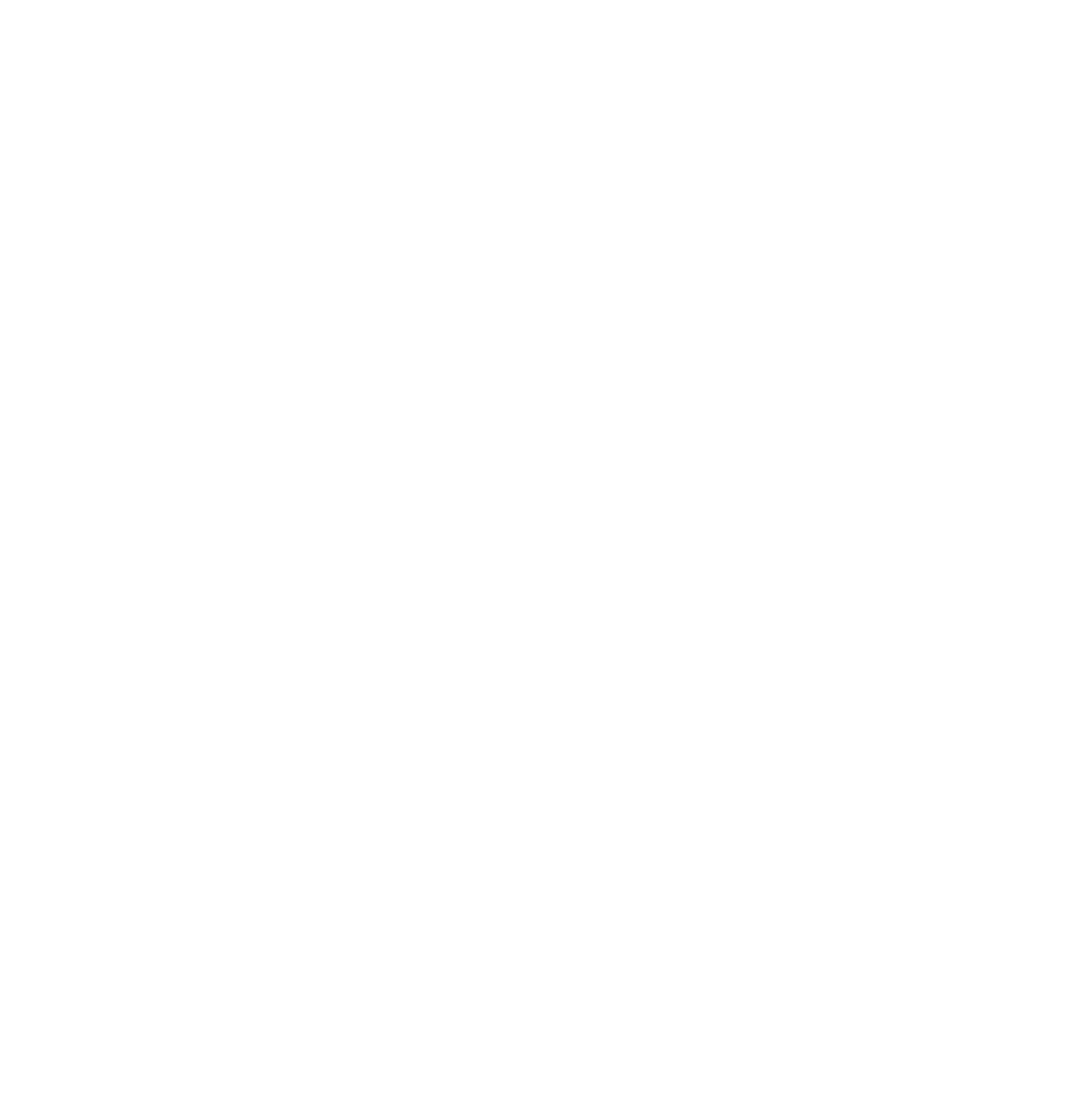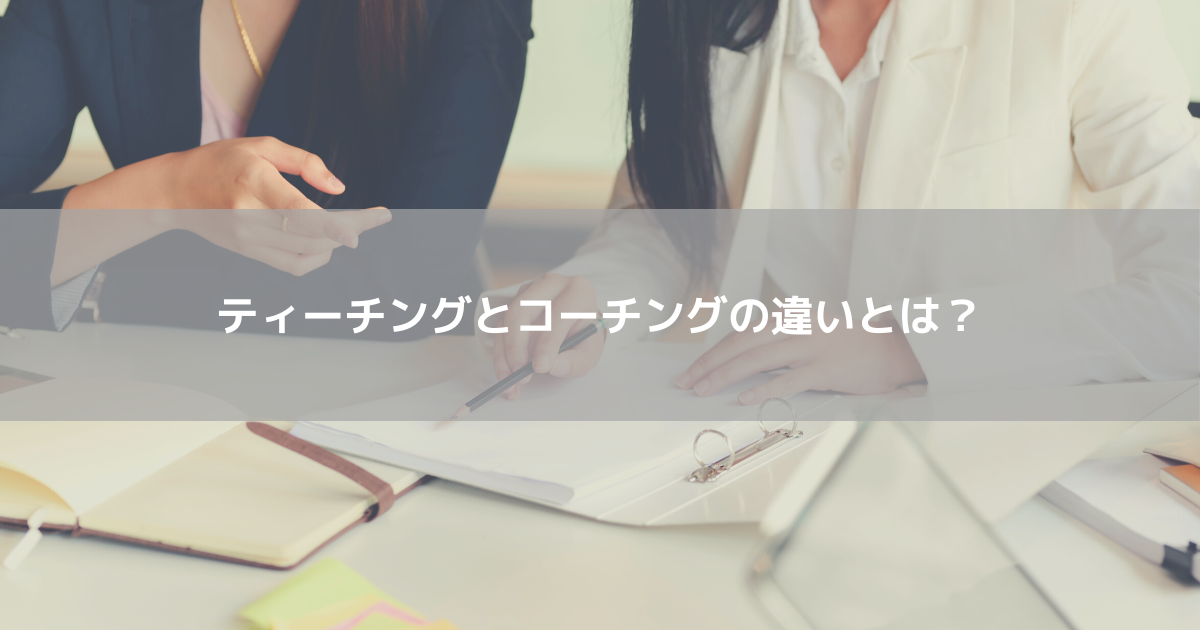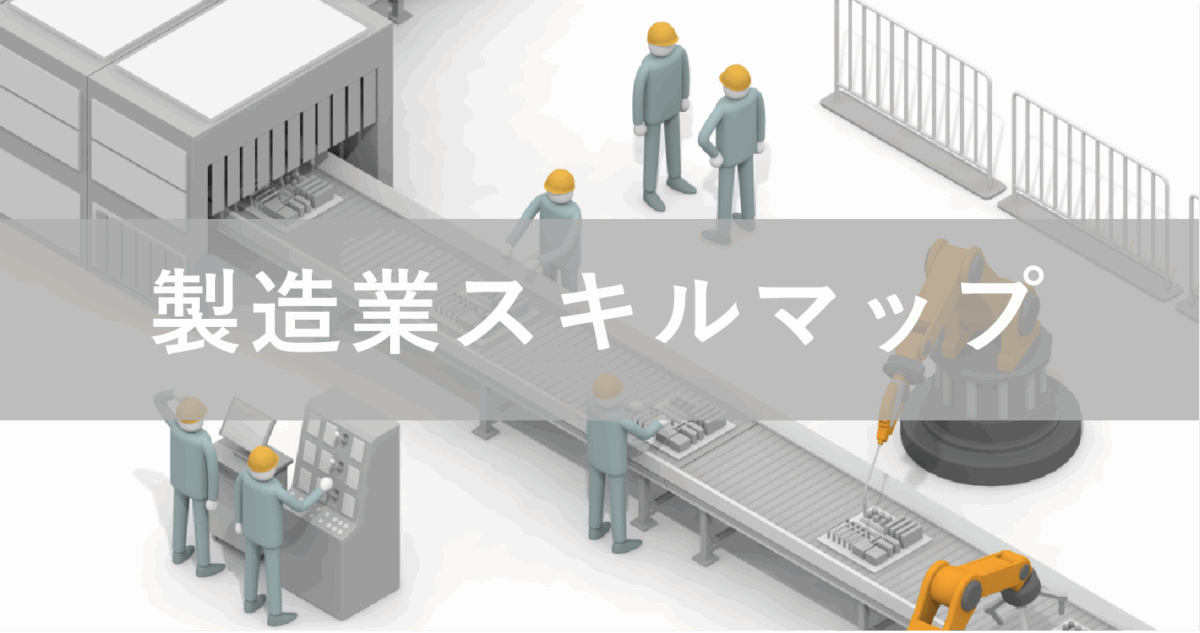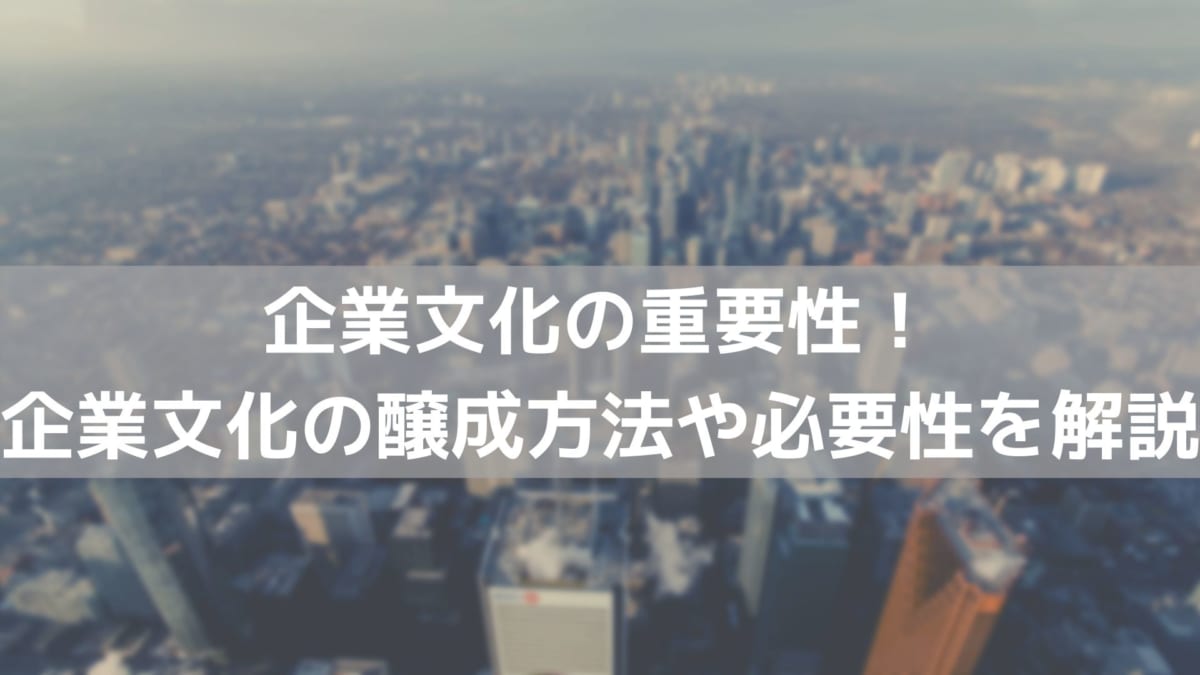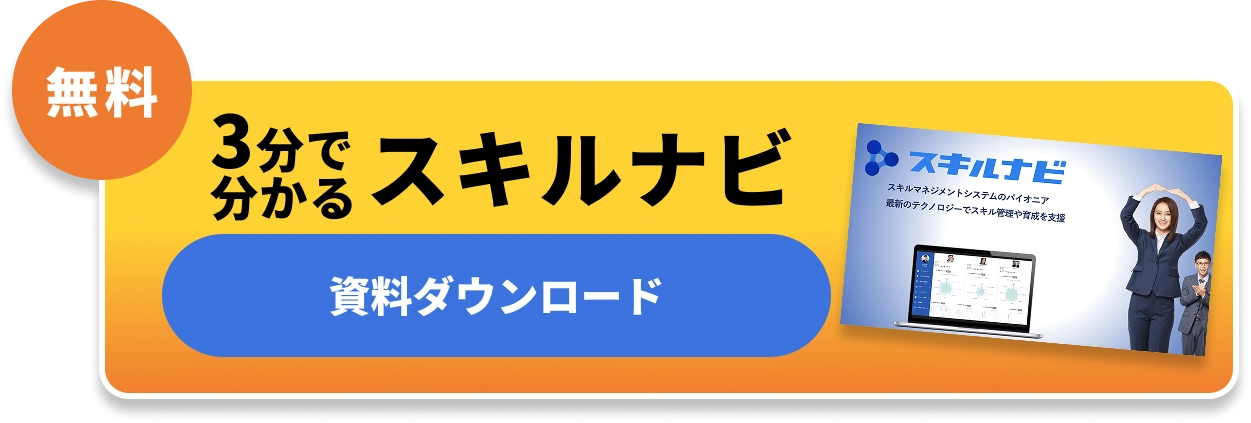ジョブローテーションとは?目的やメリット、事例もあわせて解説
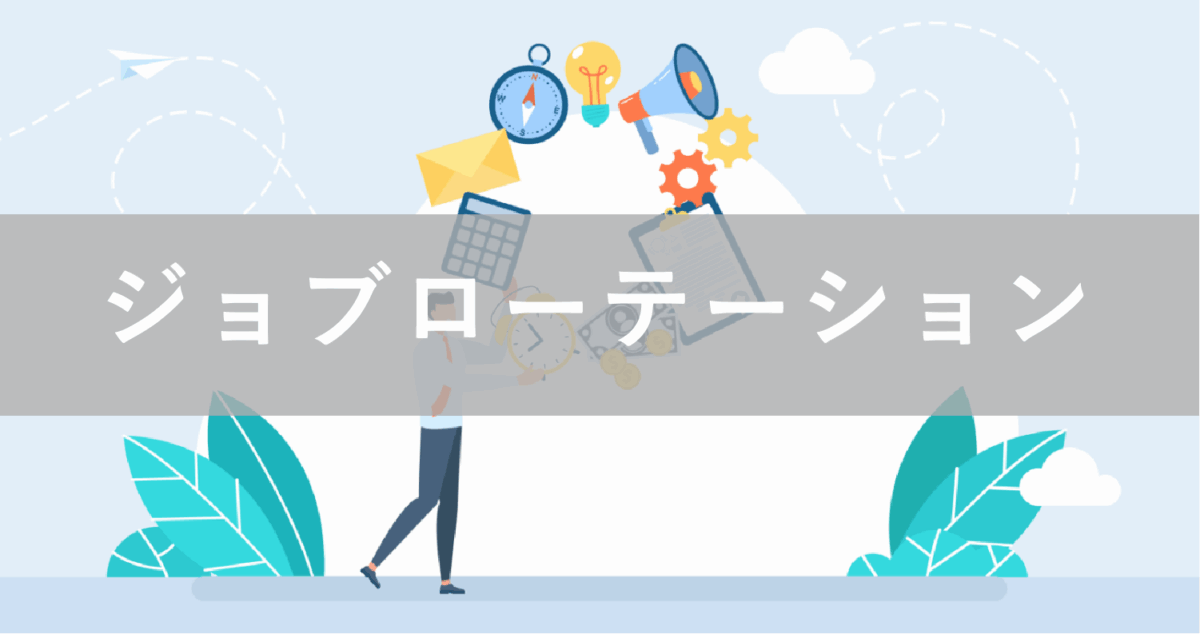
ジョブローテーションは、従業員が複数の部署や職種を経験することで、幅広いスキルや知識を身につける人材育成の手法です。
これにより、社員の適性を見極めやすくなり、組織全体の連携や活性化も促進されます。
本コラムでは、ジョブローテーションの目的やメリット、事例を交えながら、その効果的な活用方法について詳しく解説します。
ジョブローテーションとは
ジョブローテーションとは、定期的に従業員の職場や職種を配置転換をおこなうことであり、「戦略的人事異動」や「計画的人事異動」とも呼ばれます。
特定業務に偏らず多様な経験を積むことで、幅広い知識やスキルを習得でき、組織全体の業務理解や柔軟な対応力が向上します。
また、適性発見やキャリア形成の促進にもつながり、企業にとっても多能な人材の育成や人員配置の最適化に効果的です。
ジョブローテーションと他制度との違いとは
ジョブローテーションには、混同されがちな制度が複数あります。
本項目ではそれぞれとの違いを解説します。
人事異動制度との違い
人事異動とは、欠員の補充や組織の活性化などを目的として、経営戦略上の必要性から検討される出向・昇降格・解雇などを含む配置転換のことを指します。
一方で、ジョブローテーションは、人事戦略に基づき、人材育成や社内交流の促進を目的としておこなわれる配置転換のことを指します。
目的や実施の背景が異なる点が大きな違いといえるでしょう。
社内公募制度との違い
社内公募制度とは、人材が必要になった部署が社内募集をおこない、希望する社員が自主的に応募して異動をおこなう仕組みです。
これに対し、ジョブローテーションでは企業側が人材育成や組織活性化を目的に計画的に従業員を選び、配置転換をおこなうという違いがあります。
異動を実施する主体が、社員か企業かという点が大きな違いといえるでしょう。
ジョブチェンジとの違い
ジョブチェンジは、職種を変え、新たなスキルや知識を身につけて能力開発をおこなうことを指し、その中には転職も含まれます。
一方、ジョブローテーションは、社内での部署や職務の異動に限るものであり、社内人材の育成や経験の幅を広げることを目的とします。
ジョブチェンジとジョブローテーションには、その範囲と目的に明確な違いがあります。
ジョブローテーションを行う目的
ジョブローテーションを行う目的もさまざまなものがあります。
本項目では主な3つの目的について解説します。
幅広い自社業務への理解
ジョブローテーションでは、営業、企画、製造、管理部門など、さまざまな部署や業務を経験することで、企業全体の流れや各部門の役割を深く理解できます。
そうすることで、組織内での情報共有やコミュニケーションが円滑になり、業務効率や生産性の向上が期待できます。
このように、幅広い自社の業務への理解を深めることは、ジョブローテーションの目的のひとつです。
長期的な人材育成
ジョブローテーションをおこなうことで、配属先ごとの業務への適応力や、そこで出会うさまざまな従業員との関係構築力を向上することが期待できます。
異なる業務経験を積むことで、視野が広がり、課題解決力や判断力、調整力など、将来のリーダーとして必要とされる総合的な能力を育むことができます。
これにより、組織の長期的な人材基盤の強化にもつながります。
組織リスクの分散と属人化防止
ジョブローテーションをおこなうことで、特定の従業員にしか業務対応ができないという、依存によるリスクを防ぐことができます。
複数の従業員が同じ業務を理解・遂行できる体制を整えることで、休職者や退職者などが発生した場合も、他の従業員が業務を引き継ぎ、滞りなく対応し補うことができます。
これにより、属人化を防止し、業務が停滞するリスクを減らすことができます。
ジョブローテーションを行う際のメリット
ジョブローテーションにはさまざまなメリットがあります。
本項目ではジョブローテーションをおこなうメリットについて解説します。
適材適所の配置ができる
ジョブローテーションをおこない、さまざまな業務を経験することで、従業員の業務遂行における強みや課題、得意分野などの適性を見極めることができます。
その結果、本人の能力や志向などの適正によりマッチした職務への配属が可能となります。
そうすることで、従業員のモチベーションやパフォーマンスの向上が期待できるでしょう。
幹部候補の適正確認や育成ができる
ジョブローテーションによって異なる業務スキルや知識を習得することで、従業員は幅広い業務経験を積むことができます。
これにより、将来的に幅広いキャリアパスを選択できるようになり、管理職や経営層への選択肢まで可能性が拡がります。
企業にとっても、各従業員の幹部候補としての適正を確認し育成できることは大きなメリットといえるでしょう。
社内の活性化が期待できる
ジョブローテーションを通じて複数の部署を体験することにより、従業員は部署を超えた幅広い人的ネットワークを築くことができます。
これにより、社内や部署間でのコミュニケーションが円滑になり、情報共有や連携がスムーズに進みやすくなります。
結果として、社内の風通しが良くなり、組織全体の活性化が期待できるでしょう。
モチベーションの向上が期待できる
長く同じ業務に携わっていると、業務に対しての物足りなさや意欲の低下が起こりやすくなります。
ジョブローテーションをおこなうことで、従業員は別の業務や環境に触れ、新たな刺激や学びを得られます。
結果として、社員のモチベーションが向上され、業務への積極的な取り組みを促すことが期待できるでしょう。
採用コストの削減ができる
近年、外部からの優秀な人材確保が難しくなっているため、自社内での人材育成と定着の重要性が高まっています。
ジョブローテーションは、多様な業務経験を通じて社員のスキルや適性を引き出し、優秀な人材を社内で育てる効果的な手法です。
また、適切な職務配置により社員の満足度や定着率を高める効果も期待できるため、採用活動にかかるコストや時間の削減にもつながるでしょう。
柔軟かつ持続可能な運営体制ができる
ジョブローテーションにより従業員がさまざまな部署や業務を経験することで、多様なスキルや知識を持つ人材を育成できます。
これにより、人手不足などが発生した場合にも、迅速かつ柔軟に対応できる人材を確保することができます。
結果として、業務を円滑にまわし、柔軟かつ持続可能な組織運営をおこなうことができる体制をつくることができるでしょう。
ジョブローテーションを行う際のデメリット
ジョブローテーションにはさまざまなメリットがある一方で、デメリットにも注意が必要です。
本項目ではジョブローテーションを行う際のデメリットを解説します。
スペシャリストの育成には向いていない
ジョブローテーションは、半年や数年といった期間で職場や職種を異動するため、短期間で業務の深い部分までを理解することはほぼできません。
そのため、高度な技術や専門知識が求められるスペシャリスト育成には不向きであることに注意が必要です。
ジョブローテーションは幅広い経験や汎用的なスキル習得には効果的である一方、このようなデメリットがある点は認識しておきましょう。
コストや時間がかかる
ジョブローテーションをおこなう際には、新しい業務を習得してもらうために教育や研修、サポートが必要となり、これらには一定のコストと時間がかかってしまいます。
特にジョブローテーションを行った後、業務を覚えるまでの間は、一時的に生産性が低下することも避けられません。
こうしたデメリットを考慮したうえで、十分な準備・検討をおこなうこととフォロー体制を整えることが重要になるでしょう。
早期離職のリスクがある
望まないジョブローテーションがおこなわれると、社員の意欲低下や不満が生じ、早期離職となってしまうリスクがあります。
本人の志向や適性を考慮せずにジョブローテーションをおこなうと、モチベーションやエンゲージメントが下がってしまうことも少なくありません。
そのため、ジョブローテーションをおこなう際は、その目的や意味、本人への期待を丁寧に説明し、社員の理解と納得を得ることが重要です。
ジョブローテーションが向いている企業
ジョブローテーションには向いている企業と向いていない企業があります。
本項目では向いている企業の例を紹介します。
新卒一括採用を実施している企業
新卒一括採用を実施している企業では、社会人経験のない人材を一括で採用するため、入社時点で個々の適性を判断することができません。
このような場合、ジョブローテーションをおこない、複数の部署や業務の経験を重ねることで、従業員自身が自分の適正に合った業務を理解することができるようになります。
企業側としても従業員の適性や能力を見極め、最適な配置や育成が可能になるでしょう。
総合職・ゼネラリスト志向の人材が多い企業
総合職の従業員が多く、将来的に管理職やリーダーとしての役割を期待している企業においては、ジョブローテーションが非常に効果的です。
幅広い部署や業務を経験することで、社員は会社の全体像を把握し、総合的な視野を養うことができます。
このような経験は、管理職に不可欠であり、総合職・ゼネラリスト志向の人材が多い企業において、ジョブローテーションは人材育成に適した手法と言えます。
業務・部門の幅が広く、連携が必要な企業
部署数が多く、部門間の連携が重要な大企業では、社内コミュニケーションがとりにくくなる傾向があります。
こうした企業においては、ジョブローテーションを実施することで、従業員が、複数の部署を経験し社内に幅広い人脈をつくることができるようになります。
その結果、異なる部署間でのコミュニケーションが活発になり、組織全体の連携力が向上が期待できるでしょう。
ジョブローテーションが向いていない企業
本項目ではジョブローテーションが向いていない企業の例を解説します。
高度な専門性が求められる企業
高度な専門性が求められる企業では、専門的な知識や技術が不可欠です。
その場合、ジョブローテーションをおこなってしまうと、必要となる専門的な経験を十分に得ることが難しくなり、必要な知識や技術を習得することができなくなってしまいます。
結果として、人材育成の効率が低下し、コストが増大してしまうため、こうした企業ではジョブローテーションはあまり適していません。
少人数な企業(スタートアップ・ベンチャー)
少人数で運営されるスタートアップやベンチャー企業では、社員一人ひとりが複数の重要な業務を担当していることが多く、ジョブローテーションをおこなうと業務が立ち行かなくなってしまい、業務が滞ったり、効率が低下したりする場合があります。
こうした環境では、ジョブローテーションによるメリットよりもデメリットのほうが大きくなってしまうため、ジョブローテーションはがあまり向いていないといえるでしょう。
中長期的な業務を中心とした企業
中長期的な業務が多い企業では、ジョブローテーションによりプロジェクトの途中で担当者が変わってしまうと、業務の引継ぎが不十分になるリスクが高まります。
これにより、業務の引継ぎミスが発生し、プロジェクトの遅延や品質低下につながる可能性があります。
このようなリスクがあるため、中長期的な業務が多い企業ではジョブローテーションはあまり適していないといえます。
新卒採用が少なく中途採用が多い企業
中途採用が多い企業では、採用された社員がすでに必要なスキルや経験を取得している場合も多くあります。
こうした場合、本人のスキルや経験を知らずにジョブローテーションを無理におこなうと、必要のない教育コストや時間が発生し、組織全体の生産性を低下させる可能性があります。
そのため、中途採用者が多い企業では、ジョブローテーションはあまり向いていないといえるでしょう。
ジョブローテーションを成功させる方法
ジョブローテーションを成功させるためにはどのようにすればよいのでしょうか。
本項目では3つのポイントを解説します。
明確な目標設定を行う
ジョブローテーションを成功させるためには、まず目標や取り組みの目的を明確にすることが重要です。
事前に計画を立て、人員の配置や期間を具体的に決めておくことで、社員が何を達成すべきか理解しやすくなり、効果的にジョブローテーションを進めることができます。
計画的な運用により業務の混乱を防ぎ、効果的なスキル習得や適性の見極めが可能となるため、明確な目標設定は重要なポイントといえるでしょう。
情報の蓄積・管理を行う
ジョブローテーションをおこなうと、従業員のスキルや人事情報を得ることができます。
これらの情報を人事戦略に有効活用するために、社内に散在しないよう、一元的に蓄積・管理する仕組みを整えることが重要です。
適切に情報管理をすることで、個々の能力や適性を正確に把握でき、人事配置や育成計画に役立つため、ジョブローテーションの効果を最大化することができるでしょう。
従業員への説明・理解を得る
一方的なジョブローテーションを実施すると、従業員のモチベーションが低下して離職につながるおそれがあります。
そのため、事前に目的の説明をおこなうとともに、本人の意思や適性を十分に確認して理解を得ることが不可欠です。
また、ジョブローテーション後には必ず定期的にフィードバックを行い、適切な評価を通じて成長を支援することが重要です。
これにより、従業員の納得感や意欲を維持し、ジョブローテーションの効果を最大限に引き出すことができます。
人材育成のために正しいジョブローテーションを行おう
ジョブローテーションを成功させるには、企業側の考えのみではなく、従業員の意見や適性も尊重することが不可欠です。
双方の理解と協力を得ながら計画的に進めることで、ジョブローテーションの成果を出すことができ、効果的な人材育成が実現します。
従業員のモチベーション維持や育成、組織の活性化につなげるためにも、正しいジョブローテーションをおこないましょう。