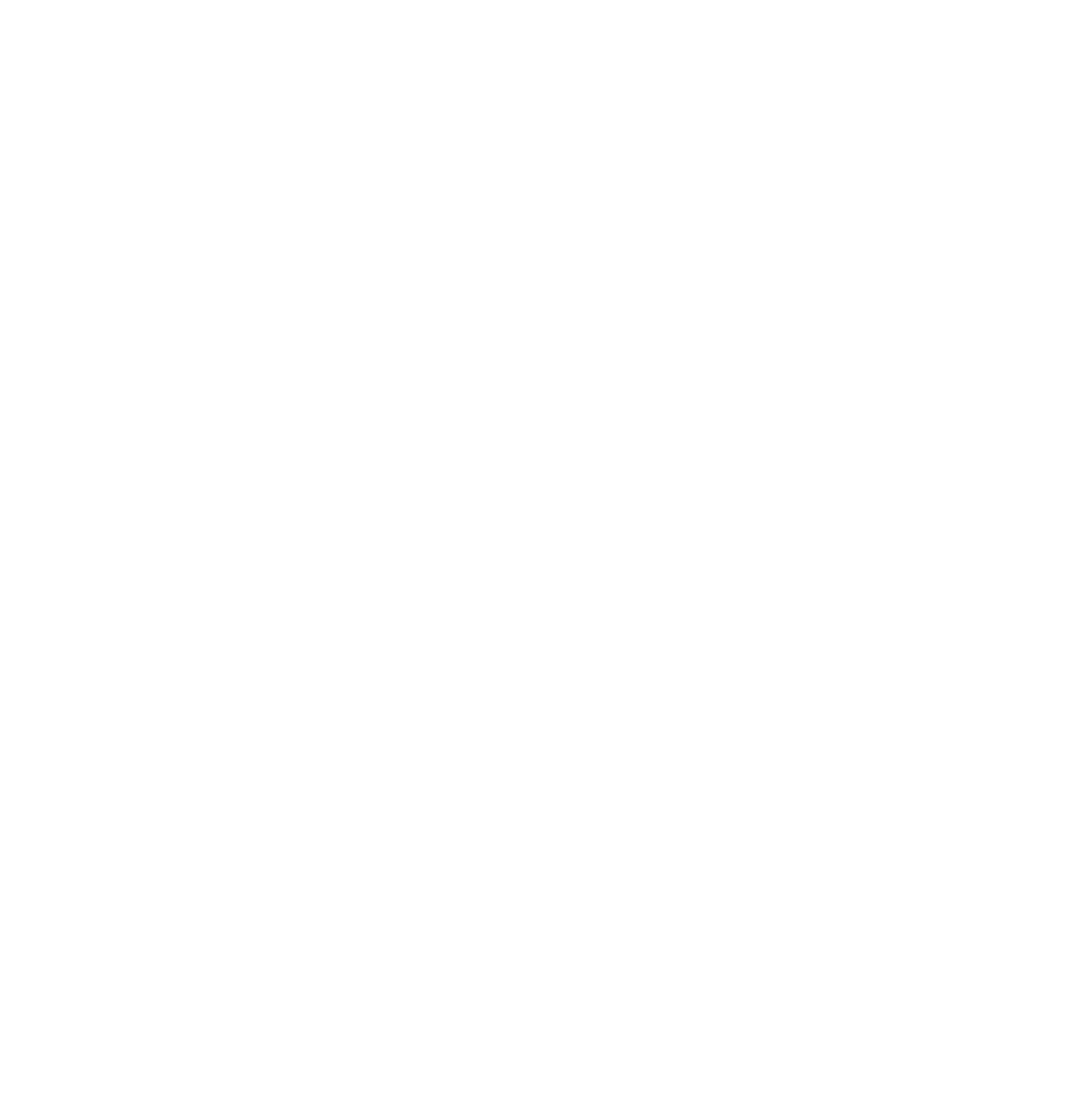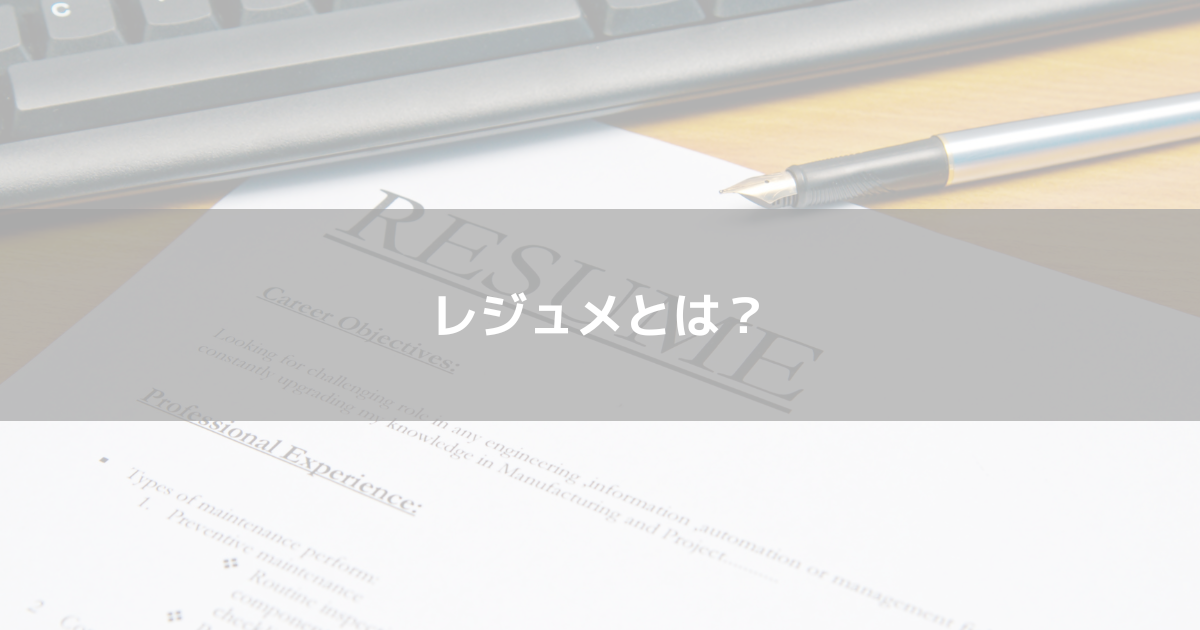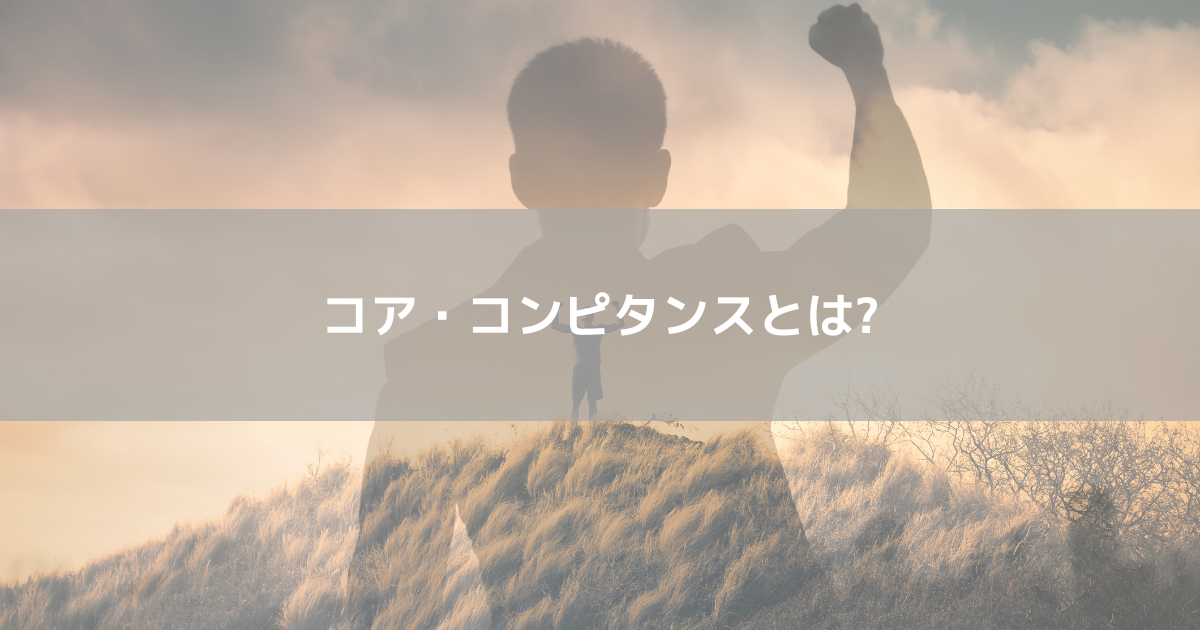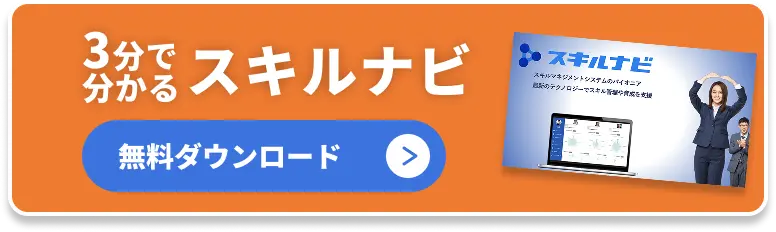OKRとは?仕組みやMBO・KPIとの違い|運用プロセスや注意点、事例などを解説

OKR(Objectives and Key Results:目標と主要な成果指標)とは、組織や個人が達成したい目標(Objective)を明確にし、それを実現するための具体的な成果指標(Key Results)を設定するフレームワークです。
MBO(目標管理制度)が「評価や人事制度と連動する仕組み」であるのに対し、OKRはチャレンジングな目標を共有し、チーム全体の成長や挑戦を促すことを目的としています。
短期間での振り返りを重ねながら柔軟に調整する点や、KPIよりも戦略的・意欲的な目標設定が特徴です。
ここでは、OKRの基本的な仕組みと、MBO・KPIとの違い、運用プロセスや事例について解説します。
OKRとは
OKR(Objectives and Key Results:目標と主要な成果指標)とは、組織や個人が挑戦的な目標を掲げ、その達成度を測るための具体的な成果指標を設定する手法です。
目標(Objective)は「何を達成したいか」、成果指標(Key Results)は「どのように測定するか」を示し、短期間で進捗を確認しながら柔軟に調整していくのが特徴です。
Googleをはじめとした先進企業で採用されており、チームの方向性を揃えながら高い目標への挑戦と学習サイクルを生み出す仕組みとして注目されています。
OKRが注目される背景とその理由
近年、OKR(Objectives and Key Results)は、従業員の主体性を引き出し、組織の方向性を統一する仕組みとして注目を集めています。
その背景には、GoogleやIntelなどの先進企業による成功事例があることに加え、チーム間で目標を共有し、従業員のエンゲージメント向上を実現できる点が挙げられます。
さらに、急速に変化するビジネス環境においても、短期サイクルで柔軟に目標を見直せるOKRは、高い適応力を持つ仕組みとして評価されています。
ここでは、OKRが注目される主な3つの理由を解説します。
OKRの基本と仕組み
OKR(Objectives and Key Results)は、挑戦的な目標(Objective)と、それを達成するための主要な成果指標(Key Results)で構成される目標管理のフレームワークです。
「何を達成したいのか(目的)」と「どうなれば達成といえるのか(成果基準)」を明確にすることで、組織全体が同じ方向を向きながら成果を高められる点が特徴です。
また、短期間で進捗を確認し、柔軟に見直す仕組みを持つため、変化の早いビジネス環境にも適応しやすいというメリットがあります。
ここでは、OKRの基本構造と仕組みについて解説します。
目標(Objective)
Objective(目標)は、組織やチーム、個人が「何を達成したいのか」を明確に示すものです。
OKRにおけるObjectiveは、単なる業務目標ではなく、メンバーの意欲を高め、挑戦を促す“方向性”を示す役割を持ちます。
たとえば、「顧客満足度を業界トップクラスに引き上げる」「新製品を通じて市場をリードする」といったように、定性的かつ前向きな表現で設定するのが特徴です。
短期間で見直しながら、組織のビジョンや戦略と結びついた目標を立てることが、OKRの成果を最大化する鍵となります。
主要な結果(Key Results)
Key Results(主要な結果)は、設定したObjective(目標)をどの程度達成できたかを測定するための具体的な指標です。
「何をもって成功とするか」を明確に定義することで、進捗を数値や具体的成果として可視化できます。
たとえば「顧客満足度を90%に引き上げる」「新規リード数を30%増加させる」といったように、定量的・具体的に設定するのが特徴です。
Key Resultsは1つのObjectiveにつき3〜5項目程度に絞り、定期的に進捗を確認・見直すことで、目標達成に向けた方向性を保ちやすくなります。
スコアリング
スコアリングとは、設定したOKRの達成度を定期的に数値化し、振り返りを行う仕組みです。
多くの企業では、Key Resultsの進捗を0.0〜1.0(または0〜100%)のスコアで評価し、0.6〜0.7程度の達成を「適切な挑戦」として良しとします。
この仕組みは、成果を「達成/未達」で判断するのではなく、どこまで到達し、何を学んだのかを振り返ることを目的としています。
スコアリングを通じて目標設定の精度を高め、次のOKRに活かすことで、継続的な成長サイクルが生まれます。
他の目標管理手法との違い
OKRはMBOやKPIなどの他の目標管理手法と異なり、挑戦的な目標設定と短期間での振り返りを重視します。ここでは、それぞれの違いを整理します。
MBOとの違い
MBO(目標管理制度)は、主に人事評価や報酬と連動する仕組みとして運用されるのに対し、OKRは挑戦的な目標設定を通じて成長を促すことを目的としています。
MBOでは年次や半期ごとの評価サイクルが一般的ですが、OKRは四半期などの短期間でレビューを行い、柔軟に見直すのが特徴です。
また、MBOが個人単位の目標管理に重きを置くのに対し、OKRはチーム全体で目標を共有し、透明性を高める運用を重視します。
評価主軸のMBOに対し、OKRは学習と挑戦を支援するフレームワークといえます。
KPI・KGIとの違い
KPI(重要業績評価指標)やKGI(重要目標達成指標)は、「何をどれだけ達成したか」を数値で管理する手法です。
一方でOKRは、「なぜその目標を追うのか」「どこに向かって進むのか」という目的や方向性を重視します。
KPI・KGIが成果の進捗を測定する“結果の指標”であるのに対し、OKRはその目標を実現するための“行動の道しるべ”として機能します。
つまりOKRは、KPIやKGIを補完し、組織全体で目標を共有・連動させるためのマネジメント手法といえます。
ノーレーティングとの違い
ノーレーティング制度は、数値による評価やランク付けを行わず、成長のための対話を重視する制度です。
従業員の学びや成長を支援する点でOKRと近い思想を持ちますが、OKRは目標と成果指標を設定し、定期的に進捗を可視化・共有する仕組みである点が異なります。
ノーレーティングは評価を完全に排除しますが、OKRはあくまで目標達成の過程を振り返り、次の行動を導くマネジメント手法です。
また、他の評価制度と併用する場合は、OKRを評価目的に転用しないよう運用設計を分けることが重要です。
その他の目標管理手法
目標管理の手法はOKRやMBOだけでなく、組織の目的や文化に応じてさまざまな方法があります。
たとえば、コンピテンシー評価は成果だけでなく、業務遂行に必要な行動特性やスキルを評価する手法です。
また、360度評価は上司だけでなく、同僚や部下、他部署など複数の視点から評価を行う仕組みで、より客観的なフィードバックを得ることができます。
これらの制度は、単独で運用するほか、OKRやMBOと組み合わせて導入することで多面的な成長支援が可能になります。
OKRを導入するメリット
OKR(Objectives and Key Results)は、単なる目標管理手法ではなく、組織全体の方向性をそろえ、挑戦を促すマネジメントフレームワークです。
導入することで、経営層から現場まで目標を共有でき、チーム間の連携や透明性が高まります。
また、従業員が自ら目標を設定・振り返ることで、主体性の向上やエンゲージメント強化にもつながります。さらに、短期的なレビューサイクルにより、変化の激しいビジネス環境にも柔軟に対応可能です。
ここでは、OKR導入によって得られる主なメリットを具体的に解説します。
組織目標の明確化と共有ができる
OKRを導入することで、組織全体の最重要課題にフォーカスし、そこへリソースを集中させる方向性を明確にできます。
さらに、社内でOKRを公開・共有することで、各部署・メンバーが目標の方向性を把握しやすくなり、バラバラな動きが減ります。
たとえば、OKRツールを使えば、組織目標からチーム・個人に目標をすり下ろす操作が効率化され、共有性が高まるというメリットもあります。
こうして、全員が目指す先を共通認識として持つことで、チーム間の連携や相互支援がスムーズになり、組織の一体感も強まります。
業務の優先順位が明確になる
OKRを導入することで、目標達成に直結する業務とそうでない業務を明確に区別できるようになります。
「今どの業務が最も重要か」「どこに時間やリソースを割くべきか」が可視化されるため、日々のタスクに優先順位をつけやすくなります。
チーム全体でObjective(目標)とKey Results(成果指標)を共有することで、メンバー間の方向性のズレも減り、業務の重複や無駄な作業を防ぐことができます。
その結果、業務効率の向上と、より戦略的な意思決定が可能になります。
職場内の連携が円滑に進む
OKRは、組織全体で目標を共有し、部門やチームを横断して連携を深める仕組みとして機能します。
Objective(目標)のすり合わせやKey Results(成果指標)の進捗共有を通じて、他部署の動きや優先課題を理解しやすくなり、サイロ化を防ぐことができます。
定期的なレビューやチェックインの場を設けることで、部門間の対話が活性化し、相互支援や情報共有の文化が生まれます。
結果として、組織全体が同じ方向に向かいながら、よりスピーディーで柔軟な協働が実現します。
モチベーション・エンゲージメントの向上
OKRを導入すると、従業員は自分の業務が組織全体の目標とどうつながっているのかを具体的に把握できるようになります。
その結果、「自分の仕事が会社の成長に貢献している」という実感が得られ、仕事への主体性や責任感が高まります。
また、目標設定や振り返りを通じて上司・チームと方向性を共有することで、認識のズレが減り、信頼関係の構築にもつながります。
こうしたプロセスの積み重ねにより、従業員のモチベーションとエンゲージメントが自然と向上していきます。
OKRの導入・運用プロセス
OKRを効果的に運用するには、単に目標を設定するだけでなく、組織全体で運用の流れを明確にし、継続的に改善していく仕組みが必要です。
導入初期には、経営層から現場までが同じ目的を共有し、OKRの意義やルールを浸透させることが重要です。
そのうえで、目標設定 → 進捗確認 → フィードバック → 振り返り のサイクルを回すことで、挑戦と学習が定着します。
ここでは、OKRを導入・運用する際の主なステップと、それぞれのポイントを解説します。
1.導入準備:目的の明確化と体制の整備
OKRを導入する前に、まずはなぜOKRを導入するのかという目的を明確にすることが重要です。
企業理念やビジョン、経営戦略を再確認し、OKRを通じて何を実現したいのかを社内で共有することで、導入後の一貫性が保たれます。
また、導入をスムーズに進めるためには、経営層・人事・現場が連携した推進体制を構築し、目標設定や運用ルールを示すガイドラインを整備しておくことも欠かせません。
これらの準備が整っていることで、OKRの目的が全社に浸透し、形骸化を防ぐ土台が築かれます。
2.OKRの設定:チームや個人ごとの目標を構築
OKRを設定する際は、まず企業全体のObjective(目標)とKey Results(成果指標)を策定し、その方針をもとに部門・チーム・個人のOKRへと段階的に落とし込みます。
このプロセスにより、組織の方向性と現場の取り組みを連動させ、全員が同じ目的に向かって進める体制を整えることができます。
各層でOKRを策定する際は、整合性と現実性を両立させることが重要です。
上位目標に沿いつつも、チームや個人が自ら考え挑戦できる内容にすることで、納得感の高い目標設定が実現します。
3.目標の共有:組織内のすり合わせ
OKRを効果的に運用するためには、各層で設定したOKRを組織全体に公開・共有することが欠かせません。
企業・部門・チーム・個人のOKRを可視化することで、目標同士の矛盾や重複を防ぎ、相互の整合性を保つことができます。
また、公開されたOKRをもとに、関係部署やチーム間で方向性のすり合わせや連携強化を図ることも重要です。
このプロセスを通じて、組織全体が同じゴールを共有し、部門間の壁を越えた協働と透明性の高いマネジメントを実現できます。
4.運用:定期的な進捗確認の実施
OKRは設定して終わりではなく、定期的な進捗確認(チェックイン)を通じて改善を重ねることが重要です。
週次や隔週などの短いサイクルで進捗を共有し、現状と目標のギャップを明確にします。
そのうえで、課題やボトルネックを特定し、必要に応じて行動計画や優先順位を見直す柔軟な調整を行います。
また、中間レビューの場では、チーム内で成果を共有し合うことでモチベーションを維持でき、目標達成への一体感も生まれます。
こうした小さな振り返りの積み重ねが、継続的な改善と成長につながります。
5.振り返り:次期OKRの再設定
OKRは設定して終わりではなく、定期的な進捗確認(チェックイン)を通じて改善を重ねることが重要です。
週次や隔週などの短いサイクルで進捗を共有し、現状と目標のギャップを明確にします。
そのうえで、課題やボトルネックを特定し、必要に応じて行動計画や優先順位を見直す柔軟な調整を行います。
また、中間レビューの場では、チーム内で成果を共有し合うことでモチベーションを維持でき、目標達成への一体感も生まれます。
こうした小さな振り返りの積み重ねが、継続的な改善と成長につながります。
OKR作成時の注意点
OKRは、挑戦的な目標を掲げて組織の成長を促すフレームワークですが、設計の段階で誤りがあると期待した効果を発揮できません。
現実からかけ離れた目標や、曖昧な成果指標を設定すると、従業員が混乱し、制度そのものが形骸化してしまう可能性があります。
また、部門や個人ごとのOKRが整合していないと、組織全体の方向性がぶれ、成果が分散してしまう点にも注意が必要です。
ここでは、OKRを作成する際に意識すべき代表的な注意点を解説します。
成果指標の発展
OKRを作成する際には、成果指標(Key Results)をどのように設定・発展させていくかが重要です。
数値で測定できる指標だけに頼ると、短期的な成果に偏りやすく、挑戦的な目標を十分に評価できないことがあります。
そのため、まずは測定しやすい定量的な指標から始めつつ、徐々に質的な変化や行動改善も評価できる定性的な指標を組み合わせていくことが有効です。
これにより、目標達成度を多角的に把握でき、組織や個人の成長過程を適切に評価できるようになります。
目標の位置が低くならないよう注意
OKRでは、目標が現実的すぎると本来の効果を発揮できません。
「確実に達成できる範囲」で目標を設定してしまうと、組織としての成長余地が縮小し、挑戦意欲も生まれにくくなります。
OKRの本質は、少し背伸びをしなければ届かない挑戦的な目標を掲げることにあります。
そのため、失敗を過度に恐れず、「7割達成でも成功」と捉える柔軟な評価基準を設けることが大切です。
また、上司やチームが挑戦を後押しする文化を醸成することで、従業員が積極的に高い目標へ挑める環境を整えることができます。
目標に対する成果指標が不十分
OKRでは、掲げた目標(Objective)に対して、適切で十分な成果指標(Key Results)を設定することが欠かせません。
成果指標が曖昧だったり数が不足していると、目標達成度を正しく測れず、日々の行動改善や優先順位づけが難しくなります。
たとえば「顧客満足度を高める」というObjectiveに対して、「問い合わせ件数を減らす」だけをKRにしてしまうと、真の改善度合いを把握できません。
複数の角度から指標を設定し、量(数値目標)と質(顧客の声やプロセス改善)を組み合わせることで、目標達成度をより精緻に評価できるようになります。
会社目標とのズレ
OKR運用でよく見られる課題のひとつが、個人やチームの目標が会社全体の方針とズレてしまうことです。
上位のObjectiveと整合していないOKRを設定すると、組織全体で同じ方向に進むことが難しくなり、結果としてリソースの分散や優先順位の不一致を招く恐れがあります。
こうしたズレを防ぐためには、まず企業全体のOKRを明確に共有し、部門・チーム・個人がその方針を踏まえて設定するプロセス(カスケード設計)が欠かせません。
また、運用中も定期的に進捗を確認し、上位目標との整合性を見直す仕組みを取り入れることで、方向性を常に一致させることができます。
OKR導入と運用を成功させるためのポイント
OKRは、ただ導入するだけでは成果につながりません。
制度として形だけ運用しても、現場での納得感や挑戦意識が伴わなければ、すぐに形骸化してしまいます。
OKRを定着させ、組織全体の成長を促すためには、経営層の理解とリーダーの支援、現場の主体性、継続的な改善が不可欠です。
ここでは、OKRを組織に根づかせ、効果的に運用していくためのポイントを解説します。
自社に合ったOKRツールを選定する
OKRを継続的に運用するには、自社の業務フローや組織体制に合ったツールの選定が欠かせません。
ツールを導入することで、各チームや個人のOKRを一元的に管理でき、進捗状況の可視化や定期的なレビューもスムーズに行えるようになります。
また、OKRを全社で共有することで、部門間の連携や情報共有の促進、透明性の高いマネジメントにもつながります。
ただし、機能が複雑すぎると現場が使いこなせず形骸化する恐れもあるため、使いやすさ・柔軟性・サポート体制を重視して、自社の運用スタイルに合ったツールを選ぶことが重要です。
ストレッチゴールの設定とスコアリングをおこなう
OKRでは、あえて高いハードルの目標(ストレッチゴール)を設定することが重要です。
達成可能な範囲にとどまらず、少し背伸びをしなければ届かない水準を掲げることで、個人やチームの成長を促します。
ただし、目標が高すぎて現実味を欠くと逆効果になるため、7割程度の達成で成功とみなす柔軟な評価基準を設けることがポイントです。
また、四半期や月次などのスパンでスコアリング(数値評価)を実施し、成果と課題を可視化することで、次期OKRの改善につなげられます。
このプロセスを繰り返すことで、挑戦と学習を両立した組織文化が醸成されます。
フィードバックを定期的におこなう
OKRを効果的に運用するには、人事評価とは切り離したフィードバックの場を定期的に設けることが重要です。
OKRの目的は、成果を査定することではなく、挑戦の過程を共有し、成長を促すことにあります。
そのため、週次や月次でのミーティングを通じて、達成度や課題、学びを対話的に振り返る機会をつくりましょう。
また、OKRを全社的に公開・共有することで、チーム間の透明性が高まり、お互いの進捗を称賛し合える文化が醸成されます。
こうしたフィードバックの習慣が、従業員のエンゲージメント向上や、組織全体の一体感につながります。
業界別・職務別OKRの具体的な活用法
OKRはあらゆる業界・職種に導入可能な目標管理手法ですが、効果的に活用するためには、自社の業界特性や職務内容に即した設計が欠かせません。
たとえば営業部門では売上や商談数などの成果指標、開発部門では品質改善やリリース速度といった指標が重視されるなど、設定すべきOKRは業務内容によって異なります。
ここでは、業界別・職務別に具体的なOKRの活用例を紹介し、自社での運用イメージを掴めるよう解説します。
営業
営業職のOKRでは、企業やチームの売上向上に直結する目標が設定されることが一般的です。
たとえばObjectiveとして「新規顧客の開拓」を掲げる場合、Key Resultsには「アプローチ件数」「商談化率」「新規受注数」などの具体的な数値指標を設定します。
また、数値だけでなく「問い合わせ対応の迅速化」「既存顧客の紹介制度の立ち上げ」など、売上につながる行動プロセスも評価対象とすることで、短期的成果と中長期的成長を両立できます。
OKRを導入することで、営業担当者一人ひとりが優先すべき行動を明確にし、自主的に動ける仕組みを構築できます。
マーケティング
マーケティング職は、自社の商品やサービスを必要とする人々に対して、その存在を認知させ、選ばれる仕組みを構築する役割を担っています。
そのためOKRでは、「誰に・どのように情報を届けるか」や「購買意欲をどう高めるか」といった業務に直結する目標を設定することが効果的です。
たとえばObjectiveに「見込み顧客の認知拡大」を掲げ、Key Resultsとして「Webサイト訪問者数の30%増加」「セミナー申込数の2倍化」「資料DLから商談化率15%達成」などを設定します。
数値成果だけでなく、「ターゲットに刺さるコンテンツ制作」や「広告運用の改善提案」といった行動ベースのKRを組み合わせることで、施策全体の精度を高めることができます。
人事
人事職におけるOKRでは、人材の採用や確保を中心とした組織づくりが主要なテーマとなります。
たとえば新チームの立ち上げが予定されている場合、Objectiveとして「必要なスキルを持つ人材の確保」を掲げ、Key Resultsには「エンジニア3名の採用」「応募数を前期比150%に増加」「スカウト返信率20%達成」など、具体的な数値や手段を設定します。
また、採用だけでなく「オンボーディング体制の整備」や「離職率の低下」など、採用後の定着・育成を含めたOKRを設計することで、人材戦略全体の質を高めることができます。
このようにOKRを通じて、組織の成長フェーズに応じた柔軟な人事戦略を推進することが可能です。
製造職
製造職におけるOKRでは、製品の品質向上が重要なテーマのひとつです。
企業全体のObjectiveとして「業界をリードするトップ企業への成長」を掲げる場合、その実現には現場レベルでの品質改善と生産性向上の取り組みが欠かせません。
たとえばObjectiveを「不良率の低減による品質向上」と設定し、Key Resultsには「不良率を前期比30%削減」「検査工程のリードタイムを20%短縮」「改善提案数を月10件に増加」など、具体的な行動指標と成果指標を組み合わせます。
このようにOKRを導入することで、現場の一人ひとりが自分の業務が企業目標にどう貢献しているかを実感しながら、継続的な改善活動を進めることが可能になります。
OKR導入企業の成功事例
企業がOKR(Objectives and Key Results)を導入する背景は、組織の目標を明確にし、個人やチームが同じ方向に進むためです。ここでは、OKR導入によって成果を上げた代表的な企業の事例を紹介します。
Googleでは、毎四半期に全社での会議を開き、OKRの公開と評価を行っています。OKRの目標は、個人の価値観や信念に基づいて決められます。上司は、頻繁に部下との面談を行い、部下の現状や考えを把握することができます。それと同時に、企業が掲げる目標や戦略に対して、全社員から理解を得られることにもつながります。OKRによってコミュニケーションの活性化につながります。
メルカリ
メルカリでは、OKRとMBOを併用して評価を行っています。3か月に一度データを基に、社員との面談を行っています。半年ごとに各チームのOKRの共有、理解のために合宿を実施しています。全社OKRについても、トップダウンではなく、全員で決定をしています。
Chatwork
Chatworkでは、OKRを「挑戦の姿勢」を評価する仕組みとして位置付けています。
評価制度は「業績評価」「行動評価」「全社業績」の3つの観点から構成され、それぞれにグレードごとの係数が設定されています。単に目標達成率を評価するのではなく、どれだけチャレンジしたかを重視する点が特徴です。
この運用により、社員が失敗を恐れずに高い目標に挑戦する文化が根付き、組織全体の成長マインドが醸成されています。
intel
Intelは、1970年代にOKRを導入した先駆的企業です。当時、事業が多角化していたことで、各部門の取り組みがバラバラになっていたことが課題でした。
OKR導入によって、分散していた施策を一つの戦略に統合し、全社的に共有する仕組みを構築。経営層から現場までが同じ方向を向くようになり、経営の再建に成功しました。
この取り組みは、のちにGoogleをはじめとする多くの企業の参考モデルとなり、OKRがグローバルに広まるきっかけとなりました。
Sansan
クラウド名刺管理サービスを展開するSansanでは、当初は個人単位でOKRを設定していました。しかし、個人目標の達成が必ずしも組織全体の成果に直結しない課題が生じたため、チーム単位のOKRへと運用をシフト。
部署間でのOKR共有ミーティングを積極的に実施し、目標達成に向けて議論を重ねる場を設けることで、チーム連携を強化しています。
この取り組みを通じて、全社の一体感と納得感のある評価制度を実現しました。
OKRを運用するならスキルナビ!
OKRの効果を最大化するには、目標設定から進捗管理、スキル可視化までを一元的に行える仕組みが欠かせません。
「スキルナビ」なら、OKRと人材育成を連動させ、従業員一人ひとりの成長を組織全体の成果につなげることができます。
スキルマネジメントの観点から、OKRの運用をより戦略的に進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。