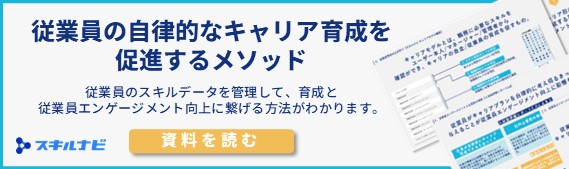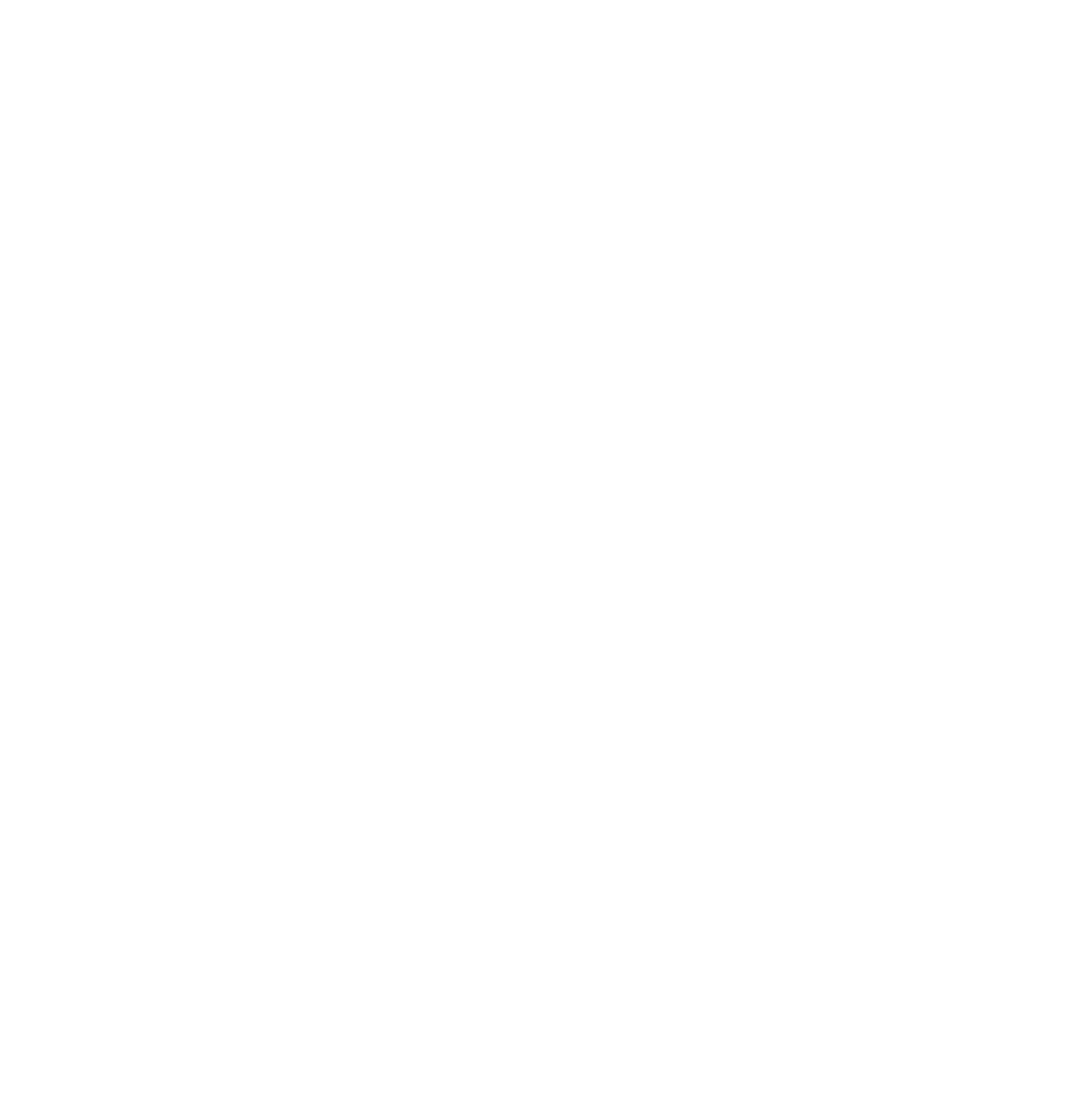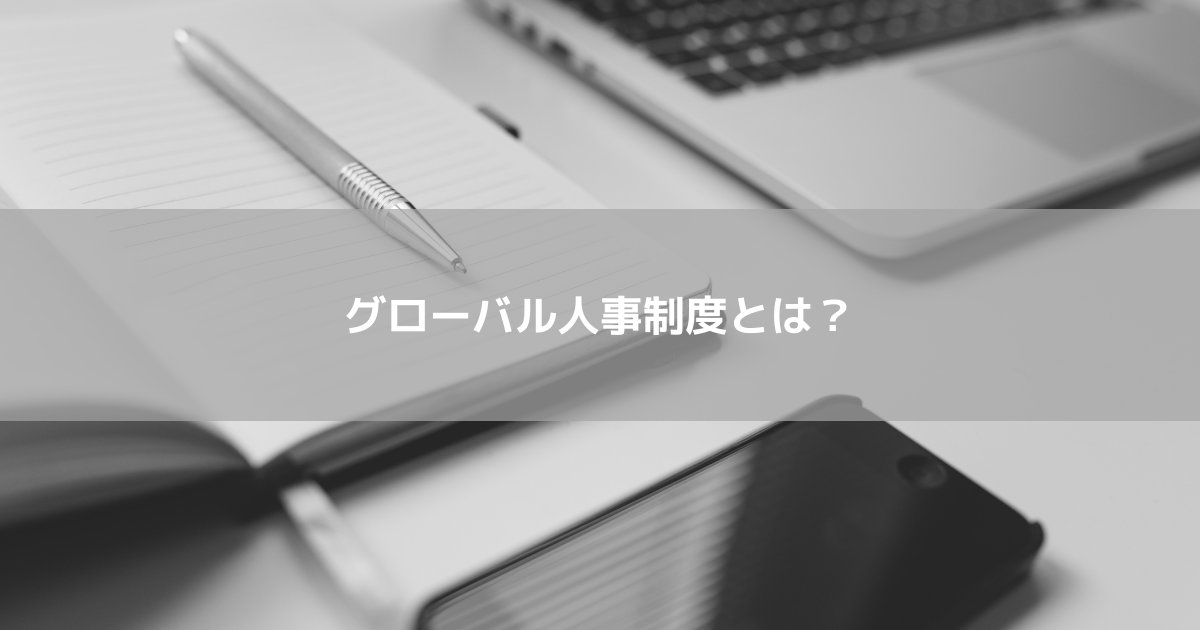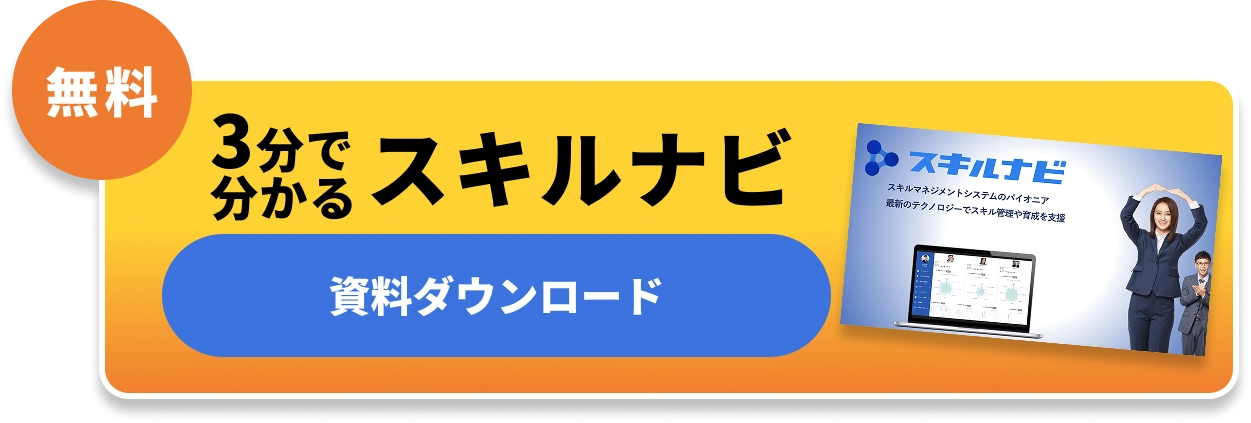タレントマネジメントとは?意味や目的、メリットと導入方法を解説

タレントマネジメントは、90年代にアメリカで導入されたことにより注目を集めました。
日本国内でも従業員の働き方の価値観の変化や、人材の流動化などの社会情勢の変化により、多くの企業担当者がタレントマネジメントに注目しています。
本記事では、タレントマネジメントの定義や具体的内容、そしてタレントマネジメントシステム導入のポイントなどをご紹介します。
タレントマネジメントとは
- タレントマネジメントの意味
タレントマネジメントとは、従業員が持つタレント(英語で「能力・資質・才能を意味する」)やスキル、経験値などの情報を人事管理の一部として一元管理することによって組織横断的に戦略的な人事配置や人材開発を行い、特に管理職層の業務遂行や育成をサポートすることを指します。
人材が備えている能力・スキルを可視化し、そのパフォーマンスを最大活用するための戦略であり、人材の基本情報だけでなく、保有している資格や経歴といった情報を管理することで、適切な業務配置や育成の方針を決定できます。
マネジメントをスムーズに行うために開発されたツールが「タレントマネジメントシステム」です。
この戦略が注目された理由として、時代とともに社会が変化したことがあげられます。
終身雇用が崩れ、高齢化が進んだことで人材の確保も難しくなったことから、限られた人材を活用する方法が求められた結果、タレントマネジメントという考え方が生まれました。
人事システムとの違い
人事システムは、人事情報を管理し、業務をスムーズに行うためのツールであり、人事業務の効率化を目的としています。採用や評価、給料計算や配属など、どれも組織が人材を活性化し、企業の最大の経営資源である「人的資本」を最大化するためにも欠かせません。
スタッフの勤怠記録を管理する勤怠システム、入職手続きや申請を管理する人事管理システム、勤怠情報から給与を計算する給与計算システムなどが人事システムに該当します。
人事業務全般をスムーズに行うことを目的としています。
タレントマネジメントが注目されている背景
タレントマネジメントは、元々アメリカのコンサル会社が定義した考え方です。
企業間が従業員が持っているスキルや資格を管理することで、企業戦略や人材戦略に落とし込み、企業成長に繋げる概念です。
では、なぜ日本でタレントマネジメントが注目されているのでしょうか。本項目では、タレントマネジメントが注目されている背景を解説します。
少子高齢化による労働人口の減少
一つ目は、少子高齢化による労働人口の減少です。
日本では少子高齢化が進み、労働人口(生産年齢人口)の減少が発生している状況です。
企業が優秀人材を確保する際、新卒一括採用に注力するだけでは、企業へ従業員の育成のコストやリソースがかかってしまい、効率的な採用が実施できません。
また、即座に優秀な人材が確保できないため、年齢や国籍を問わない優秀な労働力の確保が企業にとって重要となります。
労働に対する価値観の変化
続いては、労働に対する価値観の変化です。
元々、日本企業の採用方法はメンバーシップ型採用という、いわゆる正社員採用が一般的でした
。終身雇用を前提とし、総合職として採用をする雇用方法です。
しかし2020年に日本経済団体連合会(経団連)の当時会長である中西氏が「一つの会社でキャリアを積んでいく日本型の雇用を見直すべき」と提言したことで、現代社会に合わせた採用方法に見直されるきっかけとなりました。
少子高齢化や人口減少に陥っている現代日本の企業は、正社員という雇用方法以外にも、時短勤務や契約社員、フリーランスなどの柔軟な雇用方法に対応することが重要です。
デジタル技術の進化
以前は従業員のスキルや適性、成果などの資質を客観的に評価することは難しく、評価基準も属人的になりがちでした。
しかし、近年のデジタル技術の進化により、人材データの収集・分析・可視化が容易になり、個々の特性や成長度合いを客観的に把握できる環境が整ってきました。
これにより、タレントマネジメントが可能な環境が整っているため、近年タレントマネジメントが注目されています。
人的資本経営の推進
近年注目されている人的資本経営は、人材を企業価値向上の源泉と捉え、戦略的に育成・活用する考え方です。
その実現には、スキルや経験、適性などを踏まえた「適切な人材ポートフォリオの構築」と、「従業員データの定量把握・分析」が欠かせません。
上記二点の実行にはタレントマネジメントが不可欠なため、人的資本経営を推進するために、タレントマネジメントの重要性が一層高まっています。
タレントマネジメントの目的
タレントマネジメントの最大の目的は「経営目標の実現」です。
この目的を達成するために、タレントマネジメントを通して人材の調達・育成・配置・定着を効果的におこなっていくことが重要です。
本項目ではそれぞれの内容について解説します。
人材調達
近年、少子高齢化や労働人口の減少という社会的背景から、人材調達の重要性が高まっています。
そのため、採用活動や社内の人材発掘により、経営目標の達成に必要な人材を集めることが必要であり、タレントマネジメントを通じた人材要件の明確化や人材発掘が求められています。
人材育成
求める人材像と現状の差を埋めるため、新たな業務経験を積ませたり、教育プログラムを提供したりすることも重要です。
そのために、タレントマネジメントを活用して、現状の従業員のスキルを可視化し、個々人に対して適切な育成計画をたてることが必要となっています。
人材配置
経営目標を実現するために、能力やスキルを発揮できるポジションに人材を配置することで成果を最大化することも重要な取り組みのひとつです。
タレントマネジメントを活用することで、従業員のスキルや志向性を把握し、適切な人材配置が可能になります。
人材定着
最後に、調達や育成した人材に長く活躍してもらうために、モチベーション維持やキャリア開発に取り組むことも重要な取り組みのひとつです。
タレントマネジメントにより、従業員のキャリア志向や適性にあった人材配置や育成計画が実現されることで、人材の定着につながるでしょう。
タレントマネジメントのメリット
これまで、上項でタレントマネジメントについて大まかな概要について説明しましたが、具体的にどんなメリットを持っているのでしょうか。今回は5つに分けて紹介します。
人材配置の適正化
一つ目は、人材配置の適正化です。
企業がタレントマネジメントを実施せず、自社に所属する従業員のスキルや能力を正確に把握できていないと、例えば業務に人員をアサインする際に、適切な人材を入れ込むことができない可能性が考えられます。
また、効率的な業務運営が出来ない可能性も考えられます。
そこで、企業がタレントマネジメントを実施し、活用することで、適切な人材配置が可能となるので、業務アサインを効率化することに繋がります。
人材育成
二つ目は、人材育成です。
タレントマネジメントを実施すると、従業員の能力やスキルを適切に把握できます。
そのため、例えば育成したい従業員と他の従業員とで比較をした際、保有している能力や得意分野、長所短所などを可視化をし、分析することが可能です。
従業員が将来的にどのような人物になりたいのかというキャリアビジョンを基に、人材育成計画の立案に繋げることができます。
そのため、タレントマネジメントは効率的なキャリア支援を実践するのに重要な施策です。
従業員のモチベーション向上
三つ目は、従業員のモチベーション向上です。
タレントマネジメントを企業に導入すると、職務能力に限らず、ポータブルスキル、将来的に身につくスキルにも注目されます。
そのため、一人ひとりの適性を見極めた人材配置や育成計画が実現されることで、従業員は自身の成長や企業への貢献を実感しやすくなります。
その結果、従業員の仕事に対するモチベーションが向上し、定着や採用への好影響が期待できます。
生産性の向上
四つ目は、企業の生産性向上につながるということです。
タレントマネジメントを実施することで、従業員一人ごとのスキルや経験に合った部署や業務への配置が可能となるので、結果的に社員の能力を最大限引き出すことができます。
人材配置の適正化、人材育成、従業員のモチベーション向上の三つにより、結果的に従業員と企業の生産性の向上に寄与します。
顧客満足度アップ
タレントマネジメントによって従業員一人ひとりの能力や適性に合った業務配置や育成が行われると、仕事へのモチベーションやエンゲージメントが高まります。
これにより業務の質やスピードが向上し、ミスやトラブルの削減、提案力や対応力の強化につながります。
その結果、顧客に対してより高品質なサービスや製品を提供でき、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
タレントマネジメント導入の準備
企業が導入し上手く活用できれば、企業運営や人材戦略にメリットをもたらすタレントマネジメント。
しかし、タレントマネジメントを企業内でいざ実践しようと取り組んでも、ポイントや順序を抑えないと施策が形骸化してしまう可能性があります。
本項目では、タレントマネジメントの成果を最大化するための導入準備方法をお伝えします。
人材情報の可視化
従業員に関するスキルや個人情報、および組織情報などを可視化することで、企業に所属している従業員が目指すべき人材の姿と現状との間にある差分を明確化することができます。
差分が明確になることで、そのギャップを埋めるための経営戦略の立案や適切な人材配置、更には人事評価制度の仕組みなどを最適化することができます。
また、タレントマネジメントを導入する際は、以下の人材情報を取り込むことで、組織の人材情報の可視化に寄与します。
- 【基本的なデータ】
年齢や配属先、ポジション、入職日など、会社として利用する頻度が多いデータを取り込みます。配属先やポジションは変わりやすいので、適宜修正する必要があります。
- 【スキル】
仕事を行ううえで必要な知見や技術だけでなく、他の人とのやり取りや部下の管理能力なども含めて入力します。可能であれば、保有資格や長所なども追加しておくと、今後役に立つ可能性があります。
- 【業務内容・成果】
仕事における内容やその成果、成功した事項などを取り込みます。
- 【勤怠】
勤怠データを取り込んでおけば、行動にあわせた成果を分析したり、業務過多によるメンタルの変動をいち早く察知可能です。
- 【独自的なマインド】
表面上では判断しにくい人材の立ち位置や思考パターン、価値なども可能であれば入力しておきましょう。
将来的なポジションやチーム配置を考える際に役立ちます。
タレントプールの作成
人材情報の可視化を実現したあとは、経営戦略の遂行に必要なタレントを特定します。
タレントを特定することで自社内で補填できるのか、もしくは外部から新たに調達が必要なのかを判断することができます。そのためには、タレントプールの作成が有効です。
タレントプールとは、「将来的に自社で採用する可能性のある人材データベース」を指します。
タレントプールに自社が採用する可能性がある人材のデータが蓄積しているため、面接回数を減らすなど採用活動の工数を削減できます。
自社との適正がある人材があらかじめタレントプールによって選別されているので、採用後の早期離職などといったミスマッチを減らすこともできます。
人材情報を可視化し、タレントプールなどでデータベース化しておくことで、タレントマネジメント導入後の方向性が明確化するのでタレントマネジメントの効果が向上します。
目的・目標の明確化
続いては、目的・目標の明確化を行いましょう。
目的と目標が定まっていなければ、タレントマネジメントを運用しようとしても、運用が形骸化し得る可能性があります。
何を目的にタレントを増やすのか?どのような人材を求めるのか?何人必要なのか?など訂正的な情報だけでなく、5W1Hの定量的な目標まで落とし込むことが重要です。
タレントマネジメントをただ実施するだけではなく、事前にしっかり経営戦略と人事戦略と連動させることが重要です。
必要項目の整理
次は、タレントマネジメント時にデータとして取り入れたい項目を調整し、うまく活用することが重要です。
たとえ入力可能なデータが豊富にあっても、うまく利用できなければ意味がありません。
またデータは取り込んだら完結ではなく、常に新しい情報を得られるようにリニューアルし続ける必要があります。
社内にはどんな特徴の人材が働いているのかを管理することが、成功への近道です。
浸透させるための広報活動や研修
新鮮な情報をいつでも管理するためには、従業員と力をあわせる必要があります。
しかし、概要をよく把握していなかったら個人的なデータの収集を怪しまれる可能性があるでしょう。
データを集める理由、利点をしっかりと説明して、社内の理解を深めていくことが大切です。講習や研修を開き、どのようなゴールを描いているのか、データをどのような用途で使用するのかを共有するのもおすすめです。
運用フローの整理
最後は、運用フローの整理です。
実際の運用において、過去の実施内容やその成果を見つめ直して、次のアクションに生かすことが重要です。
そのためには、以下の流れを整頓してみましょう。
- 現段階の企業の状況を理解しておく
- 社内の人材をよく分析して必要な項目を決定する
- 課題達成のためのプランを作る
- プランに則って適切な人材の確保、業務配属を行う
- 実行した結果を分析し、次のアクションに備える
このように、これまでの情報を活かしたうえで、企業特有の流れを組み立ててみましょう。
タレントマネジメントの導入方法
実際に導入した後は、どのような流れを行えば成果が出るのでしょうか。
ここでは、具体的な実践方法を各段階に分けて解説します。
1.採用・育成計画書を作成する
社内の従業員のデータを集めた後、いくつかのカテゴリに分け、そのカテゴリに適した教育プランを作ります。
カテゴリ内に十分な人材がそろっていない場合、新しく採用を行うことも検討しましょう。
一方で、1つのカテゴリに溢れるほど人数がいる場合、再びプランを組み直すことも考えましょう。
これは導入の段階で核となる要素であるため、方針変更はあっても目的から逸れずに計画をしておくことが大切です。
2.人材を採用・配置する
次の段階では、作ったプランにあわせて人材を確保したり、適切な人員配置を行うことを検討します。
自社で働く従業員にも計画を共有して、実施する施策の目的や、目指すべきゴールを通達しましょう。
このような取り組みによって共通認識を持つことで、組織全体が一体感を持つことができ、施策の前進性が高まります。
これらのアクションが従業員にも伝わるように、明確な意思を持って実施しましょう。
3.人事評価・レビューを実施する
続いては、人事評価・レビューを実施することです。
2で新しい戦力の確保や配属を変更した後は、職場環境がこれまでとは異なることが予想されます。
そのため、配属配置をした従業員と細かく面談などを実施しながら評価を実施し、どのような効果が現れているのか、また、どのような課題点があるのかをチェックしましょう。
従業員それぞれの成果や生産性はもちろん、業務姿勢に変化がないかをよく確認しておくことをおすすめします。
4.異動・能力開発を実施する
仕事面で指導が必要だと判断した場合、不足しているスキルを養うために研修や教育によるサポートを行います。
思うような成果が見られない場合、配属が適していない他にも、単純にスキル不足の可能性もあります。
その従業員が行う仕事の生産性を高めるためにも、企業として協力できる体制を整えておきましょう。
5.1~4を継続する
これまでの段階を踏んだら、そこで終了ではありません。
今まで実践したことを再度繰り返し、さらにブラッシュアップできるような体制を作ります。このサイクルを回転させるほど、企業としての成長につながるでしょう。
たった一度の実践で完了させるのではなく、一連の取り組みを反復する力が重要なのです。
また、PDCAの回し方やポイントを解説した記事がありますので、ご興味をお持ちでしたら下記をご確認ください。
タレントマネジメントでよくある失敗例
上手く運用すれば、企業にメリットを及ぼすタレントマネジメント。ここでは、よくある失敗例についてご紹介します。
手段が目的化している
タレントマネジメントでよくある失敗の一つが、「手段が目的化してしまう」ことです。
本来は経営戦略や組織課題を解決するために活用すべきなのに、データ収集やシステム運用そのものがゴールになってしまうケースが少なくありません。
社員情報やスキルデータを大量に登録しても、活用シナリオが不明確なままでは単なる「人材名簿」に留まり、現場からも負担感だけが残ってしまいます。大切なのは「何の意思決定に活かすか」を明確にした上で、最小限のデータ収集から始めることです。
評価制度が年功序列に依存している
タレントマネジメントを導入しても、評価制度が従来の年功序列型に依存していると十分な効果を発揮できません。
スキルや成果よりも勤続年数や年齢が重視される環境では、従業員がスキルを高めても評価や処遇に結びつかず、モチベーション低下を招きます。
また、優秀な若手が成長実感を得られず離職につながるケースも多いです。タレントマネジメントを機能させるには、スキルや成果に基づいた公平な評価基準を整え、キャリア開発や適材適所に直結させる仕組みが欠かせません。
従業員に人材戦略が浸透していない
タレントマネジメントを推進する際に多い課題が、経営層や人事部門が描く人材戦略が従業員に十分浸透していないことです。
組織としての方向性や育成方針が現場に伝わらなければ、スキルデータの入力や評価制度も「なぜやるのか」が理解されず、形だけの運用になりがちです。
その結果、従業員の協力が得られず、せっかくの仕組みも機能不全に陥ります。人材戦略を浸透させるためには、経営の意図や活用イメージをわかりやすく共有し、現場が自分ごととして取り組めるコミュニケーション設計が不可欠です。
従業員情報が更新されていない
適切にタレントマネジメントシステムを運用するためには、従業員のスキルや経験、役職、評価などの情報を正確かつ適時更新することが不可欠です。
運用が形骸化し情報更新が滞ると、現状との乖離が生じ、適切な人材配置や育成計画が立てられなくなってしまうため、情報の更新に対して明確なルールを設け、運用するように気をつけましょう。
導入後の運用が定着しない
タレントマネジメントは、制度やシステムを導入しても形だけの運用になってしまうケースがあります。
形だけの運用にとどまると、現場での活用が進まず、期待する成果も得られにくくなります。
そのため、定着をはかるために、研修や評価者・被評価者双方への運用上の疑問や課題に対応できるサポート体制を整備することが重要です。
タレントマネジメントを導入して組織のパフォーマンスを高めよう
効果的なタレントマネジメントのためには、システムによる情報の集約化が必須です。
今回のコラムで紹介した方法で戦略人事を推進するためのタレントマネジメントシステムを選ぶことで、管理職を含む各階層のスキルや経験を可視化し、適切な人材配置を行うことが可能になります。
当社が提供するスキルナビでは、従業員の保有する資格やスキルの集約が可能であるため、企業のタレントマネジメントの実践のための足がかりとして、スキルマネジメントの実践が可能です。
ご興味をお持ちの方は、下記よりお問い合わせください。