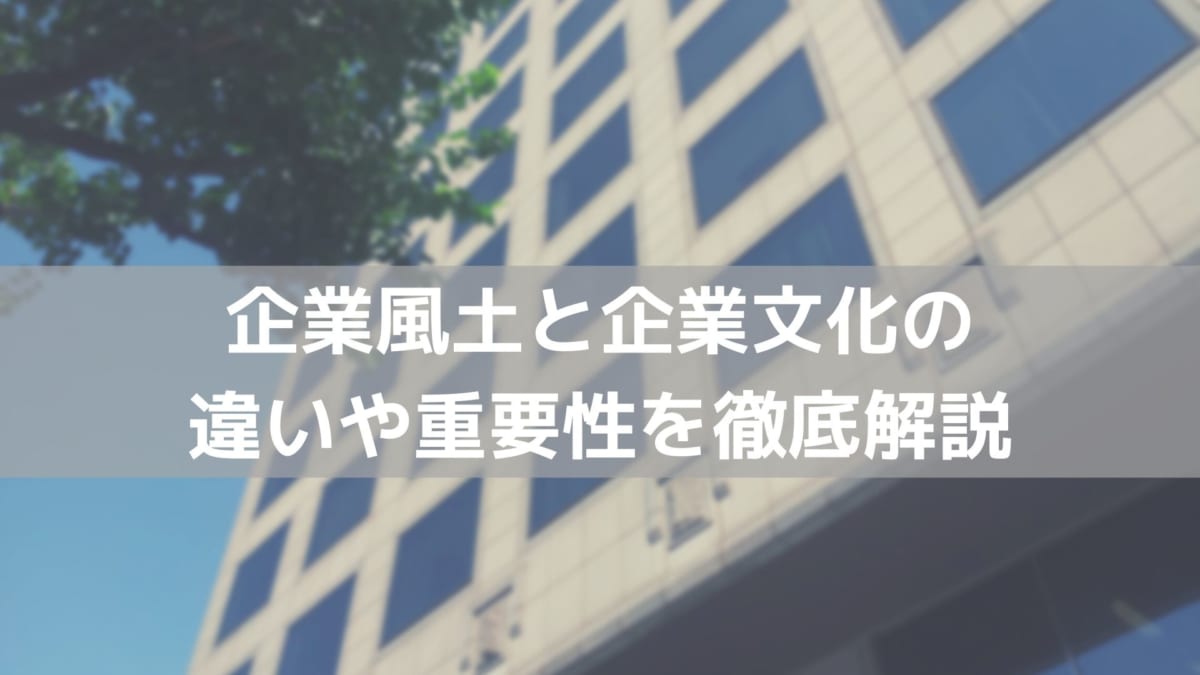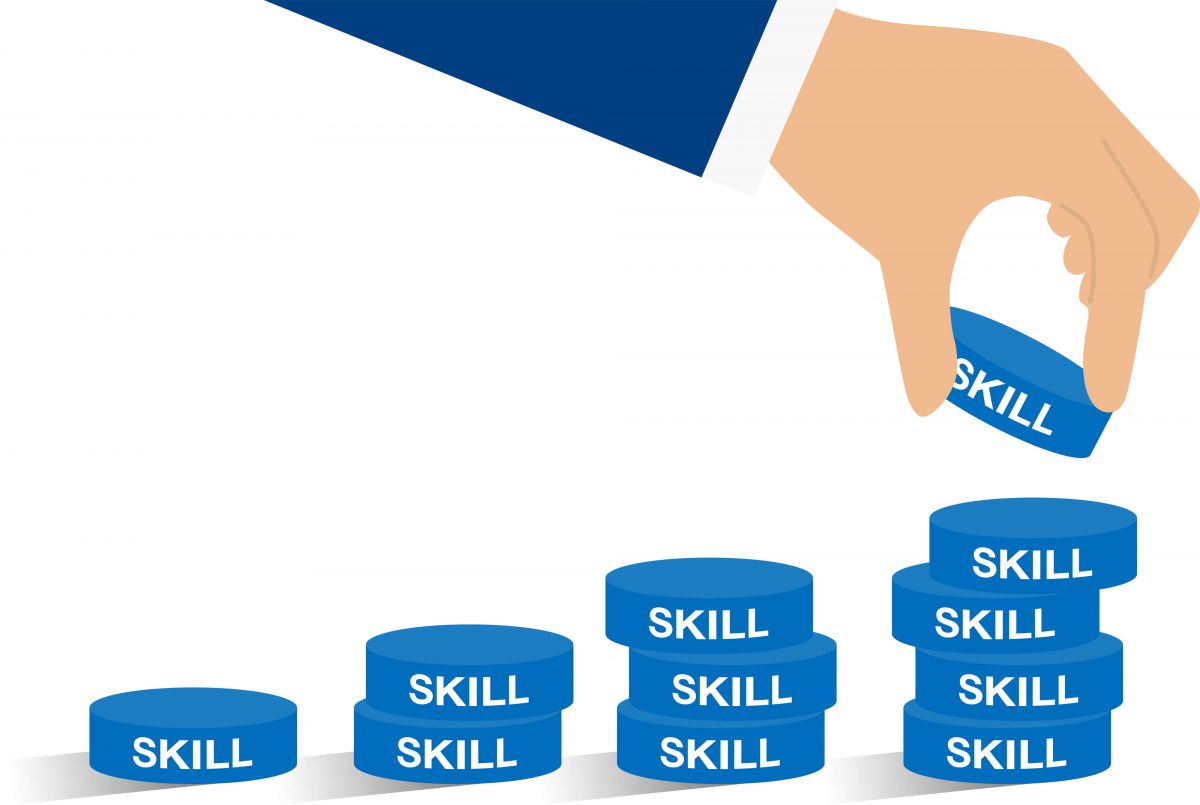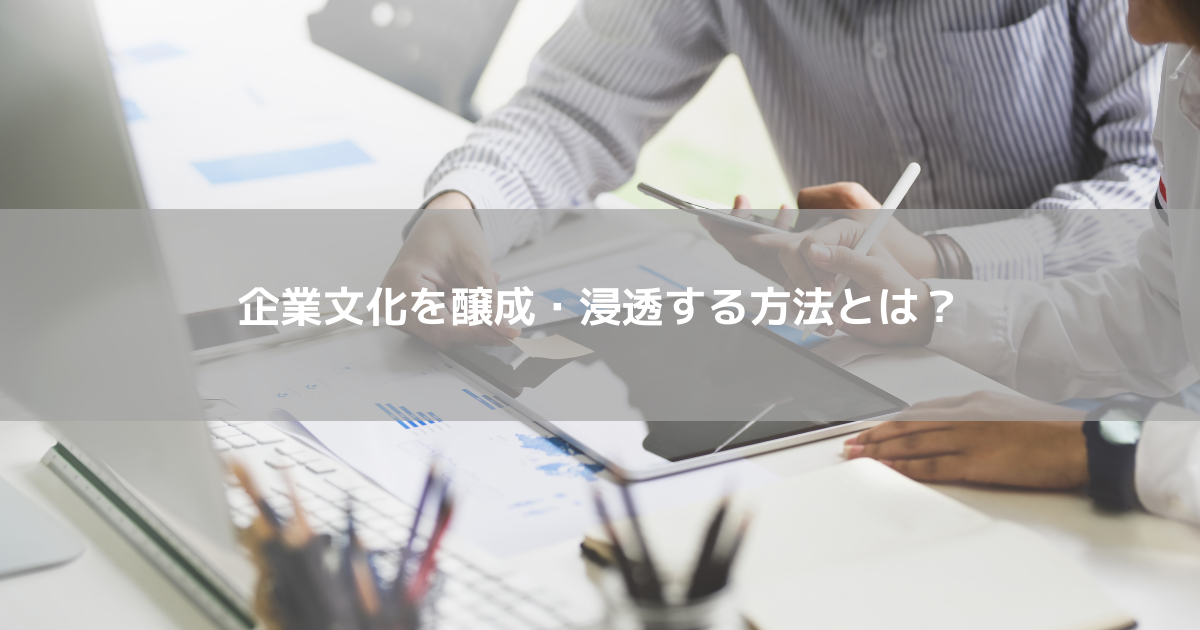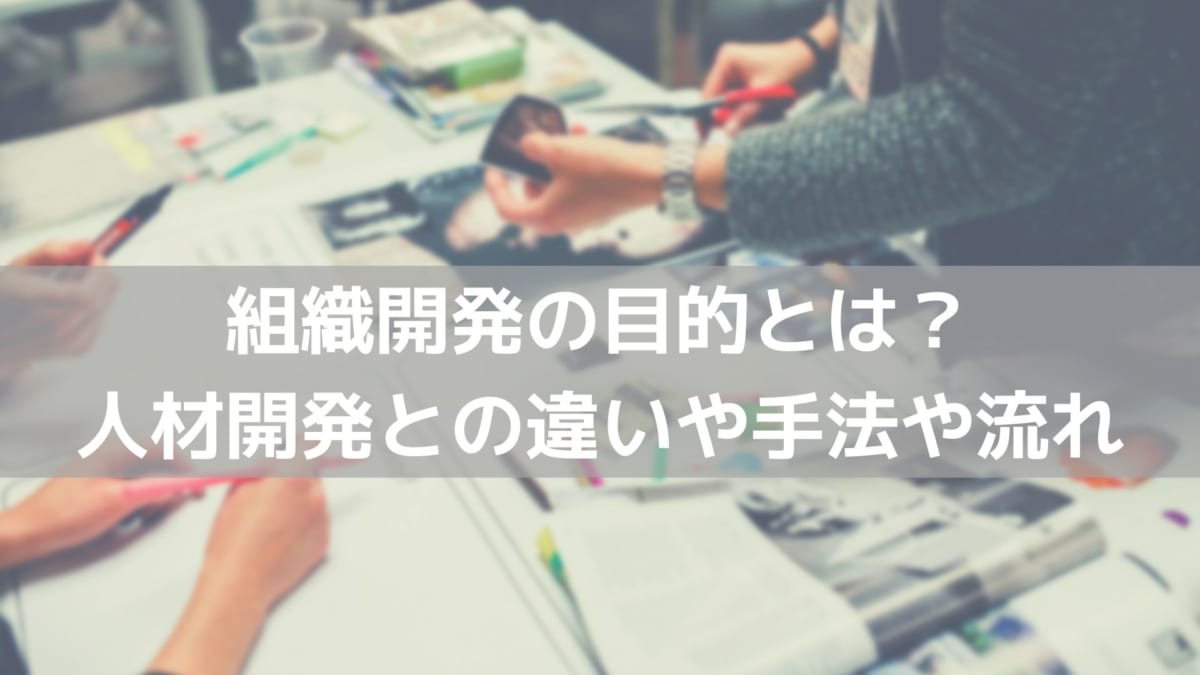人材開発とは?人材育成との違いや種類について解説

労働人口が減少している現在、昔の時代と異なり豊富な人材を確保することが難しくなりました。そのため企業が生き延びるためには、人材の「量」ではなく「質」が求められています。今回紹介する「人材開発」は、社員の質を高めるためには重要な鍵となる施策であり、企業として必ずおさえるべきポイントといえるでしょう。
人材開発とは何か
指導や研修により、社員のスキルや知識だけでなく、人としての対応力を身につけることを「人材開発」といいます。さらに具体的に述べると、以下の2つに分類します。
- 知識を提供することを「教育」
- スキルを身に付けさせることを「訓練」
この両方をうまく活用して、はじめてパフォーマンスを発揮するといえるでしょう。このポイントをおさえれば、社員のさらなる成長が期待できます。もちろん業界やチーム内で求められている能力は異なるので、それぞれに対応した点を中心に指導する必要があります。
人材開発と人材育成の違い
類似している言葉として、社員が足りていない能力を補う、あるいは新しいスキルを獲得するために実施する「人材育成」があげられます。この言葉は対象が若手の社員、あるいは管理職を指して使用する場合が多いです。反対に人材開発は、特定の社員を対象とするのではなく、すべての社員をターゲットとして使用します。
しかしどちらも「社員の能力を高める、スキルを身につける」という部分では、同じ言葉といえるでしょう。実際に使用するときは、両者を厳密に区別せずにどちらも同じような意味で扱うこともあります。
人材開発と組織開発の違い
人材開発とともに耳にする機会が多い言葉に、「組織開発」があります。これは、組織を対象にアプローチするもので、組織がより良い状態になることを目的とします。
例えば、従業員間のコミュニケーションの活性化を図るなどして、組織全体を活発にするなどの施策が挙げられるでしょう。
人材開発と組織開発は意味の異なる言葉ですが、両者は密接に関係しています。組織を構成している従業員の人材開発が不十分なまま、組織開発に取り組んでも期待する効果は得にくくなります。逆に、組織開発が不十分だと社内の雰囲気に悪影響を及ぼして、人材開発の進捗が悪くなる場合もあるでしょう。
人間の行動は、個人が持つ特性と個人が置かれた環境や状況が相互に作用して決まるとする「場の理論」をご存じでしょうか。これは、「組織開発の祖父」として親しまれる、ユダヤ系ドイツ人である心理学者クルト・レヴィンが提唱した理論です。
「場の理論」を企業に当てはめて考えてみましょう。従業員個人の能力や特性を伸ばす人材開発と、従業員が置かれる職場環境や社内の雰囲気や人間関係を改善する組織開発、両側面からのアプローチを行うことが重要だとわかるでしょう。
人材育成の対象と目的
入社して間もない社員を対象に、業務の基本となるスキルの定着を目的に実施します。具体的な項目として、以下があげられます。
- WordやExcelといったソフトの操作スキル
- 他社員と意思疎通を図るためのスキル
- 時間管理スキル
これらを修得した後は、それぞれのチームで必須となるスキルの獲得を目指します。対象が管理職の場合、マネジメントや適切な評価を下せるためのスキルが必要となるでしょう。その他にも業務配置の変更、あるいは職そのものの変化が起こったときも、新たな育成を実施します。
人材開発の対象と目的
特定の誰かを指定することはなく、対象は基本的にすべての社員であり、それぞれの能力の向上を目的に実施します。業務に対しての姿勢や考え方を見直すことでモチベーションを高めたり、今後のキャリアの選択肢を広げたりすることもあります。
人材育成と比べると目的の具体性に欠ける場面もあるため、社員が困惑することもあるでしょう。効果を最大化させるために、人事部を中心に取り組みを推進するだけでなく、他の社員と協力できるようなサポート体制の構築が大切です。
これからの人材開発に必要なこと
必要なことは3つあります。
組織開発と人材開発を同時に進める
人材開発の効果を最大限に発揮するためには、組織開発を同時進行することが欠かせません。人材開発と組織開発はお互いに影響しあっているため、どちらか一方だけ進めても思うような効果が得られないかもしれないのです。
同時進行する上で大切なのは、組織開発と人材開発を進める担当者同士がしっかり情報共有や議論を交わして連携することです。
もしも人材開発において「IT系に強い人材を育成したい」という目標があるとしたら、組織開発でもIT化やDX化などに取り組む必要があるでしょう。環境が整わないと、求める人材が育ちにくくなり、従業員個々の能力も伸びにくくなります。
社員が主体となる仕組み作り
人材開発を適切に進める上で重要なのが、従業員一人ひとりが主体性を持って取り組む仕組みや環境を整えることです。
人材開発では、強制的に研修時間を設けてセミナーや勉強会を受けさせるのは効果的ではありません。従業員個人の能力を伸ばし、必要な知識や経験が身につくように、従業員一人ひとりに合わせた実践の機会を提供するように心がけましょう。
何が成功して何が失敗したのか、その原因など、実体験を通して得た学びは従業員の成長の糧となるでしょう。だからこそ、従業員が自ら意欲的に学べる仕組みづくりに注力することをおすすめします。
しかし、従業員自身が経験を通して学びを得ることは容易ではありません。上司などによるコーチングや会話の機会を設けて、考え方や反省点などを導き出すサポートをしてあげるとより効果的です。
スキルアップのサポート体制を充実させる
せっかくやる気を持ってスキルアップに取り組んでいても、小さなことで行き詰まって取り組みを中断してしまう従業員がいます。従業員がモチベーションを維持するためには、いざというときに相談できるメンターの存在が必要です。
企業が人材開発を推し進めるなら、社内のサポート体制を充実させることが成功の鍵となるでしょう。
企業ができるサポートとして効果的な施策は、メンター制度だけではありません。従業員一人ひとりが、各々の好みで伸ばすスキルを検討できる制度や社内環境を整えても良いでしょう。個々がそれぞれのキャリアプランを考えながら、自主的にスキルアップに取り組むことが大切です。
人材開発部の役割・仕事・ミッション
ただ社員の開発を進めるだけでは思うような効果は得られません。ここでは以下の具体的な役割について理解しておきましょう。
- 経営戦略のブレイクダウン
- 人材開発のためのプラン作成
- プランの実行
①経営戦略・経営計画のブレイクダウン
現在行っている事業や今後の展望を見据えたうえで、細かい部分まで戦略を構築します。育成のために考えるポイントは、役職や立場によって異なるでしょう。経営に関係する部門では、以下のようなポイントについて検討します。
- 経営の視点で求められる社員について
- 条件に当てはまった人材を確保するためにはどのようなプランが必要か
また現場の各チームでは以下のようなポイントを考えます。
- 業務に対してのモチベーションが高まるか
- 専門の知識・スキルを保有するための指導を行うべきか
それぞれの視点を尊重しつつ、徐々にプランをすり合わせることが大切です。
②人材開発計画の作成
今後の方針が決定したら、研修カリキュラムやプログラムを作成します。直近で成果を生み出すだけでなく、今後戦力として活躍するために長期的な視点を持ったプランニングを行うことも重要です。
現在主戦力として業務に携わっているベテラン・中堅社員の活用も大切ですが、世代変化に対応するためにも、若手の社員を中心にプランを進めていきましょう。また人材を効率よく成長させるには、最新の社会のトレンドも理解しつつ、新しい技術を柔軟に取り入れることをおすすめします。
③計画の実行
詳細なプランを構築できたら、最後に実行するフェーズに移ります。このときに注意すべきポイントは、プランを実行する目的を共有することです。
- 何のために実施するのか
- 具体的な内容はどのようなものなのか
プラン開始前後に、上記の点を他社員と共有しましょう。事前告知せずに開始してしまうと社員は混乱してしまい、思うような効果が得られない可能性があります。スムーズにプランを進めるためにも、メリットや今後の方向性などの説明を十分に行い、理解をしてもらいましょう。
人材開発の種類
人材開発の種類は1つではなく、複数に分類されます。こちらでは以下の種類について詳しく解説します。
- OJT
- Off-JT
- 自己啓発
①OJT
実際の業務のなかで指導・訓練を行うことを「OJT」といいます。この手法はさまざまな職種で採用されており、今回紹介する種類のなかでも一番有名です。事前に獲得すべきスキルを決めて、その期限とゴールを設定しておくと、より効果的です。また注意点として、以下のポイントがあげられます。
- スキルを獲得するまで実施するかどうかを決めておく
- スキル獲得のための要素をおさえておく
- OJTを実施する担当社員の成長も見越しておく
上記の点に気を付けて実行してみましょう。
②Off-JT
職場以外で指導・訓練を行うことを「Off-JT」といいます。この手法はおもに外部のセミナーや研修のことを指しており、OJTと比較すると利用する頻度は少ないでしょう。しかし職場では得られない経験を学べるので、さまざまな知見を獲得したい場合に役立ちます。注意点としては、以下のポイントがあげられます。
- 社員の能力を考慮して実施する必要がある
- 実際の業務との関連性のあるものを選択する
- 社員が意欲的になるような内容を選択する
Off-JTの性質上、学習内容を柔軟に変更できないので、それぞれの社員の特性にあった内容を選択しましょう。
③自己啓発(SD:Self Development)
社員から進んで学習を行うことを「自己啓発」といいます。この種類の特徴として、OJTやOff-JTのような企業から訓練の機会を提供するのではなく、あくまでも社員の自発性に一任する傾向にある点です。そのためどんな学習をするのか、どんな方法で行うのか、などは特別決まっていません。細かいスケジュールは社員が管理するので、自主的に成長が見込めます。
注意点としては、以下のポイントがあげられます。
- ある程度方針をまとめてから社員に一任させる
- 勉強する方法に対する時間やコストは企業がサポートする
すべてを1から社員に任せるのではなく、内容が十分に固まるまでは企業も一緒にサポートをしてあげましょう。
人材開発の事前準備
3つの準備をしておきましょう。
必要な人材像を明確にする
企業の成長のために必要な人材は、どのようなスキルや経験、考え方を持っているのでしょうか。自社に合わせた人材開発を行い、その効果を最大化するためには、企業が求める人材像を明確にしていることが重要です。
まずは経営戦略やビジョンをもとに、どのような人材がどのポジションに必要なのか、人数なども明確にして、人材像をできる限り具体的にしましょう。
経営戦略やビジョンは、時代の変化や環境に応じて変化します。人事部としては、同じように求める人材像も柔軟に変化させ、企業の理想を実現できるように努めると良いでしょう。
個々に最適な人材開発のアプローチを選ぶ
人材開発は、ただスキルや知識を身につけるために行うのではなく、従業員が人として、また社会人としての対応力を身につけることを目指しています。そのため、人材開発において重要なのは求める人材が持つ思考手順や考え方、重視するポイントを従業員に学んで貰う必要があるでしょう。
しかし人材開発に取り組む以前は、従業員一人ひとりの考え方や仕事への向き合い方はバラバラな場合が多いものです。だからこそ個々に合ったアプローチ方法を選択して、人材開発を進めることが企業の課題だといえるでしょう。
例えば、営業部門の責任者が仕事において重視していることやトラブル対応に関する考え方を共有する機会があれば、営業担当者が将来の責任者として活躍できるようになります。
また、若手従業員を管理職などのポジションに昇格させるアプローチ方法も効果的です。実際に上位職を経験することで、必要な知識や経験、考え方を身につけることが期待できます。
人事データからタレントマネジメントシステムを整備する
人材開発を計画的に進めるためには、社内人事に関わる情報を適切に管理、運用していくことが重要です。そこで役立つのが、タレントマネジメントシステムです。
タレントマネジメントシステムとは、従業員一人ひとりの個人情報や保有スキル、過去の経験などを一元管理できるシステムのことです。わかりやすく情報を整理できるため、システムを利用することで人事戦略を打ち立てやすくなるでしょう。
こうしたシステムを活用して的確な人事戦略を練っている企業は多くありません。人材開発においても、求める人材像を決めたり、個々に合わせたアプローチを検討したりする際に、タレントマネジメントシステムが役立ちます。
面談の際の記録や上司の所感、従業員の考え方を知るためのアンケートの結果など、さまざまな情報をシステムに入力するようにすると、より一層効率的かつ効果的に人材開発を進められるでしょう。
■人材開発を進めるためのポイント
最後に人材開発をスムーズに行うためのポイントについてみていきましょう。はじめに行うべきは、社員の能力と企業の状況を把握することです。どんなスキルがあれば効率性・生産性が高まるのか、どの社員がそのスキルを持っているのかを理解していれば、具体的なプランを構築できます。
そして社員の潜在的な能力を見つけ出すために、業務配置を変えたり範囲を広げたりすることも大切です。この施策は常にPDCAサイクルを回して改善を行うものなので、毎日の社員の変化に気をつけながら行っていきましょう。
人材開発の企業事例
厚生労働省が実施している「キャリア支援企業表彰(平成24年〜27年)」と「グッドキャリア企業アワード(平成28年〜)」では、従業員の自主性を重んじたキャリア形成の支援を行った企業が表彰されています。
日本全体として、人材開発の重要性が認められているなか、企業は具体的にどのような取り組みを行うと良いのでしょうか。人材開発に取り組み成功した企業を紹介します。
- 三菱東京UFJ銀行
メガバンクの1つである三菱東京UFJ銀行は、従業員が自主的に学べる自己啓発制度として、学びの場を提供する取り組みを実施しました。平成27年にグローバルラーニングセンターを設立したことが、次世代を担うリーダーやグローバルに活躍できる人材育成に大きく貢献しています。
その他にも自己開発に役立つ講座や資格取得支援、オンライン学習サービスを提供することで、従業員が主体的にスキルアップに取り組める環境を実現しています。
- 博報堂
日本の大手広告代理店として知られる博報堂は、人材開発のために会社独自の大学を設立したのが特徴です。
「HAKUHODO UNIV.(博報堂大学)」と名付けられた大学では、従業員が自分の好きなタイミングで好きな内容のスキルを学べる仕組みが取られています。そのため、従業員の自主性が育ち、モチベーション高くキャリアアップを目指せるようになりました。
また、従業員の世代に適した考え方を身につけるための「世代別キャリア開発支援プログラム」を確立するなど、従業員の理解度や経験値に応じて適切な教育を受けられる制度をつくりました。
- 株式会社JTB
2020年度の「グッドキャリア企業アワード」で大賞を受賞した株式会社JTBは、日本の大手旅行会社です。JTBは社内の人材を何よりの資源と考え、人材開発に取り組みました。
「会社が人材を育てる」という考え方を転換させ、「会社は従業員一人ひとりの自己開発を支援するものだ」という考え方のもとでさまざまな施策を実施した点が特徴です。
具体的には、社内育成プラットフォームである「JTBユニバーシティ」を生み出しました。年間800本以上の集合研修やウェビナーの実施、eラーニングの作成、キャリア開発支援などを実施し、従業員が学び続けられる環境を整備しています。
また、スキルの習得だけでなく個人のキャリアプランなどを考える機会をつくっています。従業員が自己評価を行う人事評価シートには、「自分らしさの発揮」などの項目を織り込みました。これにより、従業員が自身を振り返り、自分の考えを持って行動できるような変化を促したのです。
人材開発は種類やポイントを理解して取り組もう
人材開発は企業のみならず社員の成長を促すためには欠かせない施策です。
しかしただ「重要だから」と、考えずに取り組んでしまうと、思うような結果は得られません。スムーズに進めるためにはどんな種類があるのか、どんなポイントに気を付けて取り組むべきなのかを考えることが大切です。
ぜひ今回の記事を参考に、人材の学習を推進してみましょう。